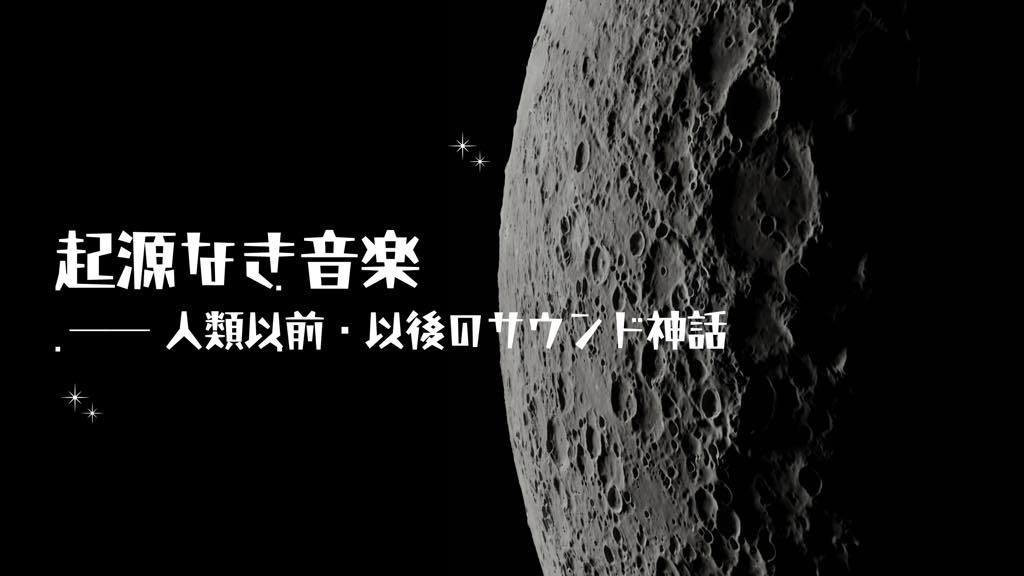COLUMN– category –
-

[妄想コラム]もしもカントリーとブルースが融合しなかったら──ロックンロール誕生以前の20世紀音楽史の空白
20世紀音楽の潮流を変えた最大の発明は、カントリーとブルースの融合である。そこから生まれたロックンロールは、世界を揺るがす文化現象となり、エルヴィス・プレスリーやビートルズの登場を可能にした。しかし、もしもカントリーとブルースが交わること... -

[連載:音の先へ]第1回:静かなる反逆 ── チャーリー・パーカーと出会った少年
イリノイ州の少年時代 1926年、イリノイ州オールトン。マイルス・デイヴィスは、裕福な黒人家庭に生まれ育った。彼の父は歯科医、母はピアノ教師という家庭環境で、音楽に親しみながらも、決して「貧困」や「不遇」に悩まされることなく成長した。だが、彼... -

[妄想コラム外伝]起源なき音楽 ── 人類以前・以後のサウンド神話 第一回:宇宙が最初に発した和音 ビッグバン・シンフォニー仮説
音楽の起源を問うとき、我々はつい人類や文明の誕生に焦点を置きがちである。しかし、そもそも“音”とは人間の文化に先立ち、はるか以前、宇宙そのものの生成の瞬間から存在していたのではないか。そう考えるだけで、我々の聴覚は一挙に時空を飛び越え、銀... -

[音の地球儀]第22回 ── スペインの深層:アンダルシアとフラメンコの原像
民族音楽は、その土地の暮らしや風土、信仰、歴史を音に刻み込んだ、人類の“声”である。電子音が世界を席巻する今もなお、世界各地には太鼓や笛、声と手拍子だけで継承されてきた音楽文化が息づいている。この連載では、アフリカのサバンナからアジアの山... -

[響き合うコーヒーと音楽の世界]第24回:マラカトゥーラ
こんにちは、リトル・パウです。今回、私が皆様をご案内するのは、中米の優良産地ニカラグアが誇る、大粒の個性派「マラカトゥーラ」の世界です。 マラカトゥーラは、ニカラグアで誕生した天然のハイブリッド品種で、マラゴジッペ(大粒で甘みが特徴)とカ... -

「AIが奏でる“人間らしさ”という病」vol.5 TOOLの迷宮は、AIによってどう“別の感情”に編み替えられるのか
12月、19年ぶりの来日公演を控えるTOOLは、1990年代以降のオルタナティブ/プログレッシブメタルを象徴する存在だ。ポリリズム、変拍子、長尺構成、抽象的で観念的な歌詞 ── 。ロックの肉体性と、数学的な構造美が奇妙に結びついた音楽で、世界中に熱狂的... -

[妄想コラム]パンク不在の世界線 ── もしも「反逆の3コード」が鳴らなかったら80年代以降の音楽史はどう変わっていたのか?
序章:パンクが存在しない世界という、最大級の“文化実験” 1976年、もしロンドンにもニューヨークにも、あの粗暴な3コードの反逆がまったく現れなかったとしたら、20世紀終盤のカルチャーはどうなっていただろうか。セックス・ピストルズの“アナーキー”は... -

[連載]JPOPと旅する:玉置浩二と旭川──北の大地が育んだ「心のメロディ」
はじめに 玉置浩二 ── その名を聞けば、日本の音楽界を代表する稀代のボーカリストを思い浮かべるだろう。ソロとして、あるいは安全地帯のフロントマンとして、彼が紡いできた楽曲は、多くのリスナーの心に深く刻まれてきた。だが、その豊かな表現力や独特... -

[響き合うコーヒーと音楽の世界]第23回:クリスタルマウンテン
こんにちは、リトル・パウです。今回、私が皆様をご案内するのは、カリブ海に浮かぶ情熱の島キューバから届いた、深いコクと甘みを持つ豆「クリスタルマウンテン」の世界です。 キューバ中央部、エスカンブライ山脈の限られた地域で栽培されるクリスタルマ... -

「AIが奏でる“人間らしさ”という病」vol.4 1つの名曲は、いくつの顔を持てるのか
AIが再構築した名曲たちを紹介するこのコラム。第4回目となる今回は、初の“単曲・異アレンジ”企画だ。 取り上げるのは、ニルヴァーナ「Smells Like Teen Spirit」。90年代のロック史を象徴するこの楽曲は、倦怠、苛立ち、衝動が綯い交ぜになった“当時の空...