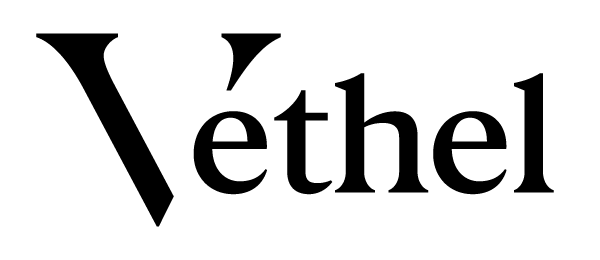「海に囲まれていること」は、日本の文化を考えるうえで避けて通れない条件である。四季の移ろい、外来文化の受容と変容、そしてなにより“外”と“内”の線引き。それは音楽シーンにも明確に影響を与えてきた。だが、ここで一つの妄想をしてみたい。もし日本が大陸と地続きの国であったなら、音楽はどのような変化を遂げていたのだろうか?
この妄想は決して単なる空想遊びにとどまらない。音楽とは、本質的に「どこから来たか」と「どう変わったか」の連続だからである。
境界の消えた列島──“通過点”としての日本
仮に、日本列島が朝鮮半島の先に“もう一枚の半島”として繋がっていたとしよう。つまり、北海道〜九州が中国大陸と直接繋がる“ユーラシア東端”の一部だったら。
この場合、日本は「極東の孤島」ではなく、「ユーラシアの東の玄関口」としての役割を持ったはずである。そうなると、文化も音楽も、“受け入れる”というより“通過させる”性質を強く帯びただろう。あるいは、モンゴルや中央アジア、ペルシア音楽の潮流が、遥か昔に日本の音楽と直に触れ合っていたかもしれない。
たとえば、喉歌(ホーミー)のような倍音唱法が、雅楽の源流として定着していたらどうだろう。日本語の声楽は、もっと倍音豊かで、詠唱的だったかもしれない。民謡「南部牛追い唄」や奄美島唄に見られる節回しの“揺らぎ”は、よりパンアジア的な土着性を帯びていただろう。
トランジット・ネイションのビート──ヒップホップの風景
現在の日本のヒップホップは、アメリカ由来のスタイルを日本語の感性で変換したものが主流である。だが、日本が大陸国家だったなら、アジア内の「交通の要衝」としてのストリート感覚が、もっと強く出ていたに違いない。
たとえば、韓国のストリートダンス、モンゴルのポリリズム、ロシアのビート詩。そういった周辺文化とより早期かつ密接に接触していたなら、日本のヒップホップはもっと民族的で、かつ雑種的な方向に開花していた可能性がある。
この曲が持つ都市感覚は、もし東京が“地続きの交通都市”だったら、もっとイスタンブール的に、さらなる混血感を纏っていたかもしれない。
エレクトロニカの民族化──沈黙とノイズのはざまに
日本は戦後、高度経済成長の余韻と共に、独自のエレクトロニカ文化を形成していった。YMOから始まり、Cornelius、坂本龍一、AOKI takamasa、Serphに至るまで、“技術の国”日本だからこその実験性があった。
だが、もし音楽的アイデンティティが島国的な「内向き」ではなく、常に「他民族との混交」によって形作られていたなら、日本の電子音楽は、もっとプリミティヴで土着的だった可能性がある。
たとえば、OOIOOの「KRS」「UMA」などに見られるポリリズムや声の反復は、原始音楽的な熱を持っている。こうした方向性がもっと主流化していたかもしれない。
また、ノイズ・ミュージックにおいても、非常階段やMerzbowのような「内破」ではなく、インド音楽やトルコのスーフィー音楽との交流によって、「瞑想と爆音のあいだ」を彷徨うような音が生まれていたのではないか。
メロディの民主化──J-POPの異なる進化系
J-POPは、内需とテレビ文化の上に築かれた“島国的ポップ”である。その最大の特徴は、コード感覚の洗練と、メロディの明瞭さである。だが、もし日本が地続きだったなら、「J-POP」という括り自体が生まれていなかった可能性すらある。
たとえば、アイドル文化はもっと国際的な芸能網の一部として機能し、K-POP的な練度やストイックさと融合していたかもしれない。Perfumeの「ポリリズム」は、バルト三国の音楽理論と出会って、変拍子の祭典になっていたかもしれないし、宇多田ヒカルの「First Love」は、より東欧的な叙情性を帯びていただろう。
つまり、J-POPは“外”が遠かったからこそ守れた調和を持っていたとも言えるのだ。
地続きのサイケデリア ── “トランス”の東方表現
また、日本が内陸国家だった場合、トランスやレイヴ文化も異なる姿をしていただろう。インドのゴア、イスラエルのサイケデリック、そしてネパールの霊性文化などとの物理的近接性により、より儀式的で霊性的なパーティ文化が主流になっていたかもしれない。
現在でも内省的なサイケ感を持つ日本の音は、より“トライバルな脱自我”に傾いていた可能性がある。
渋谷のクラブではなく、山岳地帯の祭礼や回教徒の踊り場のような場所が、トランスの主戦場になっていたら……。想像は尽きない。
「日本音楽」の不在──あるいはハイブリッド国家の矜持
このように想像を巡らせていくと、「日本らしさ」とは、実は“島であること”そのものに支えられていたことに気づく。
島であるからこそ、外の音楽と時間差で出会い、咀嚼する時間を持てた。
島であるからこそ、“自国らしさ”を温存できた。
そして島であるからこそ、音楽的にも精神的にも「独自の旋律」が生まれたのである。
もしこの“隔絶”がなければ、日本の音楽はあまりに早く「地球の音楽」と混ざり合い、個性を失っていたかもしれない。あるいは、もっと早く「アジアのハブ」としての自覚を持ち、新たなミクスチャー国家として発展していたかもしれない。
妄想の終わりに──私たちはなぜ「日本の音楽」を聴くのか?
この妄想は、現実の音楽に戻ってくるための旅でもある。
たとえば、民謡クルセイダーズ「竹田の子守唄」のように、ラテンのビートで民謡を蘇らせる手法は、まさに地続きの妄想の具現化である。あるいは、坂本慎太郎の「まともがわからない」に漂う、戦後以後の音楽的自画像。
島国の中で、私たちはつねに「外」と「内」の関係を問いながら、音を鳴らしてきた。もしこの国が大陸の一部だったなら、それはもっと無遠慮に混ざり合い、溶けていたかもしれない。
だが、そうでなかったからこそ、「音楽的な日本」が存在する。
島であることは、決して閉鎖ではない。それは、独自のリズムで、世界と会話するという選択なのだ。
※本コラムは筆者の妄想です。

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。