
VETHELの特集企画「音楽と〇〇」は、音楽と寄り添うさまざまなサブカルチャーとの交わりを探るインタビューシリーズ。〇〇はアートやゲーム、漫画、映画、ガジェット、建築、グルメ、旅行、乗り物、スポーツ、アウトドア……など何でもあり。音楽とその界隈の関係を語っていただきます。今回のゲストは?
DJとVJ、ジャケットデザインやライブ空間の演出。音楽とアートは常に境界を越え、互いに刺激を与えながら新しい表現の可能性を広げてきた。ギャラリー空間の残響を生かしたライブや、展覧会に合わせた楽曲制作など、現場では両者の融合が自然に生まれている。一方で、市場規模や仕組みは大きく異なる。億単位の投資が動く音楽産業に比べ、アートは自由度が高いが作家の自発性に委ねられる側面が強い。タグボート代表の徳光健治さんは、その違いを見据えつつも「アートは露出の絶対量が価値を高める」と語る。音楽とアートが交錯してきたカルチャーの歴史を振り返りながら、今後どんな「突き抜ける瞬間」が生まれるのか。本インタビューでは、両者を往還する刺激的な視点が明かされた。

著書「教養としてのアート、投資としてのアート」、「現代アート投資の教科書」。 地上波テレビの出演多数。Newspicksのトピックスオーナー。
芸術新潮のコラム「アートとお金のはなし」を毎月連載。青山学院大学 非常勤講師
音楽はトレンドに影響されるが、現代アートは長く親しまれることが重視される
VETHEL 徳光さんにとって音楽とアートはどのように結びついているのでしょうか。
徳光 同じエンターテイメント市場の中で、お互いが影響し合ったり、コラボレーションが進んでいく関係にあると思います。分かりやすいのはDJとVJのような組み合わせですね。ギャラリーでもレセプションの場でシンガーソングライターが弾き語りをしたり、サウンドアート的な試みを行ったりしています。例えば、作品展示の前でクリスタルボウルという水晶で作られた楽器を奏でたり、ギャラリー空間の残響を生かしてギターの弾き語りをすることもある。タグボートは天井高が約5メートルあり、非常にリバーブが効くんです。いわば「お風呂場のような残響」が得られるので、音楽とアートが自然に融合する場になっていると感じます。また、ジャケットデザインは昔からアートと音楽をつなぐ定番の領域ですよね。横尾忠則さんなどは有名ですし、私たちのところでもアーティストがCDジャケットを手がけたことがありました。最近ではイラストレーターのMika Pikazoさんが展覧会に合わせて楽曲制作を依頼し、会場で流し続けた例もありました。作品世界に音楽が溶け込む新しい形だと思います。
VETHEL ギャラリー空間における「音」の重要性について、どうお考えですか? BGMや無音も含めて。
徳光 これからは無音で静かに鑑賞するよりも、音とのコラボは必要だと思います。作家が作品に合う音楽を選んだり。
VETHEL 普段の生活や仕事の中で、音楽はどんな役割を果たしていますか?
徳光 社内で聞くBGMとしての音楽が多いですね。聞くと仕事がはかどりますし、たまにライブを見に行くこともあります。
VETHEL 音楽とアートのマーケットについては、似ているようで異なる点もあると思います。どのようにご覧になっていますか?
徳光 音楽は視聴がデジタルであってもライブであっても大衆がマーケットですが、アートは鑑賞以外に購入まで含めるとある程度の富裕層が市場ターゲットとなります。どちらもプレイヤーの才能やパフォーマンスが重要ですが。音楽はそのときの流行やトレンドに影響されることが大きいですが、現代アートは流行に左右されず、長く親しまれることが重視されます。一瞬人気を集めても、トレンドだけの作品は長続きしません。日本の現代アート市場規模は約800億円。一方、音楽は3,000億円超と桁が違うんですね。なぜなら音楽の世界は、プロダクションやレコード会社といった組織が役割を分担し、1人のアーティストに数千万円単位で投資する仕組みが整っています。音楽は一人にかけるお金も時間も桁違いに大きい。一方、アートの場合は展覧会の前に打ち合わせをする程度で、二人三脚のようなプロデュースは少ない。委託販売で出たものを扱うのが基本です。だから自由度が高い反面、作家の自発性に委ねられる部分が大きい。そこは大きな違いですね。
VETHEL 音楽業界の「サブスク化」や「デジタル化」はアート界にどう影響を与えていると思いますか?
徳光 アート作品をキャンバスに油画で描くよりも、iPad上でデジタルで描く作家が増えてます。題材を探す際にAIを活用する作家も増えてますし、これまでアナログだったアート界が早い勢いでデジタル化が進んでいますね。一方、サブスクはアートではレンタルを意味しますが、これは趣味嗜好が強い商品なので進んでいないし、今後も拡大しないと思っています。
アートは“感情の総和”によって売れ始める
VETHEL アーティストやミュージシャンには共通する「突き抜ける瞬間」があると思いますか?
徳光 個人の世界観をどこまで世の中のファンに共感してもらえるかといった点が重要ですので、そうできる「才能」を見つけ出し、世の中に知ってもらう活動をすることは同じだと思います。アートは音楽ほどSNSで一気にバズるスピードは早くありませんが、廃るのも遅くて、じわじわと火が付きます。アートは音楽のように若いトレンドセッターやインフルエンサーによって突き抜けるものではなく、多くの人に作品を見てもらったときの感情の総和によって売れ始める感じですね。
VETHEL 多くの人に作品を見てもらったときの感情の総和とは?
徳光 よく話すのは「アートの価値は見せれば見せるほど上がる」ということです。評論や受賞歴も重要ですが、まずは作品をどれだけ多くの人に見せられるか。銀座三越の催事会場を借りて数万人を集めたり、1,500平米の会場で大規模展示を行ったりするのはそのためなんです。インターネット時代の今はSNSや口コミによって作品の評価が広がります。例えて言うと一人が100万円の絵を買うより、100人が1万円ずつ買ってくれる方が、市場全体の広がりにとっては重要なんです。もちろん、著名人が購入することで一気に作品価格を押し上げるケースもありますが、それは例外中の例外。基本は「露出の絶対量」が大事です。
若い世代ではアートと音楽を地続きに捉える感覚が強い
VETHEL 音楽に影響を受けたアーティスト、あるいはアートに影響を受けたミュージシャンにはどんな例がありますか?
徳光 奈良美智さんは有名なパンク好きですよね。学生時代にバンドを組んでいたり、ルースターズにイラストを提供したりしています。パンクはファッションとアートと音楽の三つが本格的に重なった最初のカルチャーだと思います。パンクは今年でちょうど50周年(セックス・ピストルズがデビューした1975年を元年として)。英国病といわれた時代の労働者階級から生まれた強烈なサブカルチャーでした。私自身が見てきた中では、例えば小畑多丘さんの彫刻はB-BOYで、ブレイクダンスとヒップホップに親和性がある。塩見真由さんはパンクバンドに傾倒していた影響もあり、自作に鋲を打った革ジャンのモチーフを取り入れたりしています。こうした例は多くはないですが、確かに存在します。
VETHEL 音楽からアートへの影響、あるいはその逆について、個人的な体験はありますか?
徳光 音楽を聴いて作品を買うといった経験はあまりありません。ただ、最近では音楽とアニメーションを同時に作るようなプロジェクトもあり、若い世代ではアートと音楽を地続きに捉える感覚が強いと思います。アニメーションに基づいて曲をつくる事例などは、従来の順序を逆転させた発想で、とても興味深いですね。
今までになかったものを生み出せるかどうか
VETHEL 音楽をテーマにした展覧会やプロジェクトで、印象的だったものはありますか?
徳光 東京都現代美術館の“坂本龍一 「音を視る 時を聴く」”には残念ながら行けなかったのです。サウンドアートをしているアーティストはいますが、数は少ないですね。今後は展覧会で、音楽が奏でられることは増えてくると思います。
VETHEL 最後に、仕事中によく聴かれている音楽について教えてください。アートの選定やキュレーションにも影響しますか?
徳光 社内ではジャズ、ボサノバ、フュージョン、最近のJPOPから70~90年代の洋楽まで幅広く聞いています。私は音楽とアートの選定は「別次元のもの」と捉えています。音楽は車内や作業中にふわっと聴けますが、アートは集中して鑑賞する必要がある。作品選定の際には、作品もちろんですが、「作家のキャラクター」も重視します。作家自身の頭の良さや社会に対する視点、オタク的な偏愛など、強い個性を持った作家を探します。100人に会っても、売れる可能性のあるのは5〜7人ほど。音楽でも同じくらい厳しいと思います。アートは上手い下手では評価されず、唯一の尺度が「発明かどうか」。つまり今までになかったものを生み出せるかどうか。これは音楽にも通じる視点でしょうね。
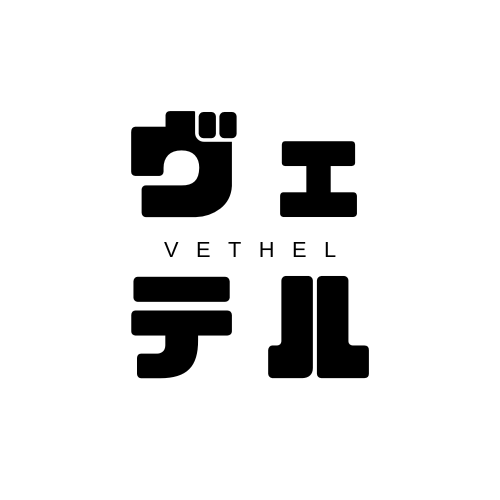
Interview & Text : VETHEL









