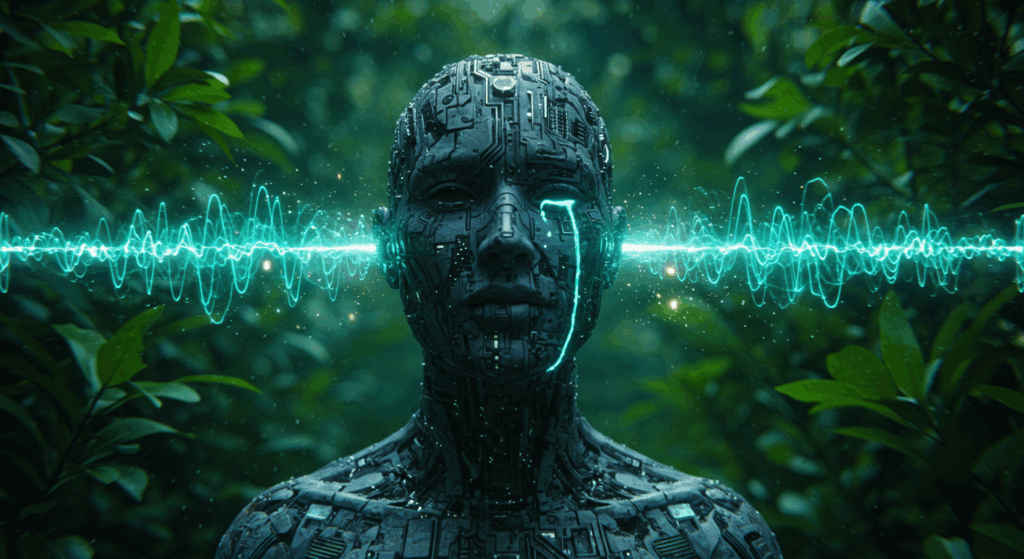
それでも人は、囀る──音楽なき世界に響く声のゆくえ
想像してみてほしい。「音楽」という概念そのものが、最初からこの世界になかったとしたらどうなるだろうか? 楽器もなければ、歌もない。旋律という発想も、リズムという感覚も、この地上には一切存在しない。そんな世界に生まれ落ちた人類は、果たして何を聴き、何を囀る(さえづる)のだろうか。
人類の歴史は、音楽と共に歩んできた。太鼓のリズムに合わせて踊った狩人たち、祈りの歌に願いを込めたシャーマンたち。音楽はただの娯楽ではなく、言葉にできない感情を伝える装置であり、共同体をつなぐ不可視の糸であった。だが、その音楽がそもそも存在しなかったなら? 本稿ではその極端な仮定のもと、人間と音の関係性を改めて見つめ直してみたい。
音のない世界ではなく、音楽のない世界
まず確認すべきは、「音楽がない」=「音がない」ではないということだ。風が木々を揺らす音、雨が屋根を叩く音、遠雷が地平線の向こうで轟く音 ── これらはすべて存在する。自然は今も昔も変わらず、豊かで複雑な音を奏でている。だが、人類はその音を音楽として認識する術を持たない。
つまり、彼らにとって音とは、意味を持たない現象にすぎない。風の音は「風が吹いている」という事実を知らせる信号であり、焚き火のはぜる音は「火が安定して燃えている」という安心材料だ。音はあくまで情報であり、そこに美しさや感情を見出すことはない。海の波音を聞いて癒されることもなければ、小川のせせらぎに心を重ねることもないのだ。
この世界では、音を「聴く」という行為に情緒は存在しない。耳はセンサーにすぎず、脳はそれを機械的に処理する。美や情緒を求めるなら、それは視覚か、触覚か、あるいは嗅覚の領域でまかなわれることになる。
情動なき声、人は何を伝えるのか?
声はある。言葉もある。人類はコミュニケーションの手段として言語を発展させてきた。だが、この世界において、声に抑揚をつけたり、音色に気持ちを込めたりする文化は存在しない。
例えば、喜びを伝えるために声が高くなる ── そんな自然な感情表現も、規範化されることはない。感情は視線や手振り、身体の向きなど、より目に見える信号で伝えられる。怒りは拳を握ることで示し、哀しみは目を伏せることで共有される。
この世界の詩人は、言葉の意味にのみこだわる。比喩や象徴を巧みに操ることはあっても、声にメロディをのせることはない。ラップも民謡も存在しない。子守唄も、応援歌もない。
母親が赤ん坊をあやすときも、そこに歌はない。ただ淡々と「大丈夫だよ」と語りかけるのみである。赤ん坊が発する泣き声や笑い声に「リズム」や「旋律」を見出すこともない。すべては、意味を持つ音として処理され、感情の記憶として蓄積されることはないのだ。

そして、最初の歌が生まれるとき
だが、果たして人類はそれで満足するだろうか? 答えは否である。なぜなら、人は常に「意味以上のもの」を求めてきた生き物だからだ。
ある日、ひとりの少年が、遠くの山に向かって叫んだとしよう。声は山にぶつかり、反響する。その声を聞いたとき、少年の胸には得体の知れない感動が走る。それは「意味」を超えた何か ── 音が空間に染み渡っていくような体験。
あるいは、焚き火のそばで、ふと鼻歌のような声を発した少女がいたとしよう。意味もなく、ことばにもならない声。だが、その声を聞いた仲間の一人が微笑んだ。その瞬間、そこに「音楽」の萌芽が生まれる。
つまり、音楽は人間の本能であり、文化以前の衝動なのだ。感情を音に変換しようとする欲望は、言葉よりも先に存在していたかもしれない。もし音楽が「存在しなかった」としても、人はやがて音楽を「発明する」。なぜなら、それは人間の魂が、自らの輪郭を知るために必要な手段だからである。
やがて、音を並べることに快感を覚える者が現れる。木を叩く音の間に、石を叩く音を差し込んでみる。意味のない声を繰り返してみる。そこには理由などない。ただ、心が震えるからやる。やってしまう。
最初の歌は、たぶん、誰にも聞かれなかった。ただの独り言、ただの遊びだったかもしれない。だが、その「意味のない声」に、初めて誰かが涙を流したとき ── それが音楽の誕生の瞬間なのだ。
音楽は「なくなる」ものではない
この世界がどれほど理性的で、効率的で、意味に満ちたものであったとしても、人はやがて意味を超えたものに手を伸ばす。それは絵画であり、香りであり、そして音楽である。
音楽なき世界を想像することは、逆説的に、音楽が私たちにとってどれほど根源的なものであるかを知ることでもある。それは社会の装飾ではない。文化の副産物でもない。音楽とは、人間が「自分が生きている」ということを実感するための、もっともシンプルな証なのだ。
そして今、世界には77億の囀りがある。そのひとつひとつが、音楽が生まれた奇跡を物語っている。
音楽がなかったら? ── いや、必ず生まれる。なぜなら、人は囀るからだ。

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。








