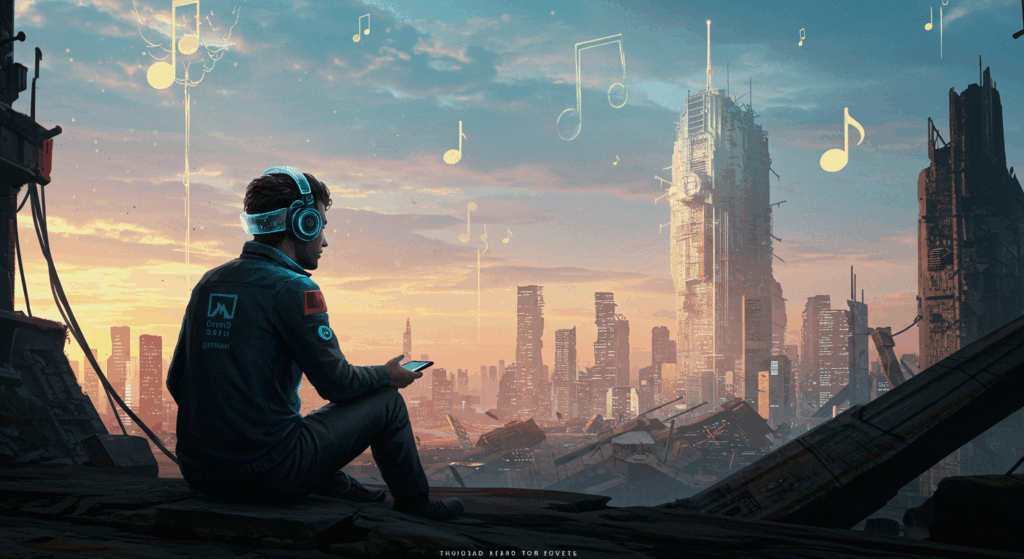
音楽の“寿命”を問うということ
私たちが日々聴いている音楽 ── それは果たして、どれほど長く生きられるものなのだろうか。流行歌の多くは数か月で忘れ去られ、名作と呼ばれる楽曲ですら、せいぜい百年かそこらの命である。それでも、1000年というスパンで未来を思い描くとき、不思議と心に浮かんでくる音楽がある。音としての美しさだけでなく、何か別の「芯」を持った作品たち ── その共通項は何なのか。
1000年後に残る音楽、それは単に「生き残った」ものではない。むしろ、「残さざるをえなかった」ものだ。では、それはいったいどんな音楽なのか。未来の耳を想像しながら、その正体を探ってみよう。
リズムは心臓に近い ── 原初的な音楽の未来
音楽の根源は「音」ではなく、「時間」にある。たとえば、母の胎内で初めて聴くのは、言葉でも旋律でもなく、規則的な鼓動だ。つまりリズムこそ、音楽における最も古くて深い言語である。
この視点から未来を想像すると、旋律や和声に依存しない音楽が案外しぶとく生き残っているかもしれない。複雑な文化や記譜法に頼らずとも、身体ひとつで感じられるビート。それはアフリカの太鼓や日本の神楽、ミニマルテクノにも通じる普遍性を帯びている。
言語も文化も変わり果てた未来において、「身体の音楽」は人類共通の遺産として機能するだろう。それは単なる娯楽ではなく、生存のリズムであり、祈りのコードである。
音楽とテクノロジーの不可分な運命
1000年後の世界には、我々が今想像もできないテクノロジーが存在している可能性が高い。脳波で操作する音楽、感情と連動する生成音、宇宙空間で再生される無重力のサウンドスケープ。こうした「変化する音楽」こそ、未来の標準になるかもしれない。
ブライアン・イーノが始めたアンビエント・ミュージックや、現在のAI生成音楽はその前兆だ。もはや音楽は「聴くもの」ではなく、「環境と交わるもの」「生きるプロセスそのもの」となっていく。
おそらく千年後には、人類と人工知能の区別すら曖昧になる。だからこそ、共に創る音楽 ──「ヒューマン × AI」のハイブリッドな音世界が生まれ、遺されていくはずだ。
音楽は記憶の装置である
人類は音楽に「記録されない記憶」を預けてきた。文字で書き表せない感情、民族の歴史、戦争の悲しみ、愛のかけら ── たとえば、ユダヤのクレズマーや、アフリカ系アメリカ人のゴスペル、アイヌのウポポなど、数百年にわたり伝承された音楽には、その民族の魂が詰まっている。
こうした「語り継ぐための音楽」は、単なる芸術作品を超えている。それは「存在の証明」であり、「忘れられないための戦い」でもある。
1000年後にも、きっと人々は音楽によって過去を知ろうとするだろう。どんなに記録媒体が進化しても、心に響く語りは、音でしかできない。音楽は、未来に語りかけるための声だ。

音楽が音である必要がなくなるとき
そして最後に、もっとも逆説的な未来を考えてみたい。── もし、1000年後の人類が、すでに音楽を「聴く」必要がなくなっていたら?
それは恐ろしい未来ではなく、むしろ音楽が感情や思考として脳に直接送信される世界かもしれない。振動としての音すら不要になり、音楽は「概念」として直接インストールされる。だがそのとき、「あえて音にする」という行為が、逆に深い意味を持ち始めるだろう。
音楽は再び、宗教的儀式のように、特別な空間と時間の中でのみ鳴らされるものになるかもしれない。ノイズも、沈黙も、機械のハム音ですら ──「音楽」として扱われるようになる。
もはやそれは、音楽というよりも、「人間性の証明」だ。
音楽は、人間が人間であるための回路
結局のところ、音楽とは何なのか。誰かと共鳴したいという欲望、過去を覚えていたいという衝動、自分という存在を宇宙に刻みつけたいという願い。どれも、あまりにも人間的で、あまりにも切実な欲求だ。
だからこそ、1000年後にも音楽は存在しているだろう。ただしそれは、今とまったく同じ形ではない。しかし、「なぜ人は音を鳴らすのか」という問いだけは、何も変わらず響き続けているに違いない。
未来の音楽を決めるのは、今を生きる私たちである。
そして私たちがどんな音を残すかによって、1000年後の誰かの心が震えるかもしれない。
そう思えば、いま耳を傾けるこの一曲にも、ほんの少し永遠が宿っているのではないだろうか。

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。








