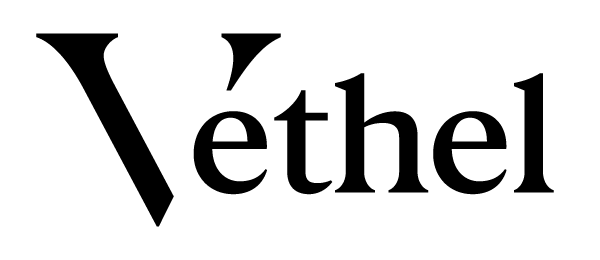「それ、音楽じゃないよね」
ノイズミュージックについて語られるとき、ほぼ必ずこの言葉が顔を出す。音程がない、メロディがない、リズムがない。耳障りで、うるさく、理解不能。だからそれは音楽ではなく「ただのノイズ」なのだ、と。
だが、ここで一度立ち止まりたい。そもそも「音楽」と「ノイズ」の境界線は、誰が、いつ、どこで引いたのだろうか。
この問いは、単なる前衛音楽擁護ではない。音楽史そのものを、少しだけ裏側から眺め直すための入口である。
ノイズとは「音」ではなく「判断」である
まず確認しておきたいのは、「ノイズ」とは物理現象ではなく、文化的判断であるという事実だ。
工学的には、ノイズとは「不要な信号」を指す。つまり、必要か不要かを決める主体が存在して初めてノイズになる。裏を返せば、誰かにとって不要な音は、別の誰かにとって必要な音になり得る。
音楽史は、この「不要」とされた音が、何度も何度も復権してきた歴史でもある。
クラシック音楽も、かつては「騒音」だった
今でこそ「高尚」とされるクラシック音楽も、誕生当初は必ずしも歓迎されていなかった。
例えば、ストラヴィンスキーの《春の祭典》(1913年初演)。原始的なリズム、不協和音の連打、暴力的とも言えるオーケストレーション。初演時、観客は激怒し、客席は騒然となった。これは音楽史に残る有名な「暴動」である。
当時の聴衆にとって、それは理解不能なノイズだったのだ。
だが現在、《春の祭典》は20世紀音楽の金字塔とされている。ノイズは、時間と文脈が変わることで、いつの間にか「音楽」になる。
ノイズを音楽として肯定した最初の思想
ノイズを真正面から肯定した最初期の人物として、イタリア未来派のルイジ・ルッソロを外すことはできない。
1913年、彼は「騒音芸術宣言」を発表する。都市の機械音、工場の轟音、爆発音──それらこそが現代の音楽素材であると宣言したのだ。
ルッソロは《目覚め》《衝突》《叫び》などのノイズを出す自作楽器「イントナルモーリ」を用いて演奏を行った。当時の人々の多くは、それを音楽と認めなかった。
しかし、ここで重要なのは、ノイズが初めて「意図的に演奏された音楽」になった瞬間であるという点だ。
ジョン・ケージと「音楽の死」
ノイズを語るうえで、避けて通れないのがジョン・ケージである。
彼の代表作《4分33秒》。演奏者は何も演奏しない。だが、その間に会場に響く咳、椅子の軋み、空調音、外の車の音──それらすべてが「音楽」として提示される。
ケージが行ったのは、ノイズを音楽に変えたのではない。音楽という枠組みを解体し、世界をそのまま聴かせたのである。
この瞬間、「音楽とは何か?」という問いは、作曲家や演奏者の手を離れ、聴き手の側へと投げ返された。
ノイズミュージックという実践
1970年代以降、「ノイズ」は思想ではなく、ジャンルとして定着していく。
例えば、日本のノイズシーン。Merzbowは、歪み切った電子音の洪水を作品として提示し続けてきた。代表作『Pulse Demon』は、メロディもリズムも拒絶するかのような音塊である。
海外では、スロッビング・グリッスルがインダストリアル・ミュージックを確立し、工業音や不快音を積極的に取り入れた。
彼らの「Hamburger Lady」は、音楽と恐怖の境界を曖昧にする楽曲である。
これらは「聴いて気持ちいい音楽」ではない。だが、意図、構造、文脈を持った表現であることは疑いようがない。
ノイズは「反音楽」ではない
よくある誤解は、ノイズミュージックが音楽への反抗、あるいは否定だという考え方だ。
実際には逆である。ノイズは、音楽を誰よりも真剣に考えた結果として生まれている。
・なぜこの音は許され、あの音は排除されるのか
・誰が「美しい」と決めているのか
・聴くとは、どういう行為なのか
ノイズは、これらの問いを突きつけるための装置なのだ。
テクノ、アンビエント、そしてノイズの浸透
興味深いのは、ノイズが決して前衛の中だけに留まらなかった点である。
初期テクノのミニマリズム、アンビエントの環境音志向、ドローンミュージックの持続音。ブライアン・イーノの『Music for Airports』は、ノイズと音楽の中間領域にある作品と言える。
また、マイ・ブラッディ・ヴァレンタインの轟音ギター、エイフェックス・ツインの歪んだテクスチャも、かつてなら「ノイズ」と切り捨てられていた音である。
ノイズは、知らぬ間にポピュラー音楽の内部へと浸透していった。
それでも「ノイズは音楽ではない」と言う人へ
ここまで来ても、なお「ノイズは音楽ではない」と感じる人はいるだろう。それは自然な感覚である。
だが、重要なのはこうだ。
「ノイズを音楽だと思えない」という感覚自体が、文化的に形成されたものだという事実である。
音楽とは、自然現象ではない。社会が、技術が、歴史が、そう呼ぶことにした概念なのだ。
ノイズが教えてくれること
ノイズミュージックは、万人に開かれた娯楽ではない。しかし、音楽というものの輪郭を最も鮮明に浮かび上がらせる存在でもある。
「これは音楽ではない」
そう言った瞬間、私たちは無意識のうちに、自分自身の音楽観を告白している。
ノイズはうるさい。
ノイズは不快だ。
ノイズは理解しづらい。
だからこそ、ノイズは問い続ける。
音楽とは何か?
それを決めているのは、本当に“音”なのか?
※本コラムは著者の妄想です

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。