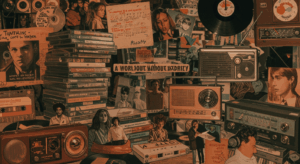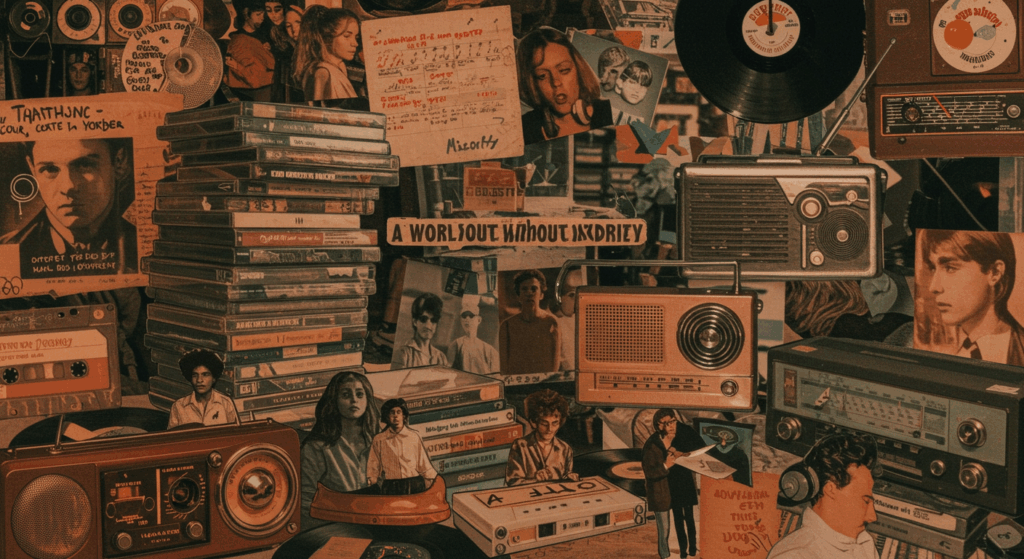
音楽の聴き方は、ここ20年で劇的に変化した。とりわけSpotifyが2008年にスウェーデンで誕生して以降、その影響は音楽業界だけでなく、リスナーの耳、身体感覚、さらにはアーティストの創作プロセスにまで及んでいる。では、もしSpotifyという存在がこの世になかったら、音楽の風景はどうなっていたのだろうか?
これは単なる「アプリの話」ではない。Spotifyは、音楽の価値観を大きく変えてしまったプラットフォームである。
プレイリスト文化の不在
Spotify以前、音楽を聴く行為は「アルバム」や「シングル」といったパッケージ単位に強く結びついていた。それぞれの楽曲はコンセプトの中で並び、物語を紡ぎ、時間軸を持って存在していた。ところが、Spotifyの台頭とともに、音楽は「プレイリスト」という新しい単位で消費されるようになる。
もしSpotifyが存在していなかったなら、「チル」「作業用」「ドライブ」「失恋」といった気分ベースの音楽のカテゴライズ文化は、ここまで浸透しなかったかもしれない。人はもっと能動的にアルバムを選び、特定のアーティストの声や世界観と深く向き合っていた可能性が高い。
アルゴリズムと出会わない世界
Spotify最大の特徴のひとつは、パーソナライズされたレコメンド機能にある。ユーザーの聴取履歴やスキップ傾向を分析し、「あなたの好みに合うかもしれない」音楽を提示する。こうしたアルゴリズムがなければ、音楽との出会い方はもっと偶然と人間関係に左右されるものだったろう。
たとえば、友人が貸してくれたCD、街のレコード屋の棚、FMラジオの深夜番組 ── Spotifyがない世界では、音楽との邂逅はもっと“物理的”で“限定的”だったに違いない。そしてそのぶん、出会ったときの感動や所有感も、もっと強烈だったかもしれない。
再生時間最適化型ソングは生まれなかった?
Spotifyが定着させたもうひとつの大きな影響は、「楽曲の最適化」である。つまり、冒頭15秒でリスナーを掴まなければスキップされる世界。その結果、ポップスはより短く、より即効的なサビ構成になっていった。
Spotifyがなければ、イントロでじっくり空気を作る曲や、5分を超える大作も、今より広く受け入れられていたかもしれない。そう考えると、現在のポップスの「最短で最大限に伝える」設計思想は、Spotifyの存在と無縁ではない。
アーティストの戦略も変わっていた
アーティストたちもSpotify以後、音楽の「出し方」を変えてきた。アルバムよりもシングル中心。曲間に無音があるとスキップされる。アートワークはサムネイルサイズを想定。あらゆる部分が“ストリーミング時代”を前提に再設計されてきた。
もしSpotifyが存在していなければ、もっと多くのアーティストがアルバム単位の物語構築を志向し、作品ごとにビジュアルやリリース形態にも個性を持たせていたかもしれない。逆に言えば、現在の音楽制作には「最適化による均質化」の危険も孕んでいる。

世界の音楽は“ここまで”繋がらなかった
一方で、Spotifyの恩恵もある。ナイジェリアのAfrobeats、韓国のK-POP、インドネシアのBedroom Pop ── こうした「ローカル音楽」が国境を越えて世界中の耳に届くスピードは、Spotifyによって劇的に加速した。
Spotifyがなければ、これらの音楽は今も“知る人ぞ知る”存在にとどまっていた可能性が高い。つまり、音楽の“民主化”や“グローバル化”という側面は、Spotifyが牽引したとも言える。
結論:「なかったら」ではなく「今、どう使うか」
Spotifyが存在しなかった世界では、音楽はもっと手間がかかり、偶然が重要で、深く濃密な出会いに満ちていただろう。だがそれは同時に、アクセスの格差や、情報の偏りも強かったということでもある。
重要なのは、「Spotifyがある」現代において、どうすれば音楽ともっと豊かに出会えるかを問い直すことだろう。アルゴリズムの外に出て、誰かのおすすめに耳を傾け、たまには1枚のアルバムを最初から最後まで通して聴いてみる──。
Spotifyがある世界で、Spotifyだけに頼らない音楽の楽しみ方を、今こそ再発明する必要がある。

Shin Kagawa:100年後の音楽シーンを勝手気ままに妄想し続ける妄想系音楽ライター。AI作曲家の内省ポップや、火星発メロウ・ジャングルなど架空ジャンルに情熱を燃やす。現実逃避と未来妄想の境界で踊る日々。好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。