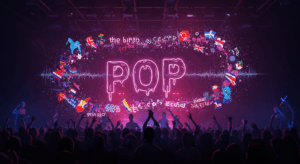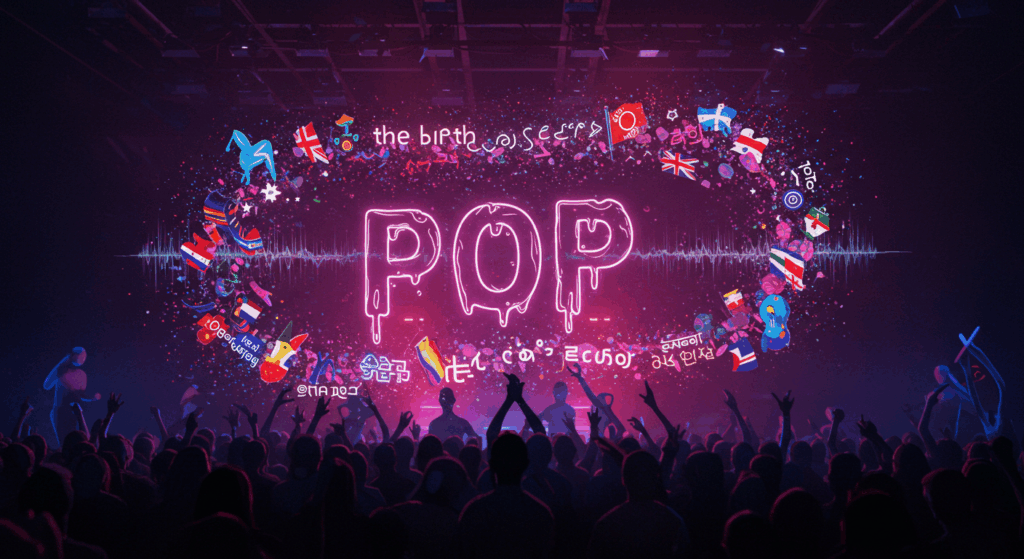
音楽の進化は、いつだって「POP」の名を借りた文化の衝突と融合から始まってきた。J-POPが感情の細部を詩情豊かに描写し、K-POPがビジュアルとパフォーマンスを武器にグローバルを席巻した今、次に来るのはどんな「POP」なのだろうか。世界中の耳が飽和しはじめたこの2020年代半ば、ぼくらが期待すべき「NEXT POP」の可能性について考えてみたい。
「POP」は国名ではなく、態度である
まず前提として確認しておきたいのは、「J-POP」「K-POP」といった言葉は、単なる「国名+ポップス」ではないということだ。それぞれの「POP」には、その土地の言語感覚、社会のリズム、文化の美意識が色濃く染み込んでいる。
J-POPは、J-ROCKやシティポップ、アニソンを含む日本独自の感性を育ててきた。孤独や内面を掘り下げ、抒情を大切にする歌詞文化。メロディ優位で、コード進行は凝っていても、どこか曖昧さを許容する。その「ゆらぎ」こそが魅力だった。
一方、K-POPは、アイドルという概念を極限まで進化させた集合芸術である。厳密なトレーニングと徹底したコンセプト管理。英語・韓国語・日本語をまたぐ多言語戦略。SNSとの高い親和性。そして“ビジュアル”の徹底的な演出力。このように、「◯◯POP」とは単なる音楽ジャンルではなく、その国が選び取った「音楽をどう定義するか」という総体なのだ。

世界が次に求めるのは、どんなPOPか?
ここで、今の世界の空気を感じてみよう。SNSでは毎日何千もの楽曲が流れ、Spotifyのアルゴリズムは過去の名曲と最新のトレンドを並列に並べる。AIボーカルが自然に歌い、MVはほぼ3DCG。ライブはメタバースで行われ、リスナーの心拍数に応じてリアルタイムに曲が変化する。
音楽は便利になった。でも、どこか「体温」を失いはじめていないか? だからこそ、次に来るPOPは、むしろその真逆 ── 「遅さ」「不器用さ」「身体性」に根ざしたものかもしれない。
候補①:「Slow Pop」── 加速社会へのアンチテーゼ
すべてが速すぎる時代、耳に優しく、心に滲む音楽が注目されている。テンポはミディアム〜スロー。歌詞は短く、感情のスケッチのように断片的。ギター1本や、ドラムマシンとボーカルだけのミニマル編成。タイのBedroom Pop、インドネシアのCity Chill、日本のZ世代が生む「ひとり語り」のような音楽たち。これらの「Slow Pop」は、SNSに即時性ではなく“余白”を持ち込む。音楽が“情報”から“関係”に戻る。そんな予感を感じさせる。

候補②:「Roots Pop」── 辺境が世界の中心になる
世界の耳が、グローバルスタンダードなポップに飽きてきた今、南米やアフリカ、中央アジアなどの「辺境」に注目が集まっている。たとえば、ナイジェリア発のアフロビーツやサウス・アフリカン・ハウスはすでに国境を超え、ドレイクやビヨンセまでもが取り入れている。ケニアのゲンゲやブラジルのバイレ・ファンク、モンゴルの喉歌とEDMの融合などもある。こうした「Roots Pop」は、ローカルなリズムや言語をグローバルに流通させる知恵を持ちつつある。むしろ、かつてのJやKと同じように、「自分たちの場所から世界に声を届けたい」という、切実な欲望こそがそのエネルギー源なのだ。
候補③:「Post Pop」──ジャンルなきジャンルの時代へ
そして最後に、もっともラディカルな可能性としての「Post Pop」がある。それは、既存のジャンル分類をすべて解体し、自分のルールで音楽を再構築するムーブメント。SoundCloudやBandcamp、YouTubeで静かに支持を集めるアーティストたちは、もはや“型”にとらわれない。トラップに民族楽器を重ね、突然ノイズを挿入し、クラシックの引用をラップにぶつける。
「POPであること」にすらこだわらない。むしろ、分類不能であることがアイデンティティになっている。この「Post Pop」こそ、今後の最前線をつくる音楽になるかもしれない。

結論:「次のPOP」は、世界をより複雑にする
「POP」はもはや国家単位の話ではない。それは、個人がどんな世界を信じ、どんな音を鳴らしたいかの「態度」そのものである。次のPOPはきっと、国境の外ではなく、個人の内側にある。そしてそれは、「誰でも作れるけれど、誰にも真似できない音楽」として、この先の時代を照らしていくのだろう。次に来る「POP」は、たぶんあなたのすぐそばで、もう鳴りはじめている。
※本コラムは筆者の妄想です。

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。