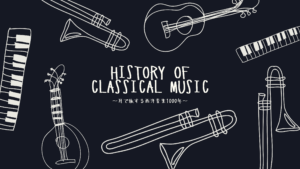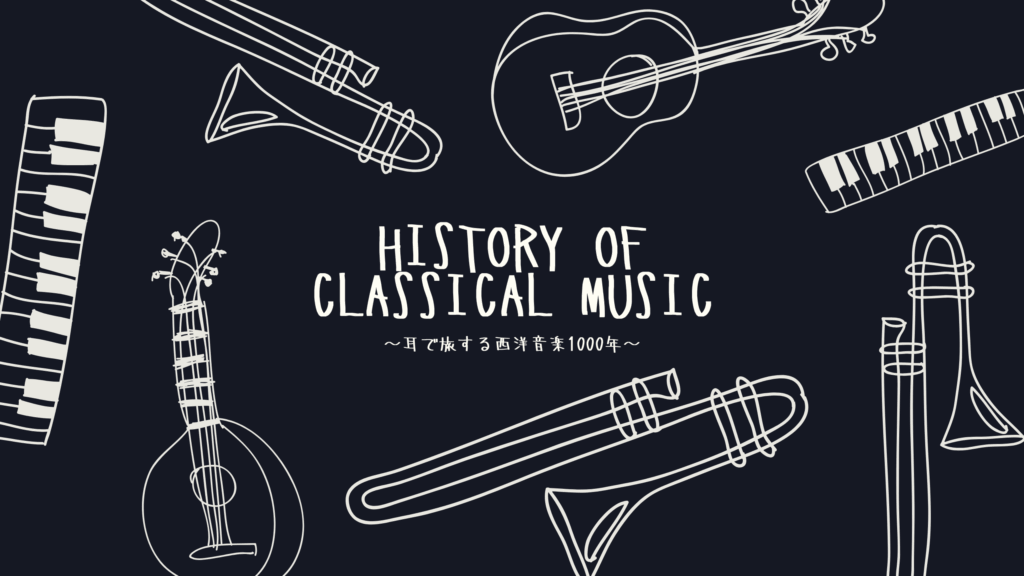
音楽は、どこから来て、どこへ向かうのか。
「クラシック音楽」と聞くと、あなたはどんなイメージを抱くだろうか? 堅苦しい、難しそう、あるいは昔の音楽 ── 。けれど、それはほんの一部に過ぎない。クラシック音楽とは、9世紀の祈りの声から始まり、劇場、宮廷、戦場、そして映画館やスマートフォンの中へと受け継がれてきた、“人間の感情と思想のアーカイブ”である。そこには、ただ美しいだけではない、問いや葛藤、時代のうねりと個人の叫びが、確かに息づいている。
この全8回の連載では、中世から21世紀まで、クラシック音楽の歴史を大きく8つのフェーズに分けてたどる。バッハも、ベートーヴェンも、ジョン・ケージも、決して遠い存在ではない。彼らの音楽は、時代を超えて今も私たちの耳に届いている。音楽は、いつも変わり続ける。だからこそ、過去を知ることは、未来の音をもっと自由に聴くためのヒントになるはずだ。クラシック音楽の1000年を、あなたの耳で旅してみよう。
クラシックとは「時代区分」ではなく「記憶装置」である
「クラシック」という語は、ラテン語の“classicus(最上級の市民)”に由来し、のちに「模範的な」「最高峰の」といった意味合いで使われるようになった。音楽における「クラシック」は、「ある特定の時代の音楽」ではなく、「長い時間を経ても聴き継がれてきた音楽」と定義するほうが正確である。
実際、クラシック音楽は非常に幅広い時代とスタイルを内包している。以下はその主な時代区分である。
中世(9世紀~14世紀):グレゴリオ聖歌など、宗教音楽が中心
ルネサンス(15世紀~16世紀):多声音楽の発展
バロック(1600~1750年):バッハ、ヴィヴァルディなど、形式と装飾の時代
古典派(1750~1820年):モーツァルト、ハイドン、初期のベートーヴェン
ロマン派(19世紀):感情の爆発、国民楽派の台頭
近現代(20世紀~):調性の解体、実験と自由
こうした時代ごとの特徴を知ることは、音楽の構造や社会との関係を理解する鍵となる。しかし、何よりも大切なのは、「この音楽が、なぜ今も生きているのか」を感じることである。
映画、ゲーム、そしてポップ ── 身近に潜むクラシック
クラシック音楽は、私たちの日常の「裏側」に流れている。たとえば──
映画『2001年宇宙の旅』で使われたリヒャルト・シュトラウス《ツァラトゥストラはかく語りき》
ゲーム『ファイナルファンタジー』シリーズで頻繁に使われるオーケストラ風の編曲
坂本龍一が手がけた映画『戦場のメリークリスマス』の主題曲の構造
CMやYouTube動画で流れる「それっぽい壮大な音楽」
これらは、クラシックの響きが「感情を揺さぶる手段」としていかに強力かを物語っている。音楽が、個人の記憶と文化的記憶の橋渡しになる瞬間だ。
初心者にこそおすすめしたい“最初の一歩”のクラシック
では、「クラシックを聴いてみたいけど、どこから始めればいいか分からない」という人に向けて、いくつかの“入口”となる音源を紹介したい。
音楽は「知る」ことで、もっと豊かになる
クラシック音楽は、一見難解に思えるかもしれない。しかし、背景を少し知るだけで、まったく違う景色が見えてくる。作曲家がどんな時代を生き、どんな想いを込めたのか。どんな形式で、どんな響きを求めたのか。それを知ることで、音楽は“音の博物館”ではなく、“音の物語”として私たちの耳に届くようになる。
音楽を「教養」として学ぶのではなく、「声」として感じる。そんなクラシックの旅へ、次回から一緒に出かけよう。

Sera H.:時代を越える音楽案内人/都市と田舎、過去と未来、東洋と西洋。そのあわいにいることを好む音楽ライター。クラシック音楽を軸にしながら、フィールド録音やアーカイブ、ZINE制作など多様な文脈で活動を展開。書くときは、なるべく誰でもない存在になるよう心がけている。名義の“H”が何の頭文字かは、誰も知らない。