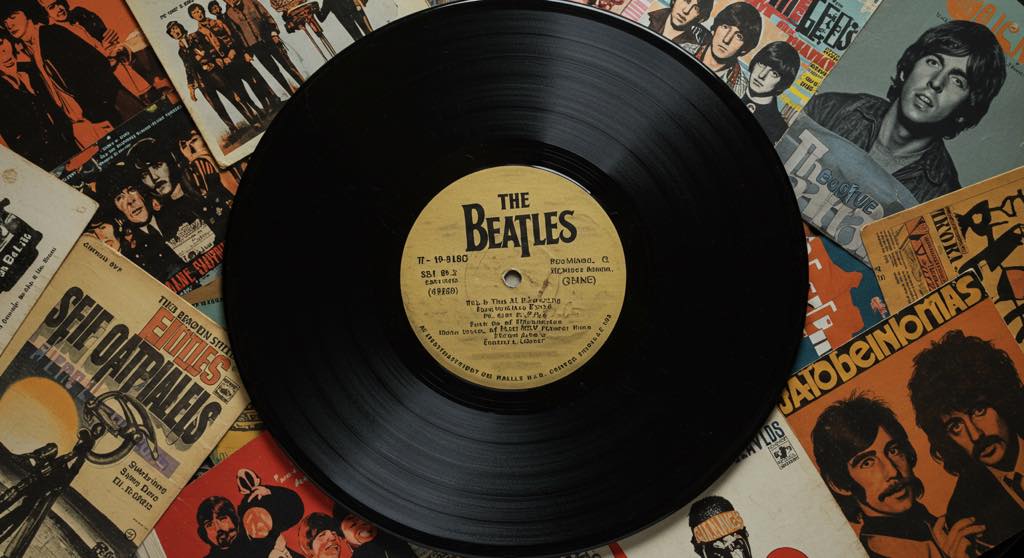
1960年代前半──“侵略”なきポップシーン
1963年、世界は静かだった。
リヴァプールからやってくるはずだった4人組は存在せず、「ブリティッシュ・インベージョン」という言葉は歴史の辞書に載らない。代わりにアメリカのチャートを席巻したのは、モータウンとスタックスのソウル・サウンドであった。
マーヴィン・ゲイの「Can I Get a Witness」(1963)、ザ・スプリームスの「Where Did Our Love Go」(1964)が長期にわたり全米を支配。白人ポップスは依然としてフランキー・ヴァリ&ザ・フォーシーズンズ、ビーチ・ボーイズの「Surfin’ U.S.A.」(1963)といった軽快なサウンドが中心であった。
一方イギリスでは、ローリング・ストーンズがブルース直系の演奏を続ける。ビートルズとの「ポップ対不良」という図式がないため、彼らは初期からシカゴ・ブルース路線を深化させ、「Little Red Rooster」(1964)のようなシングルが英国チャートを制覇。だが、その音はアメリカで爆発的ブームを起こすにはやや渋すぎた。
1960年代後半──ブルースとサイケの二極化
1965年、アメリカではボブ・ディランがフォークからロックへ移行。「Like a Rolling Stone」が全米2位を記録し、詩的で社会性のあるロックが広がる。ビートルズ不在の空白を、ディランとビーチ・ボーイズが埋める形となる。
ただしサイケデリックの爆発は局地的だ。『Revolver』や『Sgt. Pepper’s』が存在しないため、ポップ・サイケは世界的現象とならず、グレイトフル・デッド「Dark Star」(1968)、ジェファーソン・エアプレイン「White Rabbit」(1967)といった西海岸発のサウンドは、アメリカのカウンターカルチャー内に限定されたムーブメントとなった。
イギリスではクリーム、ザ・フー、ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスがブルースとハードロックの間を突き進み、ロックはますますギター中心の音楽として成熟。ヒッピー的なカラフルさよりも、音の重量感が重視された時代であった。
1970年代──大人のロックとフォーク黄金時代
アルバム文化の到来は遅れた。『Sgt. Pepper’s』のような作品がなかったため、「アルバムは芸術」という価値観が一般化するのは1970年代半ばである。
ローリング・ストーンズは『Exile on Main St.』(1972)でブルース・ロックの頂点を築き、レッド・ツェッペリンは『Physical Graffiti』(1975)でハードロックの金字塔を打ち立てる。だが、両者ともビートルズ的なポップ・メロディは持たず、ロックは「大人が聴く音楽」へと傾斜していく。
フォーク・ロックはキャロル・キング『Tapestry』(1971)、ニール・ヤング『Harvest』(1972)が大ヒット。日本ではGSブームが起きなかったため、フォークの隆盛はさらに長引き、吉田拓郎「結婚しようよ」(1972)や井上陽水「夢の中へ」(1973)が若者文化を牽引する。
1980年代──MTV時代とビートレス・ポップ
1981年、MTV開局。ビートルズ不在のポップ史では、MTVが初めて「世界同時的な音楽現象」を作り出す装置となる。
マイケル・ジャクソン『Thriller』(1982)、プリンス『Purple Rain』(1984)、マドンナ『Like a Virgin』(1984)が世界中の耳と目を奪う。ここで初めて、ビートルズに匹敵する規模のポップ・アイコンが複数登場した。
一方ロックはU2『The Joshua Tree』(1987)、ブルース・スプリングスティーン『Born in the U.S.A.』(1984)のように社会性を帯びたサウンドが主流に。ギターを中心としたバンド文化は、もはや「政治や社会を語るための手段」として機能していた。
1990年代以降──サンプリング文化の変質と新たな遺産
1990年代、ヒップホップが世界の音楽地図を書き換える。だが、ビートルズのカタログが存在しないため、パブリック・エネミーやビースティ・ボーイズが使うネタは大きく異なり、サンプリングの歴史そのものが別物となる。代わりにジェームス・ブラウン、スライ & ザ・ファミリー・ストーン、マーヴィン・ゲイらの音源がさらに徹底的に掘り起こされ、黒人音楽の遺産はより強固な礎を築くことになった。
オアシスやブラーといったブリットポップも誕生しない。90年代UKロックはレディオヘッド『OK Computer』(1997)のような芸術的実験が早くから前面に出て、ポップ・ロックの軽やかさはほぼ希少種になっていた。
21世紀、音楽はストリーミングで地球規模の共有財産となる。だが、世界共通の“原点”としてのビートルズが存在しないため、音楽教育や文化的記憶はより地域ごとに分散し、世界のポップ史は「多極化」したものとして受け継がれていく。
結語
ビートルズが存在しない世界は、決して音楽が貧しくなるわけではない。
むしろ、よりブルース寄りで、黒人音楽主導の歴史が加速し、ポップの普遍性よりも地域性と尖鋭性が際立つ時代が訪れていただろう。
だが、その代償として「世界が同じ曲を口ずさむ瞬間」は、今よりずっと少ない歴史になっていたはずである。

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。








