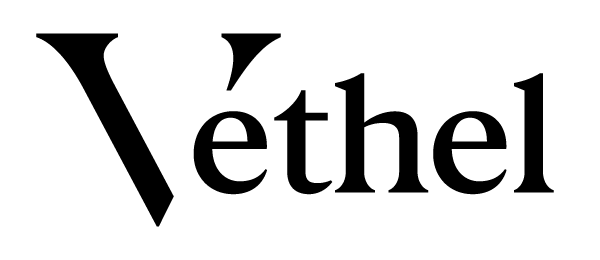序章:パンクが存在しない世界という、最大級の“文化実験”
1976年、もしロンドンにもニューヨークにも、あの粗暴な3コードの反逆がまったく現れなかったとしたら、20世紀終盤のカルチャーはどうなっていただろうか。セックス・ピストルズの“アナーキー”は叫ばれず、ラモーンズの疾走ビートは降ってこない。クラッシュの政治性も、ブラック・フラッグの狂騒も存在しない。
この仮説の衝撃は、単に「音楽ジャンルのひとつが欠ける」というレベルではない。パンクとは、音楽産業に対する爆発物であり、文化の価値観を丸ごと作り替えた地殻変動であるからだ。つまりこの仮定は、「もし地球から地殻変動が丸ごと起こらなかったら、現代の地形はどうなったか」というレベルの問いに等しい。
そして結論から言えば、こうなる。オルタナティブは生まれず、グランジも生まれず、エモもインディーロックも存在しない。音楽の価値観は1970年代のまま硬直し、音楽産業は巨大資本による支配を維持し続け、カルチャーはずっと“上から与えられるもの”のままだった。
以下では、そんな恐ろしい世界線を徹底的に妄想し、歴史を組み替えてみたい。
第一章:パンクなき70年代後半 ── プログレとハードロックの帝国支配が続く
パンクとは本来、巨大化しすぎた70年代ロックへの反動として登場した。シンセが増え、1曲15分の組曲が増え、ロックは“巨大構造物”へと変貌していった。そこへのアンチとして、最低限のコードと最低限の技術で、“誰でも演奏できる音楽”としてパンクは生まれた。もしこれが起きなかった場合、何が起きるか?
プログレは1977年以降も衰退しない
キング・クリムゾン、ジェネシス、ELP…本来なら“ロックは複雑化しすぎた”“規模が大きくなりすぎた”という反動で、パンクをきっかけに急速に影響力を失っていく。しかしパンク不在の世界ではそのまま地位を維持し続ける。70年代末以降も、ロックは複雑な構成を競い合い、シンフォニックな方向へと進む。
ハードロックは巨大アリーナ産業へ
レッド・ツェッペリンやディープ・パープル路線は、80年代になっても“反逆性の象徴”として扱われ、さらに商業的な巨大化の道をたどる。巨大レーベルはそこで莫大な利益を生み続け、「ロック=大掛かりなツアーを行える一部のスターの音楽」
という構造が維持される。ロックは“選ばれた者だけの音楽”として上流階級の象徴となり、グラマラスな巨大産業は全力でそれを後押しする。この世界線には、小さなクラブで汗を飛ばしながら演奏するロックバンドもいない。
第二章:オルタナが存在しない──ニルヴァーナもソニック・ユースもいない世界
パンクは消えても、個人の反逆心が消えるわけではない。ただその反逆は、音楽として形を持たない。実際の歴史では、1970年代後半~80年代初頭にかけて、パンクの残滓がポストパンクやノーウェイヴを生み、その後にオルタナティブの根が育っていった。しかしパンクがなければ、その土壌はそもそも存在しない。
もしパンクがなければ、ソニック・ユースは生まれない
彼らのノイズ美学やインディ精神は、パンクが開いた価値観の自由度に依存している。この世界線では、彼らは学生時代に“変な音楽をやる自由”を見つけられず、前衛芸術かクラシックの領域に進んだかもしれない。
ニルヴァーナ「Smells Like Teen Spirit」は存在しない
グランジはパンクとメタルの雑種として生まれた。パンクがなければグランジも存在しない。90年代初頭、世界を変えたあの“4コード爆発”はなく、80年代のハードロック路線がそのままメインストリームを占領し続ける。
オルタナティブという概念そのものが存在しないため、音楽は「メジャー vs マイナー」という二項に収まったままである。
間の“インディ”という選択肢がない。
第三章:エモは絶対に生まれない──内面のパンクが封じられる
エモは、“心の叫びをパンクの方法論で表現する”ところから始まった。DIYな録音、自己表現の自由、日記のような歌詞──
これらはすべてパンクが開いた文化的スペースである。この世界線では、それが存在しない。
内面の叫びは、巨大レーベルが求める“表現のフォーマット”に矯正される
繊細な少年少女が、自宅でギター片手に作った音楽が世界に届く、そんな奇跡は絶対に起こらない。音楽は“訓練されたプロによるもの”であり、“市場が認めたもの”だけが流通する。結果、この世界に生まれる音楽はどれも「正しく整えられた感情」であり、荒削りな心の震えが表に出る余地はない。エモは、文化として成立する前に死ぬ。
第四章:DIYとインディーレーベル文化は壊滅──音楽産業は永久に“巨大企業の世界”
パンクがもたらした最大の革命は、音楽の“経済構造”を変えたことである。
パンクがもたらした経済革命
- 自分たちでレーベルを作る
- 自分たちで録音する
- 自分たちでツアーを組む
- 自分たちでフライヤーを作る
- 大資本を介しない音楽文化を育てる
これらはパンク以前には存在しなかった。しかし、この世界線では当然、これらは一切発展しない。

音楽のすべては大企業の寡占状態へ
インディペンデントな仕組みが生まれなければ、若いアーティストは大企業の門を叩く以外に方法がない。
巨大レーベルに所属できなければ、音楽で食べていくことは不可能だ。
結果として音楽の価値観は、「良い音楽=売れる音楽」という1970年代の基準からまったく更新されない。オリジナリティでも反逆でもなく、市場が求めるフォーマットにどれだけ忠実かで評価が決まる。
第五章:クラブカルチャーの発展も遅れる──“下からの革命”が起きない
パンク精神は、ダンスミュージックの発展にも影響を与えている。シカゴ・ハウスやデトロイト・テクノが発展したのは、DIY的なクラブ文化があったからだ。しかしこの世界線では、クラブミュージックの発展も大幅に遅れる。
クラブは“上流階級の社交場”として固定
音楽がDIYで広まらないため、若者が自分たちのダンスパーティーを組織する文化も育たない。クラブカルチャーは高級化し、一般の若者の手の届かないものになっていく。本来なら「みんなの音楽」だったはずのハウスやテクノは、ニッチな上流文化としてひっそり栄えるだけだ。
第六章:カウンターカルチャーの空洞化──若者は何に怒るのか?
パンクがなければ、若者は“怒りを表現する言語”そのものを手にできない。社会への抗議、政治への反発、資本主義批判、格差への怒り──パンクはそれらを直接的に表現する回路だった。この回路が失われた世界はどうなるか?
怒りがアートに昇華されず、社会不安として蓄積し続ける
つまり若者文化は“脱出口のない圧力鍋”のような状態になる。この世界は、政治的な不満が暴発しやすく、社会運動は過激化する傾向を持つ。つまり、カルチャーが怒りを吸収してくれない世界は、政治がその怒りの全てを浴び続ける世界なのである。

終章:パンクが生まれたことは、単なる幸運ではない
パンクは、“下から文化を作り直せる”という希望そのものであった。
誰でも音楽を作れて、
誰でもバンドができて、
誰でもレーベルを作れて、
誰でも世界を変えられる──
この価値観を壊したら、カルチャーは70年代で時間停止する。
パンク不在の世界は、
「自由」のない世界である。
私たちが今、Spotifyでインディの知らない若手を発見できるのも、
YouTubeで自宅で録った音源が世界を動かせるのも、
全部パンクの“自由の導火線”があったからだ。
もしもパンクが登場していなかったら──?
その答えはこうだ。
現代の音楽文化は、ここまで豊かでも自由でもなかった。
そして、私たち自身の人生のサウンドトラックも、まったく違うものになっていたに違いない。
※本コラムは著者の妄想です。

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。