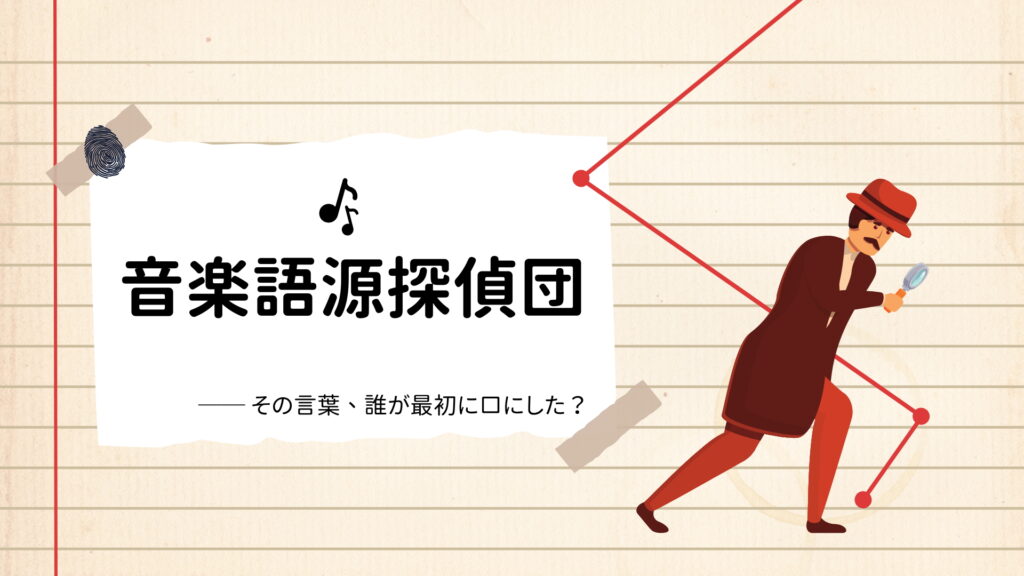音楽語源探偵団– tag –
-

[音楽語源探偵団]Vol.22:「ハウス」は誰が名付けたのか?── クラブの床から生まれた、音楽ジャンル以前の“呼び名”
ハウスミュージックという言葉ほど、当たり前のように使われながら、その由来が曖昧なジャンル名も珍しい。テクノ、ヒップホップ、パンク、ジャズ──多くの音楽ジャンルには、思想や構造、あるいは明確な発明者が存在する。しかし「ハウス」は違う。それは... -

[音楽語源探偵団]Vol.21:夜のロンドンが産んだ魔法──“Acid Jazz”という言葉が生まれた瞬間
曖昧な光と煙の中で、生まれるはずのなかった言葉 1980年代後半のロンドンは、音楽の坩堝であった。パンクの残り香が街角に漂い、ニューウェーヴがファッションと結びつき、レゲエやソウル、ファンク、そしてジャズが混ざり合い、昼と夜の境界が曖昧になっ... -

[音楽語源探偵団]Vol.20:MCという存在──ヒップホップ文化が生んだ観客との対話者
序章:MCとは何か 音楽における「MC」とは、単にマイクを持って話す人ではない。DJのパフォーマンスをサポートし、観客を盛り上げ、時にはリズムに乗って即興でラップを披露する者を指す。特にヒップホップ文化において、MCは単なる進行役ではなく、曲と観... -

[音楽語源探偵団]Vol.19:サンプリングという魔法──学者、メーカー、ヒップホップが紡いだ音楽の再生史
サンプリングとは何か? 「サンプリング」という言葉は、現代の音楽制作において日常語である。既存の音源の一部を抽出し、新たな文脈で再利用する行為──これが音楽的意味でのサンプリングである。しかしその起源は単純ではなく、技術、文化、言葉、法制度... -

[音楽語源探偵団]Vol.18:MIDIという魔法の言葉──誰が言い出し、どう広まったのか
シンセサイザー群雄割拠の時代 1970年代後半、シンセサイザーは急速に進化を遂げていた。Moog、ARP、Sequential Circuits、そしてRolandやYAMAHAといったメーカーが、アナログシンセからデジタル制御への過渡期にさまざまな機材を送り出していた。 しかし... -

[音楽語源探偵団]Vol.17:「打ち込み」という言葉の系譜──機械仕掛けの音楽が生んだ日本独自の表現
「打ち込み」という言葉はどこから来たのか 「打ち込み」という言葉は、日本の音楽シーンに特有の用語である。英語で言えば「programming」や「sequencing」といった表現にあたるが、国内では1980年代以降「シンセサイザーやリズムマシンにリズムやフレー... -

[音楽語源探偵団]Vol.16:「アイドル」という言葉の誕生──日本芸能史における“Idol”の受容と変容
欧米の“teen idol”と日本への輸入 「アイドル」という言葉は日本オリジナルの造語ではない。元来は英語の “idol” に由来し、「偶像」「崇拝の対象」を意味する単語である。宗教的には「偶像崇拝」というニュアンスで使われるが、20世紀に入ると芸能やポピ... -

[音楽語源探偵団]Vol.15:ガレージから響いた反逆の轟音──“Garage Rock”という言葉の軌跡
荒削りな音が「ガレージ」と呼ばれた理由 1960年代半ばのアメリカでは、ビートルズの成功に触発されて無数のティーンエイジャーがバンドを組み、地元のパーティや高校のダンスホールで演奏していた。彼らはしばしば最新のヒット曲をカヴァーし、時にオリジ... -

[音楽語源探偵団]Vol.14:音を“持ち上げる”という革命 ── チョーキングの誕生と進化
ギター奏者にとって「チョーキング(string bending)」は、もっとも感情を伝えやすい技法のひとつである。音を押し上げ、唸らせ、時には泣かせるような表現が、指先のほんのわずかな力加減で生み出される。ピアノにはできず、サックスにも難しい、まさに... -

[音楽語源探偵団]Vol.13:ドンとシャリでロックする ── 日本発サウンド用語の旅路
オーディオ評論から生まれた言葉 「このアンプ、ドンシャリっぽい音がするね」──バンド練習の現場で一度は耳にするこのフレーズ。だが、よく考えると「ドンシャリ」っていったい誰が言い出したのだろう? 実はこの言葉の起源は、ギタリストやバンドマンで...