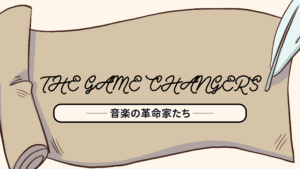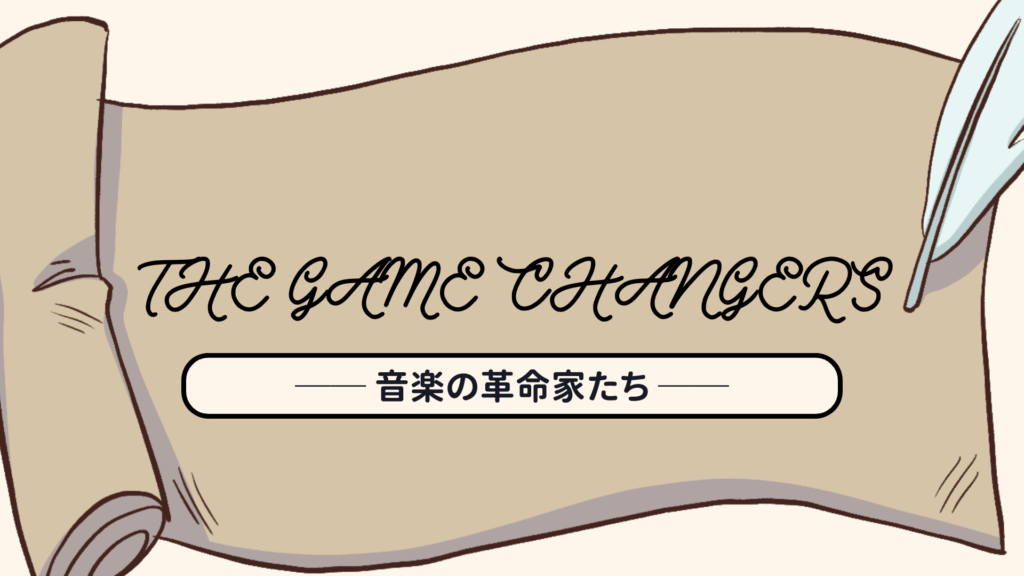
1966年秋、ひとりの黒人ギタリストがアメリカからロンドンへと渡った。その男がたった数ヶ月で「ロックの神話」を書き換えるなど、誰が予想できただろう。
ジミ・ヘンドリックス──この名前が世界を席巻するきっかけとなったのは、間違いなくイギリスだった。黒人ブルースの血を引く青年が、白人の若者たちを熱狂させる。人種も国境も飛び越え、音が世界を動かした瞬間だった。
チャス・チャンドラーとの出会い
話を戻そう。1966年、ニューヨークのクラブ「Cafe Wha?」──そこに出演していた“ジミ・ジェイムズ&ザ・ブルー・フレイムス”を偶然観たのが、元アニマルズのベーシスト、チャス・チャンドラーだった。
チャスはすぐに才能を見抜いた。「こいつは凄い。ロンドンに連れて行こう」。ジミのアグレッシブなプレイは、アメリカよりもむしろ、ブルース・リバイバルの熱が高まっていたイギリスでこそ受け入れられる、と確信したのだ。
ジミは迷わず飛んだ。故郷を離れ、まるで“異国の神”になるかのように。
The Jimi Hendrix Experience結成
ロンドンに降り立ったジミにとって、最初の課題は“自分の音を具現化するバンド”をつくることだった。チャスの紹介で、ノエル・レディング(ベース)とミッチ・ミッチェル(ドラム)という2人の白人ミュージシャンが加入し、The Jimi Hendrix Experienceが結成される。
この人選が絶妙だった。ノエルはロック/ポップの感覚を、ミッチはジャズの流れを持ち込んだ。そしてジミはアメリカのブルースとファンクをベースに、3人でしかできない「化学反応」を起こしていく。
世界がひれ伏した“ファースト・インパクト”
Experienceの初ステージは、わずか50人ほどの観客を前にした小さなクラブで行われた。しかしその噂は瞬く間に広がり、たった数週間後にはエリック・クラプトンやジェフ・ベック、ビートルズのメンバーたちが彼の演奏を見にくるようになる。
中でも有名なのは、クラプトンのバンド「クリーム」のステージにジミが飛び入り参加したエピソードだ。クラプトンはその日、《Killing Floor》をジミが一発で完璧に弾き倒したのを見て、袖に下がりながら「もうやめようかな」と呟いたという(クラプトン本人は後にこの発言を否定)。
それはただの上手さではなかった。ギターを“叫ばせる”ような独特のトーン、歪みとフィードバックを自在に操るセンス、そしてステージ上での圧倒的存在感──すでに彼は“完成されていた”。
デビュー・シングル《Hey Joe》
1966年12月、Experienceのデビュー・シングル《Hey Joe》が発売される。この曲はアメリカのトラディショナル・バラッドを下敷きにしたカバーだが(編注:起源については諸説ある)、ジミの手にかかれば、それは「絶望の愛と殺意のブルース」と化した。
緩やかなテンポで始まるこの曲は、ジミの哀愁を帯びたボーカルと、沈んだギターのトーンが印象的だ。特筆すべきはソロパート。まるでギターが嘆いているかのように歌い、聴く者の胸をざらつかせる。
この1曲で彼は「ギターで心をえぐる男」として、完全にロンドンの音楽シーンに君臨した。
1stアルバム《Are You Experienced》という革命
1967年5月、デビュー・アルバム《Are You Experienced》が発売される。これが**ロック史における“地殻変動”**であったことは、今でも広く語り継がれている。
収録曲は《Purple Haze》《Manic Depression》《Fire》《The Wind Cries Mary》《Foxy Lady》──どの曲も、当時の誰とも違う世界を描いていた。ギターの音は爆発し、ドラムは跳ね、ジミの声は夢と現実のあいだを浮遊していた。
中でも《Purple Haze》は彼の代表曲として語り継がれる。“サイケデリックの象徴”でありながら、1分1秒たりとも無駄のない構成とギターリフが印象的である。
そして何より、彼の音は“黒人音楽の語法”を持ちながら、それを白人ロックの新たな文脈に乗せるという、かつて誰も試みなかったブリコラージュを成立させていた。
「体で音を出す」ということ
ジミのプレイは視覚的でもあった。ギターを歯で弾く、背中で弾く、腕を回してノイズを出す──そんなトリックは、ロックンロールの興奮を再定義した。
だがそれは決して“見せもの”ではない。彼にとってギターは単なる楽器ではなく、自分の体の延長だった。だからこそ、彼のプレイには嘘がなかった。痛みも喜びも、すべてが指先から、ストラトキャスターの弦に流れていった。
ロンドンが、ジミを“世界”へ送り出す
1967年の「モンタレー・ポップ・フェスティバル」に向けて、ジミはアメリカに戻る。その前夜、彼はすでにイギリスで「革命児」として認識されていた。若者たちはジミの服装、髪型、言葉を真似た。黒人が白人の若者たちの“ヒーロー”になった瞬間だった。
この「逆転」は、音楽にしかできない魔法だったのかもしれない。

Jiro Soundwave:ジャンルレス化が進む現代音楽シーンにあえて一石を投じる、異端の音楽ライター。ジャンルという「物差し」を手に、音の輪郭を描き直すことを信条とする。90年代レイヴと民族音楽に深い愛着を持ち、月に一度の中古レコード店巡礼を欠かさない。励ましのお便りは、どうぞ郵便で編集部まで──音と言葉をめぐる往復書簡を、今日も心待ちにしている。