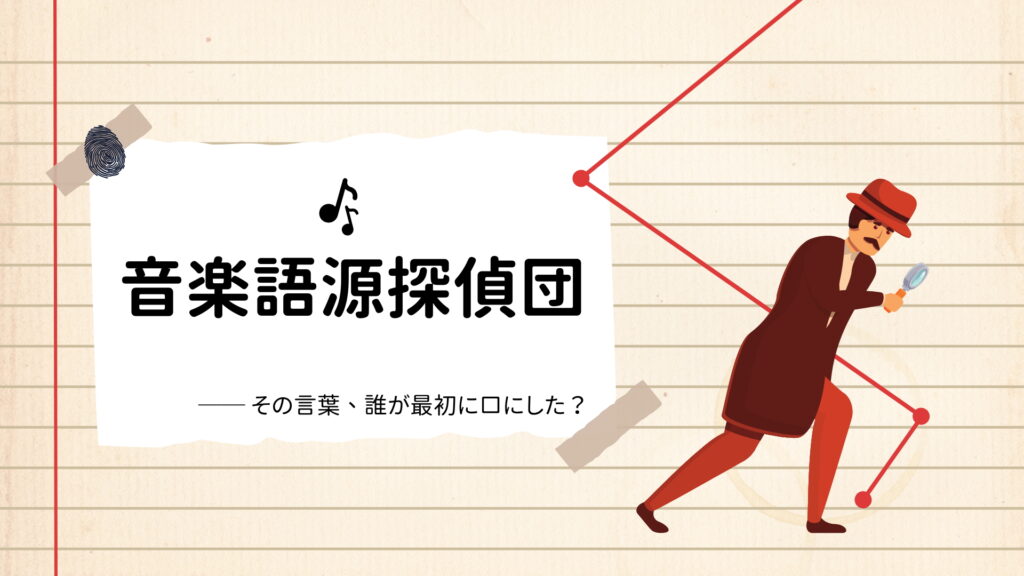
オーディオ評論から生まれた言葉
「このアンプ、ドンシャリっぽい音がするね」──バンド練習の現場で一度は耳にするこのフレーズ。だが、よく考えると「ドンシャリ」っていったい誰が言い出したのだろう? 実はこの言葉の起源は、ギタリストやバンドマンではない。オーディオ評論界である。1970年代、日本のオーディオ誌には「ドンシャリ型」という表現が頻繁に登場した。
「ドン」とは、ウーファーが低域を力強く鳴らす様子を表す擬音語。「シャリ」は、トゥイーターから出る高域がきらびやかに響くさまを示す。つまり「低音と高音は派手に出るが、中音域は凹んで聴こえる音」をまとめて形容したのが「ドンシャリ」だった。当時のオーディオ評論家が愛用した擬音は数多い。たとえば「ボワつく」「キンキンする」「コモる」など。しかし「ドンシャリ」はそのキャッチーさで群を抜いていた。
バンドサウンドに持ち込まれる
このオーディオ用語がバンドマンに浸透するのは1980年代。きっかけは、ギター雑誌や楽器店の解説だ。アンプのEQをいじって、BASSとTREBLEを大きく上げ、MIDDLEをぐっと下げたセッティング──この音はまさに「ドン」と「シャリ」が強調されている。説明の際に「これ、ドンシャリです」と言うと、ギター初心者にも一瞬で伝わる。
こうして「ドンシャリ」は、ギターやベースの音作り用語として日本のバンド文化に定着した。海外では「scooped mids(中域をすくい取った音)」や「smiley face EQ」といった表現が使われるが、擬音でズバリ言い表す「ドンシャリ」は日本独自のものだ。
ドンシャリが似合う音楽と似合わない音楽
では、バンドサウンドで「ドンシャリ」はどう使われてきたのか。ここからはいくつかの参考曲とともに見ていこう。
• Van Halen – “Ain’t Talkin’ ’Bout Love” (1978)
エディ・ヴァン・ヘイレンのギターサウンドは、まさにドンシャリ的。中域をやや削って、低音と高音を突き抜けさせたブラウン・サウンドは、当時のギタリストに衝撃を与えた。
• Metallica – “Enter Sandman” (1991)
メタル界では“ミドルカット”の音作りが伝統。ジェイムズ・ヘットフィールドのリフは低音の「ドン」と高音の「シャリ」で轟音の壁を築く。ただしライブでは中域を足して輪郭を補うことも多い。
• Nirvana – “Smells Like Teen Spirit” (1991)
カート・コバーンのギターも典型的なドンシャリ寄り。特にクリーンと歪みを行き来する中で、歪んだパートは中域を削ったパワーコードで迫力を出している。
逆に、ブルースやジャズの世界では「ドンシャリ」は歓迎されない。エリック・クラプトンやB.B.キングのギターは中域の“人声に近い帯域”こそ命。中域を引っ込めると、歌心や泣きのニュアンスが失われてしまうからだ。つまり「ドンシャリ」とはジャンルによって“正義”にも“邪道”にもなるサウンドなのだ。
EQつまみと「ドンシャリ顔」
面白いのは、グラフィックイコライザーをいじった時の見た目だ。BASSとTREBLEを上げ、MIDDLEを下げると、EQのフェーダーがちょうど「にっこり笑った顔」の形になる。これが英語圏で言うsmiley face EQ。日本ではその形を見せながら「これ、ドンシャリね」と説明すれば一発で伝わる。
ちなみに、ベースプレイヤーの間でも「ドンシャリセッティング」は有名だ。スラップベースが広まった80年代後半、マーク・キング(レヴェル42)やマーカス・ミラーといった名手たちが、中域を抑えて低音のドンと高音のパーカッシブなシャリを強調した。日本のベーシストでもT-SQUAREの田中豊雪、カシオペアの櫻井哲夫などフュージョン勢が追随。ベースの世界でも「ドンシャリ」は定着していく。
ドンシャリ批判とリハスタあるある
もちろん「ドンシャリ」はしばしば批判も浴びる。
リハーサルスタジオでありがちな光景がある。
ギタリストは「抜けが悪い」と思ってBASSとTREBLEを上げ、MIDDLEを削る。
ベーシストも「抜けが悪い」と思って同じことをする。
結果、バンド全体で中域が消え、ヴォーカルの声が埋もれてしまう。
音の隙間を設計するどころか、誰もが「ドンシャリ」に走ってしまうと、サウンドはむしろバランスを失う。スタジオで先輩から「お前らドンシャリしすぎ!」と怒られた経験を持つバンドマンは少なくないだろう。
「ドンシャリ」という言葉の魅力 ##
それでも「ドンシャリ」が愛されるのは、何よりそのわかりやすさにある。音楽理論を知らない人でも、言葉を聞けばなんとなくニュアンスが伝わる。
• 「ドン」は腹に響く低音。
• 「シャリ」は耳に刺さる高音。
• そして「中域が薄い」。
この3つのイメージが、わずか4文字で共有できるのだから強い。しかも語感がどこかユーモラスで、会話に混ぜても空気が柔らかい。海外の“scooped mids”は理屈的で硬いが、日本語の「ドンシャリ」には音の感覚を即座に喚起する力がある。擬音文化の勝利とも言えるだろう。
まとめ ── ドンとシャリの狭間で
結局のところ、「ドンシャリ」という言葉には明確な“言い出しっぺ”はいない。1970年代の日本のオーディオ評論から自然に生まれ、1980年代にバンドマンの現場へと定着した。
そのサウンドはジャンルによっては王道であり、時に批判の的でもある。だが「ドン」と「シャリ」という二つの音が、今もギターやベースのEQを回す若者たちに直感的に伝わっていくのは確かだ。
音楽に正解はない。ミドルを上げるか下げるかは美学の問題だ。ただ一つ言えるのは、スタジオの片隅で「ドンシャリすぎ!」と笑い合う、その瞬間にこそバンドの文化が息づいている、ということだ。
※本コラムは筆者の見解であり、諸説あります

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。







