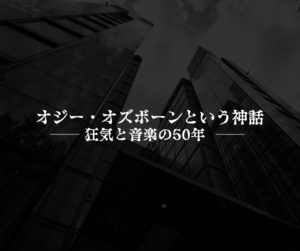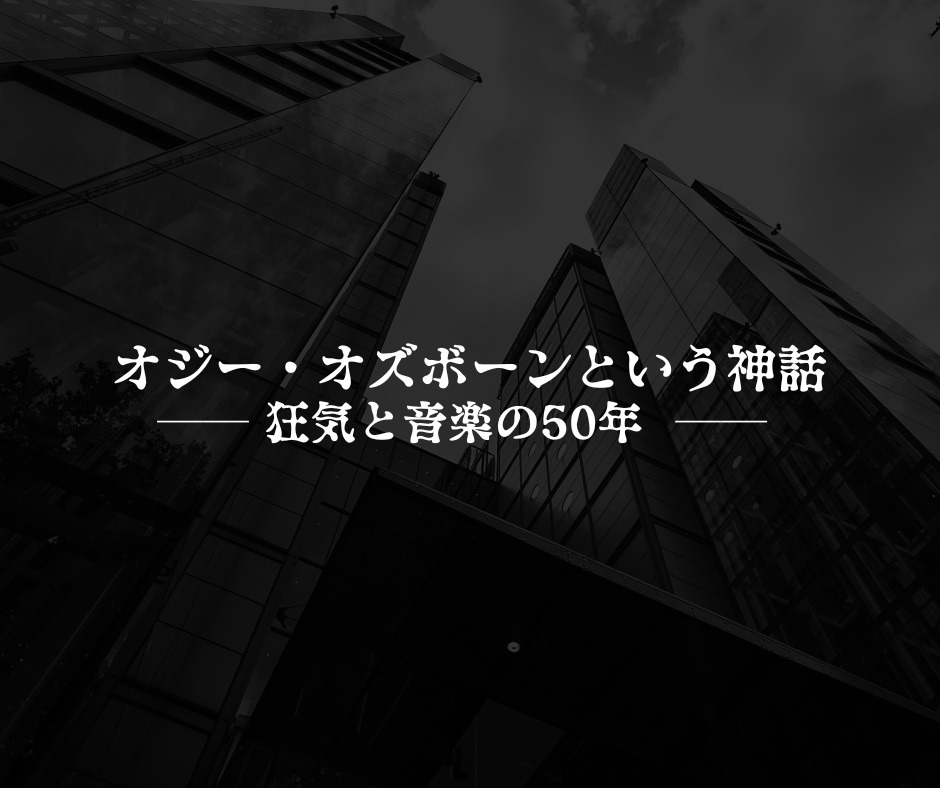
1979年、オジー・オズボーンはブラック・サバスを解雇された。酒とドラッグにまみれた日々、もはや音楽に情熱も体力も残っていなかった。バンドの創設者にして象徴だった彼は、皮肉にも、最も象徴的な“問題児”として切り捨てられたのだ。
しかし、そこからすべてが始まった。捨てられたロックンローラーが、ひとりの女性と、ひとりの天才ギタリストに出会い、80年代のメタルを再定義するアイコンへと“再誕”する──。これは、死にかけた“マッドマン”が、自らの狂気を武器に変えた壮絶な復活劇である。
絶望のホテルで
オジーがブラック・サバスを解雇された直後、彼はロサンゼルスの安ホテルに籠もり、昼夜を問わず酒を飲み続けていた。電話には出ず、風呂にも入らず、ただカーテンを閉めた部屋の片隅で虚ろに座っていた。
「生きている理由がなかった」とオジーは語る。仲間に捨てられ、音楽業界の誰からも必要とされない現実は、彼の魂を空洞にした。かつて悪魔の声を持つと讃えられた男は、自らの破滅を待つだけの存在になっていた。
シャロンという奇跡
そんな彼を救ったのが、のちに妻となるシャロン・アーデンである。当時、彼女は父ドン・アーデンが率いるJet Recordsの社員で、バンドマネージャーとして辣腕を振るっていた。
父に代わってオジーの再生を託されたシャロンは、単なる情けや義務ではなく、「彼にはまだ未来がある」という確信を持っていた。彼女は、腐敗しかけた才能の奥に残された“火種”を見逃さなかったのだ。
シャロンは酒を断つよう叱咤し、音楽をやれと迫り、オーディションを組織してバンドを立ち上げた。オジーにとって、シャロンは再起のエンジンであり、彼の第二の人生そのものだった。
天才ギタリスト、ランディ・ローズとの出会い
ソロキャリアの鍵を握る存在となったのが、若きギタリスト、ランディ・ローズである。クラシックとロックを融合させたギター奏法、驚異的な技術、そして何より楽曲構成力──彼の才能は群を抜いていた。
ランディはクワイエット・ライオットというバンドに在籍していたが、オジーとの出会いが彼の運命を変える。オーディションのわずか30秒でオジーは彼の虜となった。「これが俺のギタリストだ」と確信したという。
当時まだ23歳のランディは、ギタリストであると同時に作曲家でありアレンジャーであり、事実上の音楽監督でもあった。オジーは彼の美意識と構成力に深く影響を受け、それまでにない壮大さと叙情性を楽曲に取り入れていく。
『Blizzard of Ozz』──ソロ初作での衝撃
1980年、ついにソロ・デビュー作『Blizzard of Ozz』がリリースされる。これは単なる復帰作ではなく、ヘヴィメタルの新たな地平を切り拓く革命的なアルバムだった。
冒頭の「I Don’t Know」からして、力強いギターリフとともにオジーの鋭いボーカルが響き、聴き手の心を掴む。そして続く「Crazy Train」は、オジー最大のヒット曲として今なお世界中で愛されている。
この曲の印象的なギターリフとランディの炸裂するソロは、まさにメタルとポップの架け橋といえるもので、アメリカではMTV時代を象徴するロック・アンセムとなった。
「Mr. Crowley」ではオカルト的なテーマとともに、パイプオルガンのような荘厳なキーボードと美しいギターソロが融合し、“悪魔的な美”を体現している。サバス時代のオジーでは決して表現できなかった繊細さが、このアルバムにはあった。
ランディの創造性と“二人の関係性”
ランディとオジーの関係は、単なるバンドメンバー同士のそれではなかった。父を亡くしていたランディにとって、オジーは“保護すべき存在”だったという。
彼はオジーに酒やドラッグをやめるよう促し、音楽に集中させようとした。逆にオジーは、ランディのクラシカルなフレージングや作曲スタイルから多くを学び、自らの表現を再構築した。
2作目『Diary of a Madman』(1981年)では、その成果が如実に表れている。表題曲はバロック的な構成を持ち、メタルでありながら幻想文学のような世界観を漂わせている。サウンドはより陰鬱で洗練され、ランディのギターが導く構造美が際立っている。
空中の悲劇──ランディ・ローズ死去
だが、1982年3月19日、悲劇が起きる。ツアー先のフロリダで、ツアーバス運転手が遊覧目的で小型飛行機を飛ばし、そこに乗っていたランディ・ローズが事故で命を落とす。機体はツアーバスの車体に接触・激突。わずか25歳という若さで、ロック史に残る天才はこの世を去った。
この出来事は、オジーの心に深い傷を残した。「あの時、俺の一部も死んだ」と後年語っている。ランディの死は、音楽的損失である以上に、人生そのものの喪失だった。
ランディは、単なるギタリストではなく、オジーの再生の象徴であり、精神的支柱でもあった。彼の不在は、ソロ活動における最大の痛みであり、永久に癒えない傷となった。
『Bark at the Moon』と新時代
1983年、オジーは悲しみを抱えたまま『Bark at the Moon』を発表する。このアルバムには新ギタリストとしてジェイク・E・リーが参加し、より鋭角的でスピード感あるサウンドを提示した。
表題曲「Bark at the Moon」はMTVで大量にオンエアされ、オジーは“ヴィジュアル・ショック”を伴う存在として、若い世代にも強烈にアピールする。彼が演じる狼男の姿は、まさにマッドマンの象徴だった。
このアルバム以降、オジーはただの“過去の人”ではなく、現役のメタル・スターとして80年代を突き進む。ザック・ワイルドの登場もあり、音楽性はさらに硬質でダイナミックになっていく。
オジーという表現者
ソロキャリアのオジーは、サバス時代よりも遥かに“個”としての表現が強まっている。ステージでは血糊を浴び、コウモリに噛みつき、狂気とユーモアを紙一重で演出する。その一方で、歌詞には孤独、不安、愛と死といった繊細な感情が込められている。
マッドマンという仮面の裏には、人生の喪失と痛みを抱えた“人間オジー”が存在する。その脆さと激しさの共存こそが、彼の音楽に宿る魅力なのだ。
再生の代償と、その栄光
ブラック・サバス脱退からソロ成功への道のりは、決して順風満帆ではなかった。愛する者の死、精神の崩壊、そして常に付きまとう「過去の自分」との戦い。
だが、オジーはそれらすべてを自分の音楽に投影し、サバス時代を凌駕するほどの個性と創造性で、80年代のロックシーンを生き抜いた。
奇跡の復活は、狂気と苦悩を内包したからこそ可能だった。そして、彼はその痛みさえエンターテインメントへと昇華させた──それが、唯一無二の“マッドマン”オジー・オズボーンなのである。

Jiro Soundwave:ジャンルレス化が進む現代音楽シーンにあえて一石を投じる、異端の音楽ライター。ジャンルという「物差し」を手に、音の輪郭を描き直すことを信条とする。90年代レイヴと民族音楽に深い愛着を持ち、月に一度の中古レコード店巡礼を欠かさない。励ましのお便りは、どうぞ郵便で編集部まで──音と言葉をめぐる往復書簡を、今日も心待ちにしている。