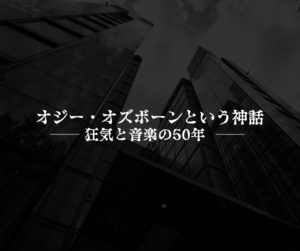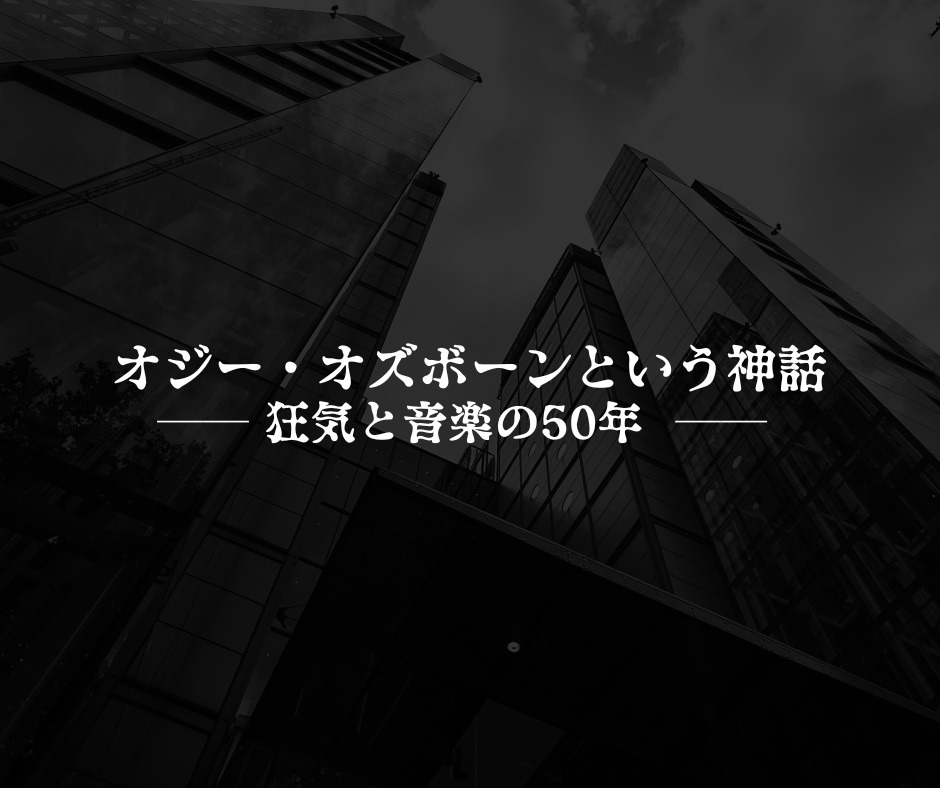
「音楽が、こんなにも怖くて、こんなにも格好いいなんて思わなかった」。1970年代、ブラック・サバスの音楽に触れた多くの若者が、そう口を揃えて語った。教会での礼拝よりも、酒場で流れるサバスのレコードの方が“神聖”だった時代。悪魔崇拝、戦争、ドラッグ、狂気。70年代のブラック・サバスは、ロックが踏み込むにはあまりに危険な場所へと、自ら音を運んだ。中心にいたのは、地獄の門を開く男 ── オジー・オズボーンである。
サバス黄金期と“重金属の夜明け”
1970年、デビュー作『Black Sabbath』のリリースと同年に、彼らはすぐさま2枚目『Paranoid』を発表する。この作品こそ、ヘヴィメタルというジャンルの礎を築いた金字塔といえよう。
「War Pigs」「Iron Man」「Paranoid」といった曲は、当時の戦争(特にベトナム戦争)や機械文明への警鐘、そして精神的崩壊をモチーフにしており、ラヴ&ピースを唱えるヒッピー文化とは完全に一線を画した。「黒」「怒り」「不安」「死」──そんな言葉がサウンドとして具現化されていた。
オジーの甲高く、時に呪詛のようにも響くヴォーカル、トニー・アイオミの重く歪んだリフ、ギーザー・バトラーの哲学的な歌詞、そしてビル・ワードの獣のようなドラム。その4人が噛み合ったとき、音楽はただの娯楽ではなく、“儀式”になった。
この頃、彼らの音楽は「悪魔の音楽」としてキリスト教保守層から忌み嫌われた。だがそれはむしろ、逆説的に彼らのカリスマ性を高めることになった。オジー自身は「悪魔なんて信じてねえよ」と笑っていたが、ステージ上での彼の姿は、まさに“プリンス・オブ・ダークネス”そのものであった。
『Master of Reality』と“サウンドの重力”
1971年発表の『Master of Reality』は、ブラック・サバスのサウンドがさらなる重量を帯びた作品である。このアルバムではギターとベースのチューニングが半音下げられ、より重く、より暗く、より攻撃的な音像が完成した。
「Sweet Leaf」ではマリファナへの愛が、「Children of the Grave」では戦争と暴力に晒された子どもたちの未来が、「Into the Void」では終末思想がそれぞれ描かれている。これは、単なる音楽以上に、当時の社会の暗部を映し出す鏡だった。
そのサウンドは、のちのドゥームメタル、ストーナーロック、グランジ、さらにはスラッシュメタルにまで影響を及ぼすことになる。オジーのヴォーカルもこの頃から一層表現力を増し、無垢さと狂気を行き来する“語り手”としての役割を確立していった。
ドラッグ、アルコール、そして“内側からの崩壊”
サバスの成功は、栄光だけをもたらしたわけではない。ツアーに次ぐツアー、膨大な収入、そして常に張り詰めた緊張感。それらはメンバーの精神を少しずつ蝕んでいった。特にオジーは、アルコールとドラッグへの依存が深刻化し、しばしばライブの直前まで姿が見えなかったり、ステージ上でまともに歌えなかったりするようになる。
その一方で、1972年の『Vol. 4』ではサウンド的な新機軸も見られた。ピアノやストリングスを導入した「Changes」などは、オジーの繊細な一面が垣間見えるバラードである。だがその裏で、スタジオにはレコード会社から提供された大量のコカインが運び込まれ、バンドは“音楽と破滅の共同体”と化していった。
「コカインは冷蔵庫よりも身近な存在だった。何を食べたかは覚えてないが、何を吸ったかは全部覚えてる」
──オジー・オズボーン(後年のインタビューより)
1973年『Sabbath Bloody Sabbath』では一時的にクリエイティビティが復活し、シンセや複雑なアレンジが導入される。だがその代償は大きく、創造と破滅のバランスは崩れ始めていた。
「Never Say Die!」── 終焉の足音
1975年以降、バンド内の不和は顕在化する。オジーとアイオミの間には音楽的方向性の違いだけでなく、ライフスタイルの面でも深刻な対立があった。オジーはよりストレートなロックンロールを求め、アイオミはより複雑で緻密な構成を志向していた。
1978年に発表された『Never Say Die!』は、そんな内部崩壊の兆しが濃く表れた作品である。決して悪いアルバムではないが、サバスの魅力だった“邪悪な一体感”は感じられず、評論家・ファンともに評価は分かれた。
その年のアメリカ・ツアーでは、なんと前座にヴァン・ヘーレンを起用。オジーは彼らのパフォーマンスを観て打ちのめされる。「俺たちはもう、過去のバンドだ」と痛感したという。
そしてその年の末、ついにオジーはブラック・サバスから解雇される。
“追放”と“解放”──闇の中に射す光
表向きは“音楽的方向性の違い”という建前であったが、実際にはオジーのアルコール・ドラッグ依存と、音楽的モチベーションの低下が原因であった。彼はしばらくの間、ホテルに閉じこもり、酒に溺れ、社会との接点を完全に断ってしまう。
だが、ここで一人の女性が登場する。シャロン・アーデン ── 後にオジーの妻となる彼女が、マネージャーとして彼をソロ活動へと導くことになるのである。
オジー・オズボーンの第一章、すなわち“ブラック・サバスのボーカリスト”としての時代は、こうして幕を下ろす。しかし彼の物語は、ここからさらに加速し、より狂気に、より壮絶に、より感動的な展開を見せていく。
それはまさに、地獄から這い上がった者にしか鳴らせない音楽 ── 狂気と再生のメタルである。

Jiro Soundwave:ジャンルレス化が進む現代音楽シーンにあえて一石を投じる、異端の音楽ライター。ジャンルという「物差し」を手に、音の輪郭を描き直すことを信条とする。90年代レイヴと民族音楽に深い愛着を持ち、月に一度の中古レコード店巡礼を欠かさない。励ましのお便りは、どうぞ郵便で編集部まで──音と言葉をめぐる往復書簡を、今日も心待ちにしている。