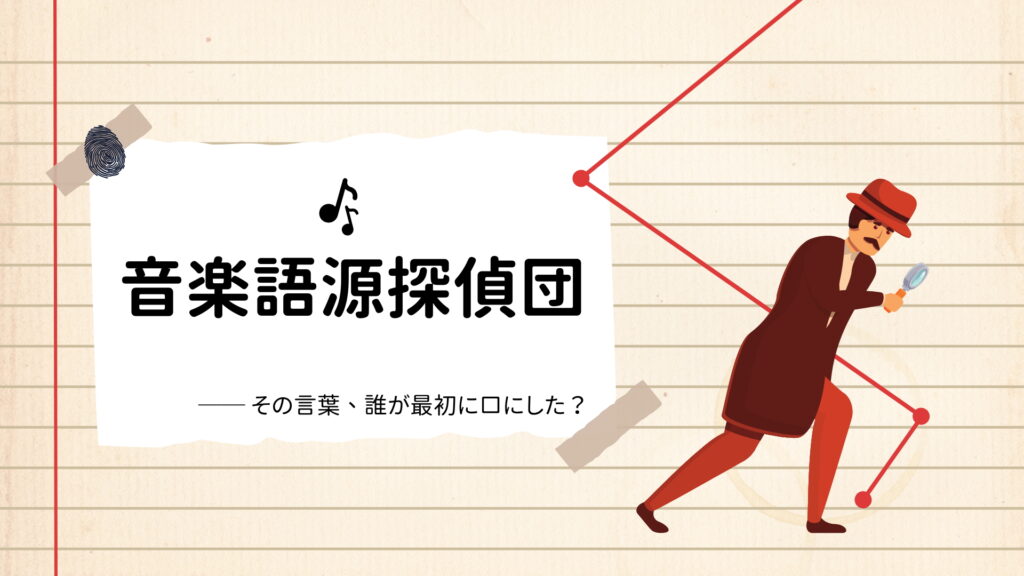
1970年代のブロンクスで、ヒップホップの胎動とともに生まれた革新的なDJテクニック「スクラッチ」。レコードを「回す」のではなく「こする」ことで音を生み出すこの手法は、単なる演出ではなく、サウンドそのものを“楽器”として操る行為であった。ギターに歪みが生まれた瞬間、あるいはターンテーブルにエフェクターを接続したかのように、スクラッチは音楽の地平を塗り替えた。その始まりには、一人の少年の偶然と、それを文化へと昇華させた多くのDJたちの知恵と闘争があった。
「スクラッチ」はどこから来たか?
スクラッチの発明者として広く語られているのが、グランド・ウィザード・セオドアである。彼は1975年、まだティーンエイジャーだったころ、自宅でターンテーブルをいじっていたときに母親に「うるさい!」と叱られ、その瞬間、レコードに手を置いた。すると、スピーカーから不思議な“こすれた音”が鳴った。これを面白がった彼は、意図的に前後にレコードを動かし、音を刻むようにして操作するテクニックを試し始めた。
この一瞬の偶然が、のちに「スクラッチ」と呼ばれるムーブメントの起点となる。本人も後年のインタビューで「俺が最初にやったし、“スクラッチ”って名付けたのも自分だと思う」と語っている。真偽の程はさておき、少なくともスクラッチのパイオニアであることに疑いはない。
音楽の“流れ”を“切り刻む”という行為
当初のスクラッチは、いわば「DJのスパイス」だった。曲と曲をつなぐ間の一瞬や、MCの声を強調するための短い効果音的な使い方が主であった。しかし、グランドマスター・フラッシュの登場により、その位置づけが大きく変わる。フラッシュは「クイックミックス理論」により、ブレイクビーツの反復や2枚使いでの演奏を極め、スクラッチの精度と表現力を高めていった。
さらに1980年代に入ると、スクラッチはパフォーマンスの中心に躍り出る。たとえばRUN-D.M.C.のDJであるジャム・マスター・ジェイや、ビースティ・ボーイズと共に活動したDJハリケーンらが、その技術を駆使して大規模ステージで観客を沸かせた。
スクラッチは、単なる“技術”ではない。それは「再生された音楽」を「生演奏の一部に変える」行為である。しかもその楽器は、通常の意味での“楽器”ではない。日常のメディアであったはずのレコードを、プレイヤーの操作一つでアートに昇華する── これがスクラッチの根源的な革命性である。
スクラッチの多様化とアートフォーム化
1980年代後半から1990年代にかけて、スクラッチはさらなる進化を遂げる。ターンテーブリズム(Turntablism)という新しい潮流の中で、スクラッチはもはや“DJプレイの一部”ではなく、“演奏そのもの”となった。
特にDJキューバート、ミックス・マスター・マイク、DJクレイズといったアーティストたちは、DMCやITFなどのDJバトルにおいて驚異的なスキルを披露。単音のスクラッチ、リズムを刻むスクラッチ、さらにはメロディを操るスクラッチなど、多彩なテクニックが開発された。
ターンテーブルとミキサーは、ピアノやギターと同じ「演奏装置」として認識されるようになった。特にハムスタースイッチ(フェーダーを逆方向に設定する)や、ボディトリック(身体の一部を使ったパフォーマンス)などは、クラシック音楽におけるヴィルトゥオーゾにも似た技巧性を感じさせる。
テクノロジーとの融合:デジタル・スクラッチの時代
2000年代に入ると、Serato Scratch LiveやTraktor ScratchといったDVS(Digital Vinyl System)の登場により、アナログ盤を使わずともデジタル音源でスクラッチが可能になった。USBやMP3ファイルを扱いながらも、あたかもレコードを操作しているかのような感触が得られるこの技術により、スクラッチはかつてないほど手軽に、多くの人々の手に届くようになった。
その一方で、「アナログでこそスクラッチの魂が宿る」という信念を貫くオールドスクール勢との間で文化的な対立も生まれた。しかし、最終的には「ツールの違いは表現の幅でしかない」という認識が広まり、アナログとデジタルは共存の道を選んでいる。
ヒップホップを越えて:グローバル化と異ジャンルとの交差
スクラッチはヒップホップの象徴として誕生したが、現在ではあらゆるジャンルに影響を与えている。エレクトロニカ、ドラムンベース、ジャズ、果てはクラシックや即興音楽の分野にまで、スクラッチの要素は組み込まれている。日本でも、DJ KentaroやDJ Krush、Grooveman Spotなどが世界的に活躍し、スクラッチを軸とした表現を深化させてきた。
また、Turntablismを即興演奏や現代音楽の一技法として取り入れる流れも強まっている。リスナーはもはや「音源の破壊」としてスクラッチを聴くのではなく、新たな音楽の構築手法として受け取っているのだ。
終わりなき“こすれ”
スクラッチは、単なる効果音や見世物ではない。それは、記録された音楽に対する反抗であり、再生行為への創造的異議申し立てである。CDでも、配信でも、AI音声でも、スクラッチは常に“物理”を必要とする。指先の微細な動き、フェーダーの切れ味、耳で感じるタイミング ── そうしたすべてが、音楽を再構成する素材となる。
グランド・ウィザード・セオドアが最初にレコードを“こすった”瞬間から、およそ50年。スクラッチは、進化と拡散を繰り返しながら、いまも新たな音を生み出している。言葉にできないグルーヴの波に乗って ── それは、終わることのない音楽の冒険である。

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。







