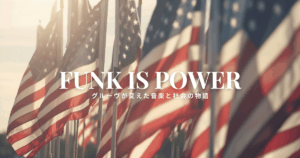ファンクは単なるダンス・ミュージックではない。それは人種、政治、スピリチュアリティ、そして大衆文化が複雑に交錯する音の運動体であった。本連載では、ジェームス・ブラウンの革新に始まり、スライ&ザ・ファミリー・ストーンによるユートピア的ヴィジョン、Pファンクの神話世界、そしてポップ化・商業化へと至るダイナミズムを全6回にわたって検証する。ファンクというジャンルが、いかにして20世紀後半のブラックカルチャーと世界の音楽地図を塗り替えたのか。その核心に、リズムとともに迫っていく。
イントロダクション:リズムは死なず
1970年代から80年代にかけてのファンクは、Pファンクの壮大な神話世界や、ディスコと手を取り合ったポップファンクの隆盛を経て、社会の深層と共鳴しながら、常に時代の鼓動を刻んできた。だが時代は移ろい、90年代に入ると、音楽産業の中でのファンクの存在感は薄れ、「終わったジャンル」のように語られることもあった。しかし、それは決してファンクの死ではなかった。むしろ、ファンクは姿を変えて生き延び、さまざまなジャンルの中で脈打ち続けている。
本稿では、そんなファンクの“その後”を辿る。ヒップホップ、ネオ・ソウル、エレクトロ、インディポップ──ファンクは、時に主役として、時に遺伝子として、21世紀の音楽にどのようなかたちで受け継がれていったのか。そしてこれからどこへ向かうのか。答えはひとつではない。だが、私たちは耳をすませることで、そのリズムの連なりを感じとることができるはずである。
ヒップホップのなかのファンク──Gファンクとサンプリング文化の継承
ファンクがそのままのかたちでポピュラリティを維持したわけではない。1980年代以降、そのビートとベースラインは、新たなストリートの音楽=ヒップホップの文脈で生まれ変わった。とりわけ1990年代の「Gファンク」(Gangsta Funk)ムーヴメントは、ファンクの復権を象徴する事例である。
ドクター・ドレーの『The Chronic』(1992年)は、ジョージ・クリントンやブーツィー・コリンズのPファンク・クラシックスをサンプリングしながら、カリフォルニアの黒人青年のリアルを語った革新的な作品であった。スヌープ・ドッグやウォーレン・Gらもその潮流を担い、太く、うねるようなファンク由来のベースラインを土台にしながら、ヒップホップという表現形式を再構築していった。
また、サンプリングという技術が、ファンクの遺伝子を未来に繋いだ。Pファンクだけでなく、スライ&ザ・ファミリー・ストーン、ジェームス・ブラウン、クール&ザ・ギャング、ザップなど、あらゆるファンク・レジェンドたちのグルーヴが、新たな文脈で再生されたのである。こうしてファンクは、90年代以降のヒップホップにおいても根幹的な役割を果たし続けた。
ネオ・ソウルとオルタナティブR&B──深層のファンク
1990年代末から2000年代にかけて登場した「ネオ・ソウル」や「オルタナティブR&B」もまた、ファンクの影響を色濃く受け継ぐジャンルである。ディアンジェロ、エリカ・バドゥ、ザ・ルーツ、ミュージック・ソウルチャイルドといったアーティストは、70年代ファンクの肉体性や内省性を自らの感性でアップデートした。
ディアンジェロの『Voodoo』(2000年)における緩やかで不均一なビート感覚は、Pファンク的な「ゆらぎ」を現代的に再解釈したものといえる。また彼はジェームス・ブラウンばりのシャウトと、ミニマルで粘着力のあるリズムを、あくまでソウルフルに融合させてみせた。これらの手法は、現代R&Bにおけるグルーヴの在り方に新たな視点を与え、多くのフォロワーを生み出している。
エリカ・バドゥやジル・スコットもまた、単なる懐古主義ではなく、ファンクを「語り」「問いかける」音楽として再構築した存在である。彼女たちが描き出す世界には、ファンク的な自由、反骨、そして霊性が息づいている。そのスピリチュアルで詩的なアプローチは、ファンクの本質が単なる音楽的構造ではなく、思想や生き方と深く関わっていることを示している。
電子音楽とファンクの融合──デーモン・アルバーンからサンダーキャット
ファンクのグルーヴは、21世紀の電子音楽にも新たな命を吹き込んだ。ゴリラズを率いるデーモン・アルバーンや、フライング・ロータス、サンダーキャット、アンダーソン・パークらは、ファンクのスピリットをエレクトロニクスと融合させ、極めて現代的なグルーヴを構築してきた。
サンダーキャットのベースプレイは、まさにブーツィー・コリンズの現代版であり、彼の作品には常にファンク由来の「遊び」と「深さ」がある。アンダーソン・パークはスヌープ・ドッグの直系にして、ネオ・ソウルとヒップホップ、そしてファンクを地続きに語ることができる希有な存在である。
また、ジャミロクワイやヴルフペックのような白人ファンク・リバイバルの流れも見逃せない。とりわけヴルフペックのミニマルでユーモラスなアプローチは、PファンクとJBファンクの「間(ま)」を知り尽くした現代的解釈といえるだろう。彼らの成功は、ファンクが人種や国境を超えて響きうる普遍的な音楽であることを物語っている。
日本のファンク、その行方──シティポップ以降のグルーヴ
日本におけるファンクもまた、独自の進化を遂げている。山下達郎、大瀧詠一、竹内まりやらによる「シティポップ」は、ファンク/ソウルのコード感とグルーヴを日本的ポップスに消化した代表例である。そしてその潮流は、Suchmos、Nulbarich、Awesome City Clubなどの現代的アーティストにも受け継がれている。
一方で、Ovall、WONK、Mime、Yogee New Wavesなどは、ファンクのリズムを骨格にしつつ、ジャズやヒップホップ、R&Bなどと自由に融合させた「和製ネオ・ソウル」的スタイルを展開している。こうした柔軟なアプローチは、まさにファンクが持つ“他者と混ざる力”の現れであり、ジャンルを超える対話の場となっている。
最近では、tofubeatsやSTUTSといったプロデューサー/ビートメイカーも、ファンクやソウルをルーツに持ちながら、クラブカルチャーや現代の都市感覚とリンクしたスタイルを提示している。ここにもまた、ファンクの「今」が息づいている。さらには、TempalayやMega Shinnosukeなど、インディー・ロックとエレクトロを自在に往来する若手たちの作品にも、ファンク的なリズム感がしばしば見られる。
ファンクの本質とは何か──ジャンルを超えた精神性
そもそもファンクとは何なのか。それは「ジャンル」である以前に「アティチュード(姿勢)」である。人々の身体を踊らせること、魂を震わせること、そして共同体のなかで連帯を生むこと──その根底には、自由を求める精神、他者との対話、そして時代と切り結ぶ批評性がある。
JBの「Say It Loud – I’m Black and I’m Proud」(1968年)に込められた自己肯定の叫び。スライ・ストーンの「Everyday People」に込められた多様性の肯定。これらは、音楽としての完成度のみならず、社会運動の文脈とも密接にリンクしていた。そしてその精神は、現代においても、BLM運動やLGBTQ+の可視化といった社会的文脈のなかで再び鳴り響いている。
エンディング:ファンクの未来は「いま」にある
ファンクは死んでいない。それどころか、ますます多様で、複雑で、しなやかになって生きている。時に露骨な形で、時に潜在的なレイヤーとして、現代音楽のあらゆるジャンルにその“鼓動”は息づいている。
ファンクとは何か? それは単なるジャンルではない。政治的な意思であり、身体的な実践であり、社会に対する眼差しである。踊ること、繋がること、感じること、そして違いを祝福すること。ファンクとは、リズムを通じた「連帯」であり、時代を超えた「運動」なのである。
そしてそのリズムは、いまこの瞬間にも、誰かの心臓の奥で、足元で、ステージの上で、鳴り続けている。未来のファンクは、きっとあなたの中にもある。

Jiro Soundwave:ジャンルレス化が進む現代音楽シーンにあえて一石を投じる、異端の音楽ライター。ジャンルという「物差し」を手に、音の輪郭を描き直すことを信条とする。90年代レイヴと民族音楽に深い愛着を持ち、月に一度の中古レコード店巡礼を欠かさない。励ましのお便りは、どうぞ郵便で編集部まで──音と言葉をめぐる往復書簡を、今日も心待ちにしている。