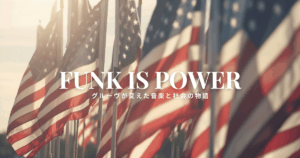ファンクは単なるダンス・ミュージックではない。それは人種、政治、スピリチュアリティ、そして大衆文化が複雑に交錯する音の運動体であった。本連載では、ジェームス・ブラウンの革新に始まり、スライ&ザ・ファミリー・ストーンによるユートピア的ヴィジョン、Pファンクの神話世界、そしてポップ化・商業化へと至るダイナミズムを全6回にわたって検証する。ファンクというジャンルが、いかにして20世紀後半のブラックカルチャーと世界の音楽地図を塗り替えたのか。その核心に、リズムとともに迫っていく。
1970年代後半、ディスコがアメリカの音楽シーンを席巻するなかで、ファンクは変容を迫られていた。しかしそれは衰退ではなかった。ディスコに吸収されながらも、ファンクはその本質──リズムへの執着、肉体性、そして社会的メッセージ──を維持し、時に反抗しながら、新たな表現の可能性を切り拓いていった。本稿では、プリンス、リック・ジェームス、ザップといったアーティストを中心に、ファンクとディスコの相克と交錯、そして次代への橋渡しとしての80年代ファンクの魅力を探る。
きらびやかな仮面の裏側──ディスコ化する時代とファンクの選択
1970年代後半の音楽シーンは、言うまでもなくディスコの隆盛に彩られていた。『サタデー・ナイト・フィーバー』(1977年)以降、四つ打ちのビートと華やかなストリングス、そして洗練されたダンスフロア仕様のサウンドは、アメリカの白人中産階級やユースカルチャーに広く浸透した。ファンクもその影響を免れることはなかった。クール&ザ・ギャングやアース・ウィンド&ファイアーのようなバンドは、ディスコ的なアレンジを取り入れつつ、ファンクの核を保ちながらチャートを賑わせた。
しかし、その一方で、ファンクの本質に立ち戻ろうとする動きもあった。より黒く、よりセクシュアルで、より挑発的な音楽。それがリック・ジェームスに代表される「パンク・ファンク」と呼ばれるアプローチである。ディスコの洗練に対して、リック・ジェームスは過剰なまでの装飾性と露骨なリリックで応答した。1978年の『Come Get It!』、続く1979年の『Bustin’ Out of L Seven』などは、踊れるが毒がある、官能的でありながらアナーキーなファンクを提示してみせた。代表曲「Give It to Me Baby」や「Super Freak」は、セクシャルなリリックと強烈なベースライン、硬質なグルーヴで、ディスコが提供する快楽とは異なる、より土着的で挑発的な喜びを体現していた。
プリンスとジャンルの解体──美学としてのファンク再生
1980年代初頭、ファンクは新たな表現者を得ることになる。ミネアポリス出身の天才、プリンスである。彼の登場は、ファンクというジャンルを内側から再構成し、ジャンルを横断する音楽美学を作り上げる転機となった。
プリンスのファンクは、単にグルーヴを提供するだけでなく、ロック、ポップ、ニューウェーブなどの要素を果敢に取り込み、また性差や人種、アイデンティティの境界線さえも曖昧にするものだった。『Dirty Mind』(1980年)や『Controversy』(1981年)は、性と政治が混じり合ったテーマを、ミニマルかつ鋭利なサウンドで包み込み、後の『1999』(1982年)や『Purple Rain』(1984年)でその爆発的な魅力を世界に知らしめた。
ここで重要なのは、プリンスがファンクの歴史と文脈に自覚的であった点である。彼のファンクは、スライ・ストーンの理想主義と、ジェームス・ブラウンの身体性、Pファンクの物語性を受け継ぎながらも、すべてをポップの文法へと変換してしまう稀有な表現力によって成立していた。つまり、ファンクを引用しつつも、それを記号として消費するのではなく、自らの音楽哲学の中心に据え直したのである。
機械仕掛けのグルーヴ──ザップとトークボックスの魔法
ファンクの変容において、技術革新の影響も無視できない。特に注目すべきは、ロジャー・トラウトマン率いるザップによるトークボックスの導入である。1980年のデビューアルバム『Zapp』に収録された「More Bounce to the Ounce」は、機械的で滑らかなグルーヴと独特の電子音声によって、ファンクに新たな質感を与えた。
ザップの音楽は、同時代のエレクトロ・ファンクや初期ヒップホップに大きな影響を与えた。トークボックスによる歌声は、人間の感情と機械の中間に位置する新しい表現方法として受け入れられ、後のGファンク──すなわちドクター・ドレーやスヌープ・ドッグが90年代に提示した西海岸ヒップホップの世界観──においてもサンプリングされ続けることとなる。
ロジャー・トラウトマンの死は、ひとつの時代の終わりを告げたが、その音楽は現在に至るまで、ファンクの未来を予見するものとして再評価され続けている。
ファンクの精神は死なず──ディスコ以後の抵抗と創造
ディスコとの融合、そしてポップとの接近という流れのなかで、ファンクは一見するとその輪郭を失いかけていた。しかし、本稿で見てきたように、リック・ジェームスの攻撃性、プリンスの越境性、ザップの技術革新などを通じて、ファンクはその核心たる「抵抗のリズム」を手放すことなく、むしろ時代に応じた表現として進化を遂げていたのである。
80年代のファンクは、音楽産業のなかでの生存戦略でありつつも、音楽的・文化的な革新の場でもあった。煌びやかなダンスフロアのなかでさえ、ファンクのビートはその本能的なエネルギーを失わず、次代の音楽家たちに受け継がれていった。
次回は、そうしたファンクの遺産が90年代以降どのように変容し、ヒップホップやネオ・ソウルといったジャンルに脈打っていくかを追っていく。ファンクの旅路は、まだ終わらない。

Jiro Soundwave:ジャンルレス化が進む現代音楽シーンにあえて一石を投じる、異端の音楽ライター。ジャンルという「物差し」を手に、音の輪郭を描き直すことを信条とする。90年代レイヴと民族音楽に深い愛着を持ち、月に一度の中古レコード店巡礼を欠かさない。励ましのお便りは、どうぞ郵便で編集部まで──音と言葉をめぐる往復書簡を、今日も心待ちにしている。