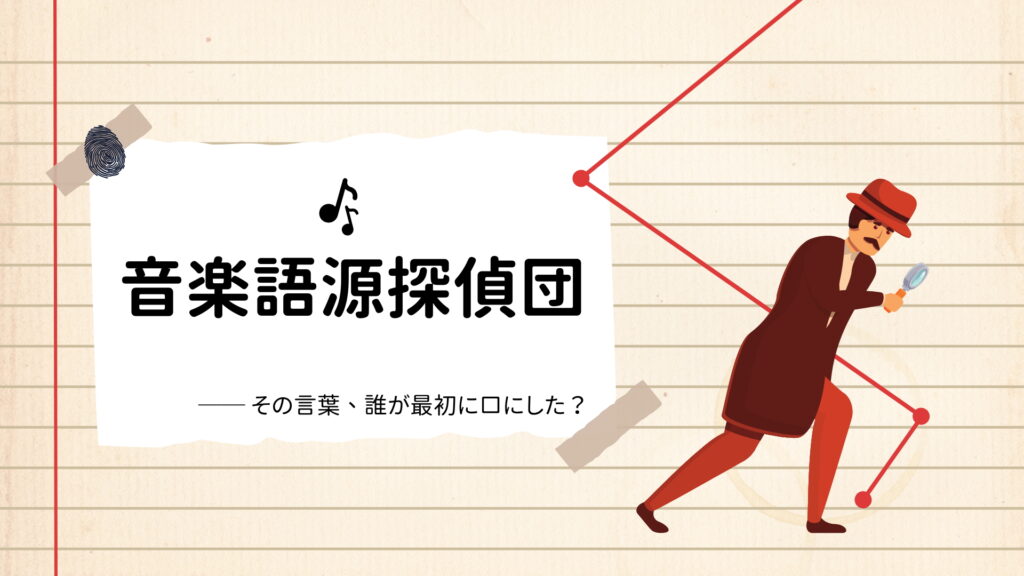
現代の音楽シーンを語る上で、テクノ(Techno)というジャンルは欠かせない存在となっている。無機質な電子音、反復するリズム、そして未来的なサウンド。クラブやフェスティバルで鳴り響くその音楽は、世界中の若者を魅了し続けている。しかし、「テクノ」という言葉は、いつ、どのようにして生まれたのだろうか? その起源を探ると、音楽の歴史と社会の変化が交錯する、興味深い物語が浮かび上がってくる。
デトロイトの若者たちと新しい音楽
1980年代初頭、アメリカ・デトロイト。自動車産業の衰退とともに荒廃したこの都市で、若き黒人ミュージシャンたちが新しい音楽を生み出していた。ホアン・アトキンス、デリック・メイ、ケヴィン・サンダーソン ── いわゆる「ベルヴィル・スリー」と呼ばれる彼らは、ヨーロッパのエレクトロニック・ミュージックやファンク、ディスコ、そして地元ラジオ局で流れていたクラフトワークやジョルジオ・モロダーのサウンドに影響を受け、独自の電子音楽を模索していた。
彼らの音楽は、既存のダンス・ミュージックとは一線を画していた。シンセサイザーやドラムマシンを駆使し、機械的で未来的なサウンドを追求したその音楽は、当時の主流であったハウスやディスコとも異なる、新しいジャンルの誕生を予感させた。
「テクノ」という言葉の誕生
この新しい音楽に、彼らはどんな名前をつけたらよいのか悩んでいた。そんな時、ホアン・アトキンスは未来学者アルヴィン・トフラーの著書『第三の波』(The Third Wave)に出会う。その中で「テクノレベルズ(Techno Rebels)」という言葉が登場し、技術革新とともに社会が変化する様子が描かれていた。アトキンスはこの言葉に強くインスパイアされ、自身のユニット“サイボトロン”の楽曲「Techno City」(1984年)や、後のレーベル名「Metroplex」にもその精神を反映させていく。
彼は自分たちの新しい音楽を「テクノ」と呼ぶことを決意し、「We call it TECHNO!(俺たちはこれをテクノと呼ぶ!)」という言葉を残したと言われている。この宣言が、後にジャンル名として世界に広がるきっかけとなった。
ヨーロッパと日本での「テクノ」の受容
一方、ヨーロッパや日本でも電子音楽の進化は進んでいた。特に日本では、1978年に音楽評論家・阿木譲が「テクノポップ(Techno Pop)」という言葉を使い、YMO(イエロー・マジック・オーケストラ)などの電子音楽を形容した。ここでの「テクノ」は、あくまで「テクノロジーを駆使したポップミュージック」という意味合いが強かった。
ヨーロッパでは、クラフトワークやニュー・オーダー、デペッシュ・モードといったバンドが電子音楽の先駆者として活動していたものの、「テクノ」という言葉がジャンル名として定着するのは、デトロイト発のサウンドがイギリスやドイツに伝わった1980年代後半以降である。
特に、1988年にイギリスのレーベル「10 Records」からリリースされたコンピレーションアルバム『Techno! The New Dance Sound of Detroit』が大きな転機となる。このアルバムには、デトロイトのアーティストたちの楽曲が多数収録され、「Techno」という言葉がジャンル名として世界的に認知されるきっかけとなった。
「テクノ」という言葉の意味とその変遷
こうして「テクノ」という言葉は、デトロイトの若者たちが生み出した革新的な電子音楽を指すジャンル名として定着した。しかし、時代とともにその意味は広がり、さまざまなスタイルやサブジャンルが生まれていく。ミニマル・テクノ、ハード・テクノ、テックハウス、インダストリアル・テクノなど、今日では多様なサウンドが「テクノ」の名のもとに存在している。
また、国や地域によって「テクノ」という言葉の使われ方にも違いがある。日本では、YMOや電気グルーヴなどのポップな電子音楽も「テクノ」と呼ばれることが多いが、欧米ではよりクラブ志向のダンスミュージックを指す場合が一般的だ。
テクノという言葉が持つ未来性
「テクノ」という言葉には、単なる音楽ジャンルを超えた意味が込められている。それは、テクノロジーと人間の関係、未来への憧れ、そして社会や文化の変革への期待 ── 。ホアン・アトキンスが「テクノ」と名付けたとき、彼は音楽だけでなく、時代そのものの変化を感じ取っていたのだろう。
今や「テクノ」は、世界中のクラブやフェスティバルで鳴り響き、世代や国境を超えて人々をつなぐ音楽となった。そのルーツには、デトロイトの荒廃した街で生まれた若者たちの創造力と、未来を見据えるまなざしがあった。彼らが「We call it TECHNO!」と宣言した瞬間、音楽の歴史に新たなページが刻まれたのである。
※本コラムは筆者の見解であり、諸説あります

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。







