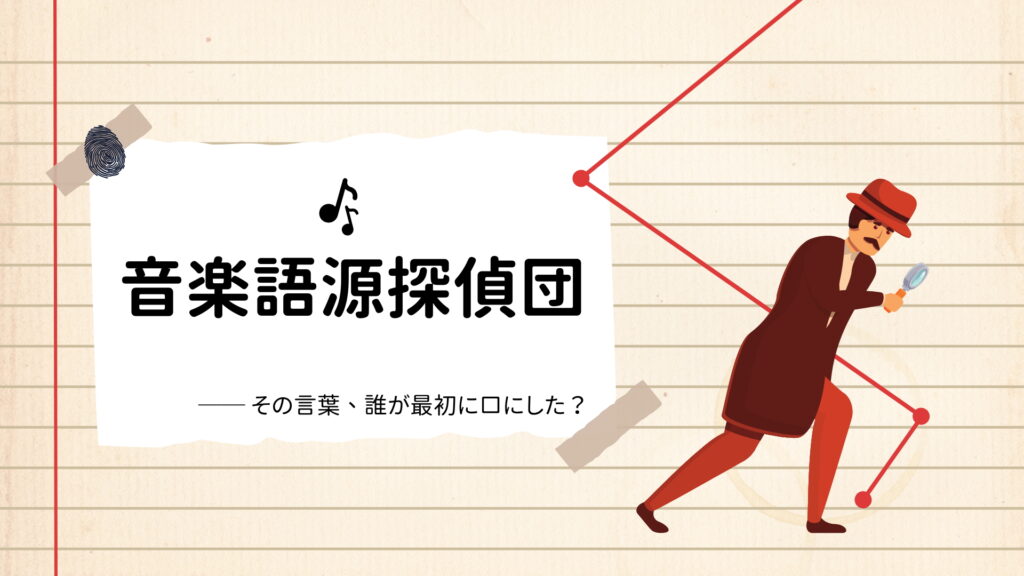
音楽において「ドラム」と聞いて思い浮かべるのは、ほとんどの場合、ドラムセット(ドラムキット)であろう。しかし、「ドラム」という言葉自体は、そのはるか以前から存在していた。打楽器の総称としての「drum」は、中世ヨーロッパにまでさかのぼることができる。ドラムとは、古英語の「drum(m)」やオランダ語の「trom」などに由来し、元々は「太鼓」を意味していた。音楽用語としての「ドラム」が誰によって最初に用いられたか、正確な記録はない。しかし、その概念は、音楽の歴史とともに自然発生的に育まれ、今日に至るのである。

軍楽隊が生んだ「近代ドラム」の原型
打楽器自体は人類史において最も古い楽器のひとつである。狩猟や儀式のために皮を張った楽器が叩かれ、それが音楽へと昇華していった。古代エジプトの壁画には、打楽器を打ち鳴らす人々の姿が描かれており、またアフリカ大陸各地では、太鼓を通じて言葉を伝える「トーキングドラム」文化も存在していた。つまり、「ドラム」という概念自体は、太古の昔から人間とともにあったといえる。
ただし、近代的な意味での「ドラム」が発展するのは、18~19世紀の軍楽隊においてである。ミリタリードラム(軍楽太鼓)は、行進のテンポを指示し、軍隊において非常に重要な役割を果たしていた。この時代、スネアドラム(小太鼓)とバスドラム(大太鼓)が明確に区別され、それぞれが専用の役割を担うようになったのである。ここでは「drummer(ドラマー)」という言葉もすでに定着していた。
ニューオーリンズとドラムセットの誕生
やがて19世紀末から20世紀初頭にかけて、ニューオーリンズを中心に興ったジャズの黎明期において、現代的な「ドラムセット」の原型が形作られる。これまで複数人で演奏していたスネア、バス、シンバルなどを、ひとりの奏者がまとめて叩くスタイルが考案されたのである。ここで初めて、「ドラム」が単なる打楽器の総称ではなく、「ドラムセットを演奏する楽器」としての意味を帯びるようになった。
ベイビー・ドッズと「歌うドラム」
この革新を担ったのが、ベイビー・ドッズである。ジャズ・ドラマーのパイオニアと称される彼は、スネアとバスを一体的に操作し、リズムに柔軟なニュアンスを与えた。ベイビー・ドッズは、当時の録音技術の制限もあり、細かなブラシワークやマレットの使用を工夫し、ドラムの音色の幅を拡大していった。「ドラムが歌う」という概念を最初に提示したミュージシャンのひとりと言ってもよいだろう。
スウィング時代のヒーロー、ジーン・クルーパ
さらに1930年代、スウィング時代の到来とともに、ドラムはバンドサウンドの推進力として決定的な役割を持つようになる。この時代の象徴的存在が、ジーン・クルーパである。彼はバディ・リッチと並び、ドラム・ソロという新たな表現手法を確立した。特に1937年の「Sing, Sing, Sing」における熱狂的なドラムパフォーマンスは、世界中の若者たちに「ドラム」を憧れの対象として刻み込んだのである。
マックス・ローチが開いた新しい地平
一方、第二次世界大戦後、ビバップが興隆すると、ドラマーにはさらに高いテクニックと即興性が求められるようになった。ここで登場するのが、マックス・ローチである。彼は単なる伴奏者ではなく、音楽そのものを構築する一員としてのドラムの役割を押し上げた。「ドラムが楽器として語りはじめる」瞬間である。
このように、ドラムという言葉とその意味は、時代とともに変容してきた。単なる「打楽器」から、「音楽を推進する力」、そして「独立した表現手段」へと進化したのである。その過程では、数多くの革新的なミュージシャンたちが、ドラムの可能性を切り拓いてきた。
現代におけるドラムの広がり
現代においても、「ドラム」という言葉は一義的ではない。ジャズ、ロック、ファンク、ヒップホップ、エレクトロニックミュージック──どのジャンルにおいても、ドラムはその音楽の核心を担い続けている。たとえば、ジョン・ボーナム(レッド・ツェッペリンのドラマー)が見せた巨大なグルーヴ感、トニー・アレン(フェラ・クティとともにアフロビートを創出したドラマー)の有機的なリズム、あるいは、ヤキ・リーヴェツァイト(Canのドラマー)のミニマルかつ実験的なドラミング。それらはいずれも、「ドラム」という言葉が単なる打楽器を越えて、文化的・芸術的な意味を帯びたことの証左である。
言葉を超えて鳴り響くもの
音楽とは、時に言葉を超える表現である。そしてドラムは、言葉が生まれる以前から、心臓の鼓動のように人間に寄り添ってきた。今日、我々が当たり前のように口にする「ドラム」という言葉には、悠久の歴史と、人類の情熱が宿っているのである。


Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。







