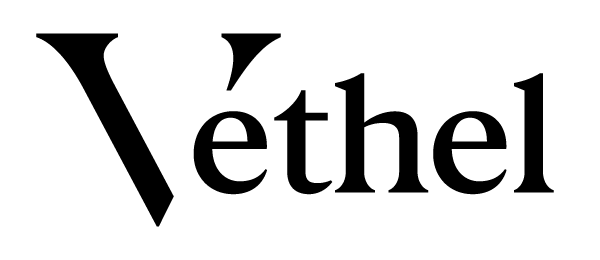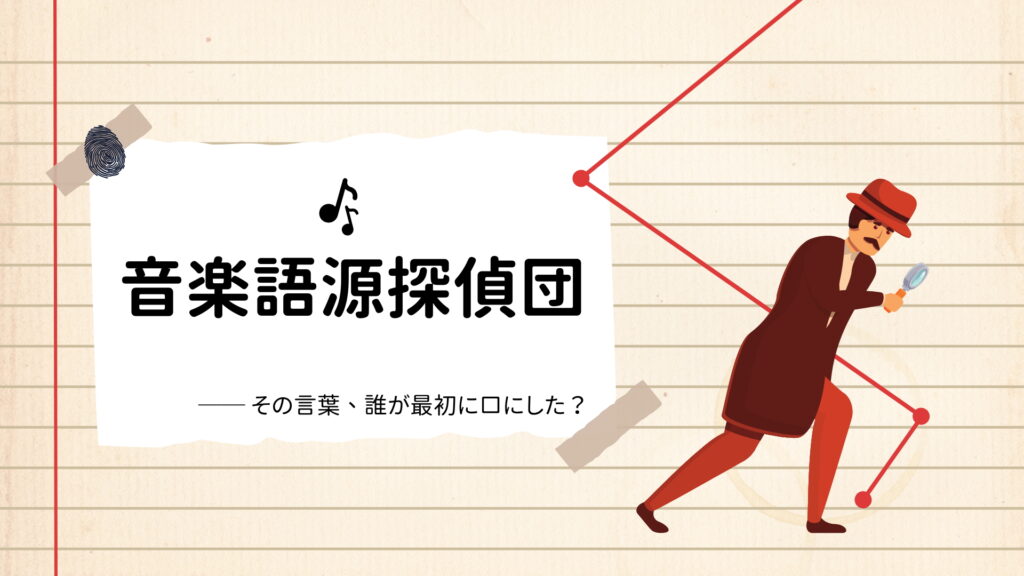
フュージョンに「言い出しっぺ」は存在しない
「フュージョン」という言葉を最初に使ったのは誰なのか? この問いに、明確な固有名詞で答えることはできない。なぜならフュージョンとは、誰かの思想や運動から生まれたジャンルではなく、音楽が“そうならざるを得なかった状態”を後から言語化した呼び名だからだ。
もともとfusionとは、異なるものが溶け合うことを指す一般語であり、音楽用語ではなかった。1960年代末、ジャズがロックやファンク、エレクトロニクスと交錯し始めたとき、その変化を一言で説明するために、この言葉が便宜的に使われるようになったのである。重要なのは、この言葉がミュージシャンの内側から生まれた自己定義ではなく、レコード会社やメディア、批評の側から貼られたラベルだったという点だ。
マイルス・デイヴィスが壊した境界線
フュージョンの起点を語るなら、やはりマイルス・デイヴィスの存在を避けることはできない。1969年の『In a Silent Way』、そして1970年の『Bitches Brew』。これらの作品でマイルスが行ったのは、新しいジャンルの提唱ではなく、既存の境界線を無造作に破壊する行為だった。
『In a Silent Way』に収められた同名曲では、エレクトリック・ピアノが作り出す静かな反復の上を、時間感覚の曖昧な即興が漂う。一方『Bitches Brew』の「Pharaoh’s Dance」では、ロック的なビートの反復と編集的手法が導入され、ジャズは一気に混沌へと踏み込んでいく。そこにはスウィングも、従来のジャズ語法もない。それでも、この音楽がジャズであることを否定できる者はいなかった。
マイルス自身は、この音楽をフュージョンと呼んではいない。ただ、同時代の音を必要なだけ取り込み、ジャズという器に流し込んだだけだった。
フュージョンを「音楽」にした弟子たち
フュージョンがジャンルとして認識されるようになったのは、マイルスのもとから巣立ったミュージシャンたちの活動によるところが大きい。彼らは、マイルスが提示した未分化な状態を、より輪郭のはっきりした音楽へと結晶化させていった。
ウェザー・リポートの「Birdland」は、その象徴的な例だ。構築的なメロディと開放感のあるアンサンブルは、ジャズの即興性を保ちながら、ロック以降のリスナーにも直感的に届く。同様に、チック・コリア率いるリターン・トゥ・フォーエヴァーが発表した「Spain」では、クラシックやラテンの要素が高度な演奏技術と結びつき、フュージョンが知的でありながら高揚感を持つ音楽であることが示された。
さらに決定的だったのが、ハービー・ハンコックの「Chameleon」だ。シンセベースが生み出すグルーヴは、もはやジャズクラブの文脈を超え、身体を揺らすファンクとして機能していた。この瞬間、フュージョンは“聴く音楽”から“踊れる音楽”へと踏み出したのである。
名付けられたのは音楽ではなく「状態」だった
1970年代初頭、ロックは巨大な産業となり、ジャズは商業的な求心力を失いつつあった。そのなかで登場した、ジャズの演奏技術とロックのビートを併せ持つ音楽は、業界にとって極めて魅力的だった。
「ジャズ・ロック」や「ジャズ・ファンク」という呼び方も存在したが、それらは音楽性を限定しすぎる。「フュージョン」という言葉は、その曖昧さゆえに、あらゆる混交を受け入れることができた。つまり、フュージョンとは特定の音楽様式を指す言葉というよりも、「ジャンルが溶け合っている状態」そのものを示す言葉だったのだ。
この呼び名に対し、多くのミュージシャンが違和感を覚えていたことも見逃せない。彼らは新しいジャンルを作ろうとしたわけではなく、ただ自分たちが生きている時代の音を、ジャズの感覚で鳴らしたにすぎなかった。
日本で完成した「様式としてのフュージョン」
興味深いのは、フュージョンが日本で極めて明確なジャンルとして定着した点だ。1970年代後半から80年代にかけて、日本ではフュージョンが洗練された都会的音楽として受容されていく。
カシオペアの「ASAYAKE」に聴かれる明快なメロディと爽快感、T-SQUAREの「Truth」が持つ疾走感と精密さ。これらの楽曲は、フュージョンを「高度でクリーンな音楽」としてイメージ付けた。スタジオ・ミュージシャン文化やテレビ、CMとの親和性も高く、日本においてフュージョンは反逆ではなく、成熟と技術の象徴となったのである。
フュージョンとは、名付けられてしまった革命だった
結局のところ、フュージョンに明確な言い出しっぺはいない。マイルス・デイヴィスが境界を壊し、次世代のミュージシャンたちが音楽として形にし、レコード会社とリスナーがその状態に名前を与えた。その総体として、フュージョンは生まれた。
それは誰かの思想ではなく、時代が生み出した必然だった。そして皮肉なことに、「融合」を意味するその言葉自身が、ジャズと商業、芸術と市場が溶け合った結果でもあった。だからこそフュージョンは、今もなお評価が揺れ続け、繰り返し語り直される。その不安定さこそが、フュージョンという音楽の本質なのかもしれない。

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。