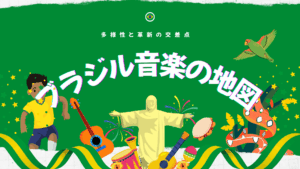ブラジルの音楽は、ただのジャンルやリズムの集まりではない。それは広大な国土に根を張る無数の文化の交差点であり、歴史的な重層性と現代的な革新が常に交錯しているダイナミックな音の海だ。本シリーズでは、サンバの起源から現代のクラブシーンに至るまで、ブラジル音楽の成り立ちとその豊かな多様性を深く掘り下げ、21世紀の音楽シーンにおける新しい潮流を追いかける。
本コラムを通じて、伝統的なサウンドの中にひそむ革新や、地域ごとのユニークな音の魅力に触れ、ブラジル音楽が持つ無限の可能性を再確認できるだろう。サンバの叙情的な情熱、ボサノヴァの静けさ、アフロ・ブラジルの鼓動、そして電子音楽との融合 ── それらが織りなすメロディとリズムは、世界中のリスナーに強い影響を与え続けている。
この8回のコラムを通じて、ブラジル音楽がどのように地域性と世界性を交わらせ、時代を越えて進化してきたのかを紐解いていく。音楽というアートフォームを超え、ブラジル音楽は文化、政治、アイデンティティを語る重要なメディアであることを、改めて感じさせられるに違いない。
さあ、ブラジル音楽の世界に再び足を踏み入れ、その無限の魅力を心ゆくまで味わってほしい。
サンバ ── この二音節の響きほど、ブラジルという国のイメージを端的に象徴する言葉は他にないかもしれない。リズミカルな打楽器、陽気なステップ、華やかなカーニバル……確かにそれらはサンバの一面である。しかし、サンバは単なる「楽しい音楽」ではない。その深層には、移動と融合、抑圧と解放、宗教と日常というブラジル社会の縮図が刻み込まれている。
サンバのルーツ ── バイーアの黒人宗教文化
サンバの源流は、ブラジル北東部の州・バイーアにある。この地は奴隷貿易の主要な玄関口であり、アフリカ由来の文化が最も色濃く残る地域である。サンバの語源も「semba(セムバ)」というアフリカの踊りや儀式に由来するという説が有力である。
特に注目すべきは、カンドンブレなどの宗教儀式で用いられる打楽器群とその複雑なポリリズムである。サンバのグルーヴ感は、このアフロ・ブラジル宗教のビートを基盤として生まれた。
やがて19世紀末から20世紀初頭にかけて、バイーア出身の黒人移民たちがリオ・デ・ジャネイロに移り住み、彼らの音楽や踊りが都市文化と交差することで、「都市型サンバ」へと姿を変えていく。
チャラスとテレイロ ── 音楽が生まれる場所
サンバが最初に都市の中で鳴り響いたのは、いわゆる「チャラス」と呼ばれる集会所である。なかでも最も有名なのが、チア・シアタ(Tia Ciata)というバイーア出身の女性が主催していた家だ。そこでは、カンドンブレの儀式の後に即興の打楽器セッションが開かれ、サンバの祖型が形成された。この時代のサンバは、今のような形式ではなく、より自由で即興性の高いものであった。宗教、日常、歓談、そして政治的なメッセージまでもが混ざり合いながら、一曲ごとにその場の空気が音楽になっていったのである。
サンバの「定型化」と初の録音作品
1917年、最初に「サンバ」として商業的に録音された曲が登場する。ドゥンガによる「Pelo Telefone」である。これは電話の使い方を茶化した風刺的な内容の曲であり、都市的なユーモアを取り入れたことで広く人気を博した。
この曲は、リオの黒人たちの間で口伝えにされていたリズムと旋律を、譜面に起こし、レコードにするという画期的な試みであった。ここにサンバは「大衆音楽」としての第一歩を踏み出す。
ノエル・ホーザとサンバの言葉
1930年代になると、サンバは急速に洗練され、都市の詩情を映すメディアへと変貌していく。中でも重要な役割を果たしたのがノエル・ホーザである。彼は白人中産階級の出身でありながら、労働者階級の黒人たちのサンバを愛し、その言葉と旋律に新しい文学的美学を持ち込んだ。彼の代表作「Com que roupa?」は、ユーモアと皮肉が交錯する名曲であり、当時の社会風俗を鋭く風刺している。
ノエル・ホーザの登場により、サンバは単なるリズムから「語る音楽」へと変貌し、より広い層に浸透していった。
エスコーラ・ジ・サンバ ── 祝祭としてのサンバ
1930年代後半、ブラジル政府はカーニバルを「国民の祝祭」として公式に後押しするようになる。これにより、サンバ・スクール(エスコーラ・ジ・サンバ)が続々と組織化され、より劇的で視覚的なサンバが登場する。
この時期の象徴的存在が、マンゲイラやポルテーラといった伝説的サンバ・スクールである。彼らは、色鮮やかな衣装と巨大な山車、緻密に構成された楽曲をもって、カーニバルという「国家的な舞台」で競演するようになる。
エスコーラ・ジ・サンバは、単なる音楽団体ではない。それは、地域コミュニティの誇りであり、社会的結束の核でもある。サンバはここで「見る音楽」「歩く音楽」「闘う音楽」として進化していく。
サンバの政治性と普遍性
一見すると華やかで陽気なサンバであるが、その裏には常に政治的な緊張が存在していた。黒人文化であるがゆえに、時に抑圧の対象となりながらも、サンバは民衆の「声」としてしたたかに生き延びてきた。
サンバが国家に取り込まれ、観光資源として活用される一方で、その原点には「語られなかった歴史」が今なお眠っている。だからこそ、サンバはいつでも新しく、そして抵抗の力を秘めた音楽として響き続ける。
次回予告:ボサノヴァという革命 ── 静けさの中の熱情
サンバがリズムの中に社会のうねりを孕んでいたとすれば、次に登場するボサノヴァは、その波を内面化し、都市のインテリ層の静謐な美学の中に音楽を変換していく。第3回では、ジョアン・ジルベルト、アントニオ・カルロス・ジョビン、ヴィニシウス・ヂ・モライスらによる「静かな革命」の歩みを追っていく。

Jiro Soundwave:ジャンルレス化が進む現代音楽シーンにあえて一石を投じる、異端の音楽ライター。ジャンルという「物差し」を手に、音の輪郭を描き直すことを信条とする。90年代レイヴと民族音楽に深い愛着を持ち、月に一度の中古レコード店巡礼を欠かさない。励ましのお便りは、どうぞ郵便で編集部まで──音と言葉をめぐる往復書簡を、今日も心待ちにしている。