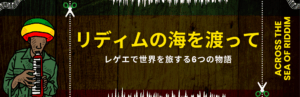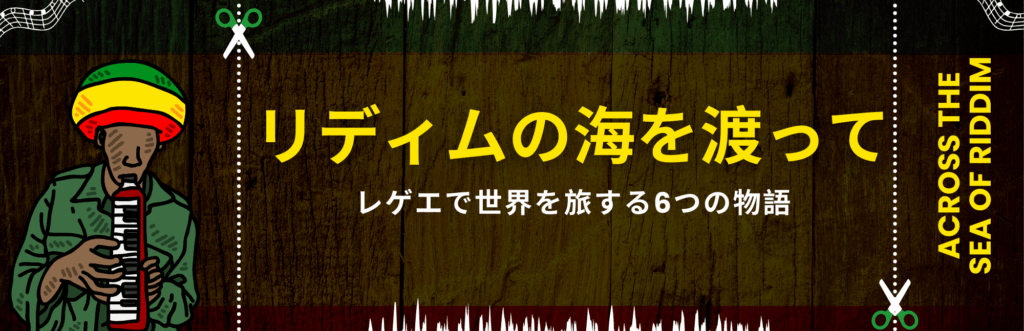
強く、優しく、揺らめくように響く音。
レゲエはジャマイカの土の匂いとともに生まれ、やがて海を渡り、世界中の心に根を下ろした──。
なぜこの音楽はこれほど人を惹きつけるのか?
どこまでが「レゲエ」で、どこからがその先なのか?
本連載では、誕生から進化、拡張、そして現在へと続くレゲエの物語を、全6回で丁寧にひもといていく。
音楽としての魅力はもちろん、その背後にある歴史、思想、コミュニティにまで迫る旅。
きっと読み終えたとき、レゲエという言葉が、音楽以上の意味を持つはずである。
「レゲエは死んだ」と、ある批評家は言った。だが、それは正確ではない。レゲエは死なず、枝分かれを繰り返しながら多様な進化を遂げたのである。
この第5回では、レゲエから派生したジャンルたち ── ダンスホール、ラヴァーズロック、レゲトン、グライム、そして現代ポップまで ── その進化の系譜を辿ってみたい。
ダンスホール ── マイクを握る者たちの時代
1970年代末、ジャマイカで新たな波が立ち上がる。それが「ダンスホール」である。レゲエの伝統的な“ルーツ感”や宗教的要素よりも、よりパーティ的・攻撃的・スピード感のあるスタイルが好まれるようになり、シンガーではなくDeeJay(MC)が中心となるカルチャーが形成されていく。
このジャンルを特徴づけるのは、以下のような要素である。
• よりアップテンポなリズム
• パトワ語によるスラング的歌詞
• 競争性の高いリリック(バトルやセクシャリティも含む)
• サウンドシステムでの「クラッシュ」文化の継承
代表的アーティスト:
• イエローマン
• シャバ・ランクス
• ビーニーマン
• ヴァイブス・カーテル
• スパイス(現代の女性スター)
2000年代にはエレクトロニック化が進み、いわゆる「デジタル・ダンスホール」へと移行。そのサウンドはヒップホップやEDM、さらにはK-POPにまで影響を与えている。
ラヴァーズロック ── もうひとつのレゲエの表情
激しいダンスホールとは対照的に、1970年代後半のイギリスでは、よりソフトでメロウなレゲエが登場する。それが「ラヴァーズロック」である。特にブラック・ブリティッシュの若者たち、特に女性に人気を博し、恋愛や内面の葛藤を歌うスタイルが生まれた。 レゲエが社会を告発する一方で、ラヴァーズロックは心の揺らぎや日常を掬い取る音楽として、多くの支持を集めた。
代表的アーティスト:
• ジャネット・ケイ
• キャロル・トンプソン
• マキシ・プリースト
• ビティ・マクリーン
このジャンルは、のちのR&BやUKソウル、さらには現代のLo-fiリバイバルの源流としても見直されている。
レゲトン ── カリブとラテンのハイブリッド
1990年代末、プエルトリコで育まれたのが「レゲトン(Reggaeton)」である。 その原型は、ジャマイカからパナマを経由して持ち込まれたレゲエ・エン・エスパニョール(スペイン語レゲエ)にあった。レゲトンの特徴は、いわゆる「デンボウ・リズム」と呼ばれる独特の反復パターン。 このビートは、90年代のジャマイカ産ダンスホールに起源を持つものであり、明確にレゲエの遺伝子を引き継いでいる。
代表的アーティスト:
• ダディー・ヤンキー(『Gasolina』)
• ドン・オマール
• J.バルヴィン
• バッド・バニー
いまや世界のポップ市場の中核を担うまでに成長したレゲトンは、レゲエがいかにしてグローバル・ポップの骨格になり得るかを証明した。
グライムとUKアフロビーツ ── レゲエの精神的な孫たち
イギリスでは、2000年代に登場した「グライム」というジャンルも、レゲエの系譜に連なっている。 ディージェイ文化、サウンドシステム、路上でのバトル精神など、レゲエ/ダンスホールから多くを継承している。
また近年では、UKアフロビーツやバッシュメントといったジャンルも、レゲエのビートやフロウ、リリック構造を下敷きにしている。つまり、現代UKアーバン・ミュージックの骨格は、ほとんどジャマイカ由来の文化DNAでできているのだ。
現代ポップへのレゲエ的侵食
現代のグローバル・ポップシーンを見渡すと、そこかしこにレゲエの影響が滲んでいる。
• リアーナ「Man Down」
• ドレイク「One Dance」「Controlla」
• ジャスティン・ビーバー「Sorry」「Let Me Love You」
• デュア・リパやドージャ・キャット、バーナ・ボーイなどもレゲエ風アプローチを多用
これらは、もはや“レゲエ風”ですらない。ポップのひとつの文法が、レゲエになっているという事実を示している。
まとめ:レゲエはジャンルではなく“変身装置”である
レゲエとは何か? それは、「ひとつのリズム」ではなく、「他ジャンルを変質させる発酵装置」だと言える。音楽ジャンルというものは、しばしば一定の“型”に閉じ込められがちだが、レゲエはむしろ、他ジャンルに侵食し、融合し、変化を促す力を持っていた。 それはまるで、菌類のようなネットワーク性を持つ音楽なのである。レゲエの進化は止まらない。変わり続けることで、その魂は永遠に燃え続けていくのである。
第6回(最終回)では、現代におけるレゲエの役割と、未来への展望について、“レゲエのいま”と“これから”を考察していきく。

Jiro Soundwave:ジャンルレス化が進む現代音楽シーンにあえて一石を投じる、異端の音楽ライター。ジャンルという「物差し」を手に、音の輪郭を描き直すことを信条とする。90年代レイヴと民族音楽に深い愛着を持ち、月に一度の中古レコード店巡礼を欠かさない。励ましのお便りは、どうぞ郵便で編集部まで──音と言葉をめぐる往復書簡を、今日も心待ちにしている。