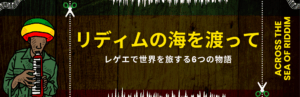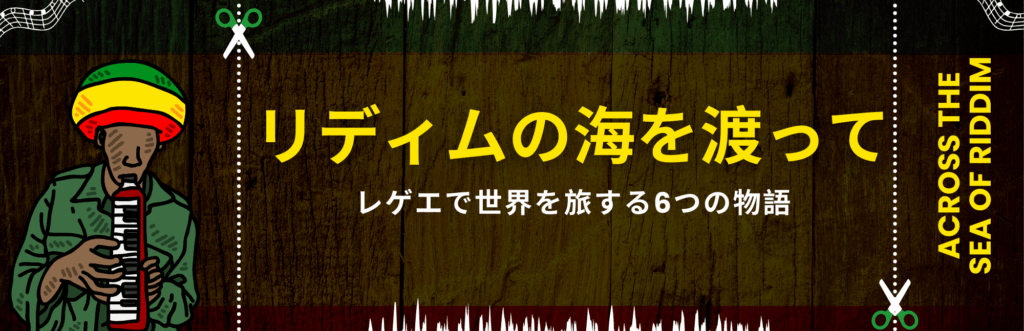
強く、優しく、揺らめくように響く音。
レゲエはジャマイカの土の匂いとともに生まれ、やがて海を渡り、世界中の心に根を下ろした──。
なぜこの音楽はこれほど人を惹きつけるのか?
どこまでが「レゲエ」で、どこからがその先なのか?
本連載では、誕生から進化、拡張、そして現在へと続くレゲエの物語を、全6回で丁寧にひもといていく。
音楽としての魅力はもちろん、その背後にある歴史、思想、コミュニティにまで迫る旅。
きっと読み終えたとき、レゲエという言葉が、音楽以上の意味を持つはずである。
レゲエはジャマイカで生まれた音楽である。しかし、その鼓動は国境を越え、さまざまな土地の人々と交わりながら新たな姿へと変貌してきた。 この第4回では、レゲエがいかにして“ディアスポラ(離散)としての音楽”となり、世界各地の文化や思想と響き合っていったのかを見ていく。
英国へ ── レゲエの“第二の母国”
レゲエの最初のディアスポラは、1950年代以降、イギリスへの移民たちによって起こされた。いわゆる「ウィンドラッシュ世代」と呼ばれるジャマイカ系移民たちは、故郷の音楽とともにロンドン、バーミンガム、ブリストルなどの都市に根を下ろしていった。
イギリスでは、ローカルなサウンドシステム・カルチャーが花開き、街角でのダンス、海賊ラジオ、インディペンデントなレコード・プレスが盛んに行われた。 レゲエは単なる音楽にとどまらず、移民の誇りであり、政治的な声であり、アイデンティティの象徴となったのである。
代表的アーティスト:
• スティール・パルス
• アスワド
• リントン・クウェシ・ジョンソン(詩とレゲエの融合)
とくにリントン・クウェシ・ジョンソンは、レゲエのリズムに乗せて社会的不正義を糾弾する“詩の戦士”として知られ、ダブ・ポエトリーというジャンルを確立した。
アフリカとレゲエ ── “帰還”の音楽として
レゲエが“帰還”したもうひとつの重要な場所が、アフリカ大陸である。 特にエチオピアやナイジェリア、セネガルでは、ボブ・マーリーをはじめとしたラスタファリアンの思想が共鳴を呼び、反植民地主義やパン・アフリカニズムのシンボルとしてレゲエは受け入れられた。
西アフリカ諸国では、1970年代から独自のレゲエバンドが台頭し、伝統音楽と融合したアフロ・レゲエが生まれた。現在もナイジェリアのマジェック・ファシェックやコートジボワールのティケン・ジャー・ファコリーなどが国際的に評価されている。アフリカにおいてレゲエは、「失われたルーツを取り戻す音楽」として機能した。つまり、レゲエは“音楽の大三角貿易”の逆回路をたどる媒体となったのである。
日本のレゲエ ── 翻訳と土着化の試み
意外かもしれないが、日本もまたレゲエの影響を色濃く受けた国のひとつである。1970年代末にジャマイカから初来日したミュージシャンのライブをきっかけに、徐々に認知が広がっていった。
1980年代には、ランキン・タクシーやスティッキー・フィンガーズなどによってジャパニーズ・レゲエが育まれ、90年代には湘南乃風やMIGHTY CROWNといったアーティスト/サウンドシステムが台頭。 特にMIGHTY CROWNは、ジャマイカのサウンドクラッシュで世界一に輝くなど、日本がレゲエの本場と対等に渡り合う存在であることを示した。
日本のレゲエは、原語であるパトワ語の響きを保ちつつ、日本語という言語を通して“翻訳”され、ユニークな形で土着化していった。そして現在も、都市と田舎、音楽と社会運動の交差点で独自の発展を遂げている。
世界各地のレゲエ・フォーム
世界には多種多様なローカル・レゲエが存在する。
• ドイツ/フランス: ラスタファリ文化への強い関心からレゲエフェスが活発。ジェントルマンやDub Inc.などが活躍。
• ブラジル: サンバと融合した「レゲエ・デ・サルヴァドール」。
• ニュージーランド: マオリ文化と結びついた「コンシャス・レゲエ」が人気。
• カナダ: トロントやモントリオールでカリブ移民の手により発展。
それぞれの土地で、レゲエは社会問題・人種問題・アイデンティティの問いとリンクしながら、ただの“輸入音楽”ではなく、その土地の文脈に根差した“在地化されたレゲエ”へと姿を変えていった。
レゲエの越境性=スピリチュアルな“通訳者”
レゲエはなぜ、これほどまでに多様な土地で受け入れられたのか。その鍵は、おそらくレゲエの根底にある「抵抗と癒し」という両義性にある。
レゲエは、時に社会体制への異議申し立てを行い、時に心の痛みを癒やす役割を果たす。そのメッセージは特定の国や言語を超え、世界中の“少数者”の声と結びつく。つまり、レゲエとは「声なき声のための音楽」であり、“国境なきスピリチュアルな通訳者”として機能するのである。
まとめ:レゲエが映し出す世界の“心の地図”
レゲエが歩んできたディアスポラの道は、単なる音楽の普及史ではない。 それは、移民の歴史、抑圧からの解放の願い、アイデンティティの模索といった、人類の普遍的なストーリーを映し出している。レゲエはもはやジャマイカの音楽ではない。それは、世界の多様な痛みと希望を響かせる“声のフォーマット”となったのである。
次回・第5回は、レゲエから派生した多様なスタイルとその拡張系 ── ダンスホール、ラヴァーズロック、レゲトン、そして現代ポップまでの進化の系譜を追っていく。

Jiro Soundwave:ジャンルレス化が進む現代音楽シーンにあえて一石を投じる、異端の音楽ライター。ジャンルという「物差し」を手に、音の輪郭を描き直すことを信条とする。90年代レイヴと民族音楽に深い愛着を持ち、月に一度の中古レコード店巡礼を欠かさない。励ましのお便りは、どうぞ郵便で編集部まで──音と言葉をめぐる往復書簡を、今日も心待ちにしている。