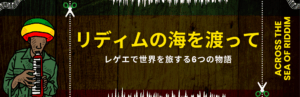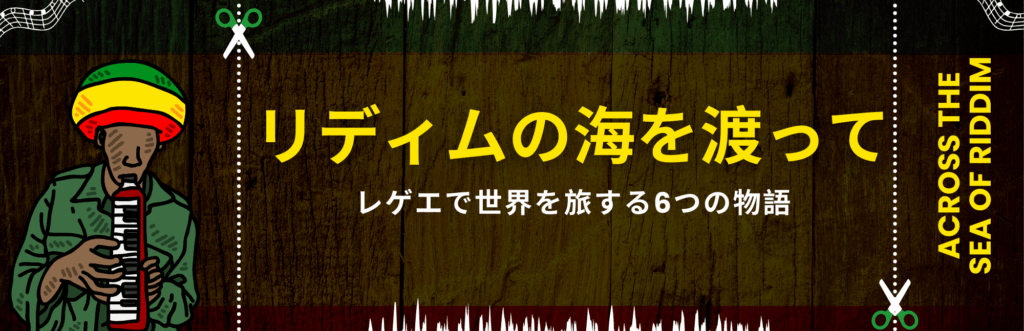
強く、優しく、揺らめくように響く音。
レゲエはジャマイカの土の匂いとともに生まれ、やがて海を渡り、世界中の心に根を下ろした──。
なぜこの音楽はこれほど人を惹きつけるのか?
どこまでが「レゲエ」で、どこからがその先なのか?
本連載では、誕生から進化、拡張、そして現在へと続くレゲエの物語を、全6回で丁寧にひもといていく。
音楽としての魅力はもちろん、その背後にある歴史、思想、コミュニティにまで迫る旅。
きっと読み終えたとき、レゲエという言葉が、音楽以上の意味を持つはずである。
1960年代後半、ジャマイカの街角では、かつてない音楽が鳴り響いていた。それはスカやロックステディといった既存のジャンルでは括れない、独特のグルーヴをまとっていた。ゆっくりと重く、しかし深く揺れるようなリズム。そして、メッセージ性を帯びた言葉。それがレゲエである。今回は、レゲエという名前がいかにして誕生し、音楽的にどのような進化を遂げたのかをひもといていきたい。
「レゲエ」という言葉の語源
レゲエという語の起源には諸説ある。一説には「ストリートでの喧騒」や「ぼろ服」を意味するジャマイカ・パトワの「rege-rege」から来たとも言われている。つまり、初期のレゲエは「社会の底辺」から発せられる声であり、その粗削りさと生々しさこそが特徴だったのだ。
この新たなジャンルを最初に明確に示したのが、トゥーツ・アンド・ザ・メイタルズの1968年の楽曲「Do the Reggay」である。この曲では「Reggay」というスペルが使われており、ジャンルとしての“命名”が初めて公に行われた瞬間とされている。
ワン・ドロップ・ビートの衝撃
レゲエを語るうえで外せないのが、「ワン・ドロップ(One Drop)」と呼ばれる独特のリズム構造である。このビートでは、通常ドラムのバス(キック)が鳴るべき“第一拍”を空白にし、代わりに三拍目に強いアクセントを置く。これによって生まれる「沈むようなビート感」が、レゲエのグルーヴを支えている。
このビートを形にしたのが、伝説的なドラマー、カールトン・バレットである。彼はボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズのリズムの要として、ワン・ドロップを確立した。 このタイム感覚は、ロックステディ時代のアップライトなリズムから一転し、「内省」と「反抗」を含んだ深い音楽性をもたらした。
スタジオ・ワンとブラック・アーク ── 2つの震源地
レゲエ誕生において重要な役割を果たしたのが、ジャマイカの二大レーベルである「スタジオ・ワン(Studio One)」と「ブラック・アーク(Black Ark)」である。
スタジオ・ワン は、コクソン・ドッドが主宰する、いわばジャマイカ音楽の“モータウン”的存在だ。ここでは、ボブ・マーリー、ヘプトーンズ、フレディ・マクレガー などの多くのアーティストが育ち、レゲエのフォーマットが築かれていった。
一方、ブラック・アークは、奇才リー・スクラッチ・ペリーの実験室とも言うべきスタジオである。彼はリバーブ、エコー、テープ逆回転などを駆使し、より幻覚的で精神的な音響世界を創出。後にダブへと繋がる“音の魔術”は、レゲエに革命的な奥行きをもたらした。
歌詞の変化 ── “Love”から“Message”へ
ロックステディの時代、歌詞は主に恋愛や失恋といった感情表現が中心であった。しかしレゲエが成立すると、歌詞のテーマは急激に社会的・政治的色彩を帯び始める。
例えば、アビシニアンズ の「Satta Massagana」では、エチオピア語を取り入れながらラスタファリズムへの信仰を前面に出した。また、バーニング・スピアの「Marcus Garvey」では、実在した黒人解放運動家の思想を讃えた。このようにレゲエは、「踊るための音楽」であると同時に、「考えるための音楽」でもあった。
ラスタファリズムとの接続
レゲエがただの音楽ジャンルではなく、「精神運動」としても機能したのは、ラスタファリズムとの結びつきによるところが大きい。ラスタとは、1930年代にジャマイカで生まれた宗教的・政治的思想であり、エチオピア皇帝ハイレ・セラシエを“救世主”とする黒人中心主義的な信仰である。
レゲエのアーティストたちはドレッドロックスを身につけ、マリファナ(“ハーブ”)を儀式的に用い、バビロン(抑圧的な西洋社会)への反抗を音楽に込めた。レゲエは、スピーカーから流れる「祈り」でもあったのだ。
“ローカル”が“グローバル”へ ── 世界に向けて響き出すレゲエ
1970年代初頭、ボブ・マーリーの存在によって、レゲエは世界の舞台に踊り出る。彼の楽曲「Get Up, Stand Up」「No Woman, No Cry」「Redemption Song」などは、レゲエの枠を超えて、世界中の人々に“抵抗と希望”を届けた。 ただし、ボブ・マーリーだけが特別だったわけではない。その背後には、ピーター・トッシュやジミー・クリフ、グレゴリー・アイザックス、カルチャー など、多くの実力派たちがいた。
そして一方で、レゲエはイギリスやアメリカの黒人コミュニティへと渡り、UKレゲエやラヴァーズ・ロック、さらにはヒップホップやダブステップといった新たな音楽の源流となっていく。ローカルで育まれたリズムは、やがてグローバルなうねりへと変貌を遂げるのである。
まとめ:レゲエは“メッセージの音楽”である
レゲエとは単なるジャンル名ではない。それはリズム構造の革新であり、社会に向けた抗議であり、信仰の叫びであり、抑圧へのレジスタンスなのである。 音のゆらぎの背後には、ジャマイカという国の矛盾と希望とが詰まっている。だからこそ、レゲエは今もなお世界中で「聴かれ」「読まれ」「感じられ」ているのだ。
次回・第3回では、レゲエの発展から生まれた“裏の主役” ── ダブという音響革命について掘り下げていく予定である。

Jiro Soundwave:ジャンルレス化が進む音楽シーンにあえて抗い、ジャンルという「物差し」で音を捉え直す音楽ライター。90年代レイヴと民族音楽をこよなく愛し、月に一度は中古レコード店を巡礼。励ましのお便りは郵便で編集部まで