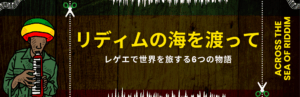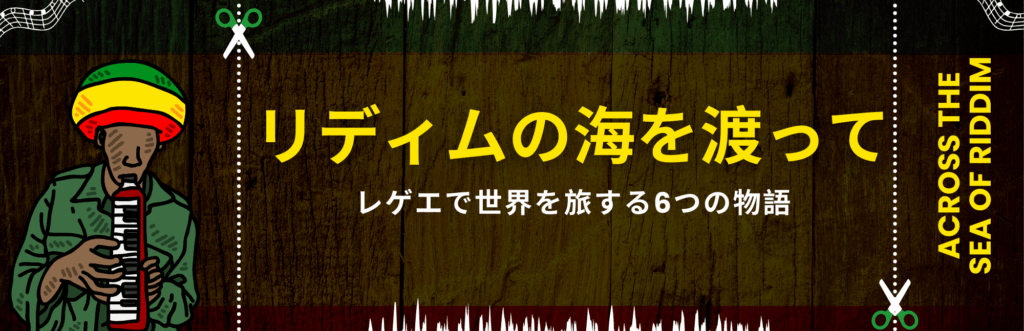
強く、優しく、揺らめくように響く音。
レゲエはジャマイカの土の匂いとともに生まれ、やがて海を渡り、世界中の心に根を下ろした──。
なぜこの音楽はこれほど人を惹きつけるのか?
どこまでが「レゲエ」で、どこからがその先なのか?
本連載では、誕生から進化、拡張、そして現在へと続くレゲエの物語を、全6回で丁寧にひもといていく。
音楽としての魅力はもちろん、その背後にある歴史、思想、コミュニティにまで迫る旅。
きっと読み終えたとき、レゲエという言葉が、音楽以上の意味を持つはずである。
「レゲエ」と聞いて、真っ先にボブ・マーリーの顔が浮かぶ人は少なくないだろう。確かに彼はこの音楽を世界的に知らしめた偉大な存在だが、レゲエとは、突如として現れた革新ではない。それは、ジャマイカという島国の歴史・風土・社会運動が積み重なった果てに生まれた、ある種の“結晶”なのである。本稿では、その誕生に至るまでの背景 ── つまり「レゲエ以前」について見ていきたい。
ジャマイカ音楽の始まり ──「メント」とは何か?
ジャマイカにおける大衆音楽の最初の形態としてしばしば語られるのが「メント(Mento)」である。19世紀末から20世紀初頭にかけて広まったこの音楽は、アフリカ系カリブ人の伝統的リズムとヨーロッパ音楽の構造が交差した民衆のフォークソングだ。
メントは、バンジョーやアコーディオン、ラムスキン・ドラム、さらには“ルンバボックス”と呼ばれる低音楽器などによって演奏される。歌詞はユーモラスかつ皮肉が効いており、植民地支配や社会の矛盾を風刺するものも多かった。レゲエ特有の“裏打ち”リズムこそまだないが、すでにジャマイカ音楽の根底に「語りと踊りと抵抗」が存在していたことを、メントは証明している。
スカの登場 ── ジャマイカが独立した年に
1962年、ジャマイカがイギリスから独立を果たした年、新たな音楽が街にあふれ出した。それが「スカ(Ska)」である。スカは、アメリカ南部から流入してきたR&Bやジャズに影響を受けながらも、ジャマイカ独自のリズム感と精神を宿していた。特徴的なのは、ギターやピアノが打つ“裏拍”である。表拍を鳴らすアメリカ音楽に対して、スカは敢えてその逆を行った。これは単なるリズムの工夫ではなく、「自分たちの音を見つけた」喜びの表現でもあったのだ。
この時代、音楽の担い手は主に“サウンドシステム”と呼ばれる移動式のDJ部隊だった。キングストンのスラム街では、巨大なスピーカーを積んだトラックが街角に現れ、地元のプロデューサーたちが独自のレコードをかけては民衆を踊らせた。サウンドシステムは単なる音楽の再生装置ではなく、貧困層にとってのコミュニティの核であり、時に政治的なメッセージを放つメディアでもあった。
代表的なスカ・アーティストには、ザ・スカタライツやドン・ドラモンド、デリック・モーガンなどが挙げられる。ジャズの即興性とカリブのダンスビートを掛け合わせた彼らの音楽は、祝祭的でありながらも、どこか苦みを含んだ現実へのまなざしを持っていた。
ロックステディ ── 哀しみを帯びた夜明け前
1966年頃から、スカはそのテンポを落とし、「ロックステディ(Rocksteady)」という新しいスタイルへと変貌していく。ロックステディは、よりミドルテンポで、メロウな旋律を特徴とする。背景には、ジャマイカの社会情勢の悪化 ── 暴力と貧困、政治的混乱の激化 ── があったと言われる。テンポの減速は、そのまま時代の“空気の重さ”を反映していたのだ。
ロックステディでは、アルトン・エリスやパラゴンズ、ケン・ブースなどが人気を博した。彼らの歌声はどこか哀愁を帯び、失恋や不安、社会への不満を率直に歌い上げた。その中には、後のレゲエで中心となる「ラスタファリズム」的な霊性や反抗の萌芽も感じられる。
音楽的には、ロックステディ期にベースラインの重要性が格段に増している点も注目すべきだ。リズムの中心がドラムからベースに移り、これが後の「ワン・ドロップ」ビート ── すなわちレゲエの代名詞となる重いビート感 ── へと繋がっていく。
レゲエの“地層”としての意味
以上見てきたように、レゲエは空から降ってきた音楽ではない。それはメントという民衆の言葉から始まり、スカという独立の高揚感を経て、ロックステディという社会的憂鬱をくぐり抜けて生まれたのだ。つまり、レゲエとは「歴史のリズム」なのである。
また、この流れの中で重要なのは、音楽がつねに「メッセージを持っていた」という点である。ジャマイカでは、音楽とはただの娯楽ではなく、“声なき人々のスピーカー”であった。社会の矛盾、宗教的信念、愛と絶望 ── それらすべてが、リズムに乗せられ街中に響いていたのである。
このような土壌があったからこそ、次回取り上げる「レゲエ」という新たな音楽ジャンルは、単なるリズムの革新にとどまらず、「精神の運動」として誕生することになる。
次回は、第2回「レゲエ誕生──そのビートはどこから来たのか」。
レゲエという言葉が生まれた背景、そして“ワン・ドロップ”という革新的リズムについて深掘りしていく。

Jiro Soundwave:ジャンルレス化が進む音楽シーンにあえて抗い、ジャンルという「物差し」で音を捉え直す音楽ライター。90年代レイヴと民族音楽をこよなく愛し、月に一度は中古レコード店を巡礼。励ましのお便りは郵便で編集部まで