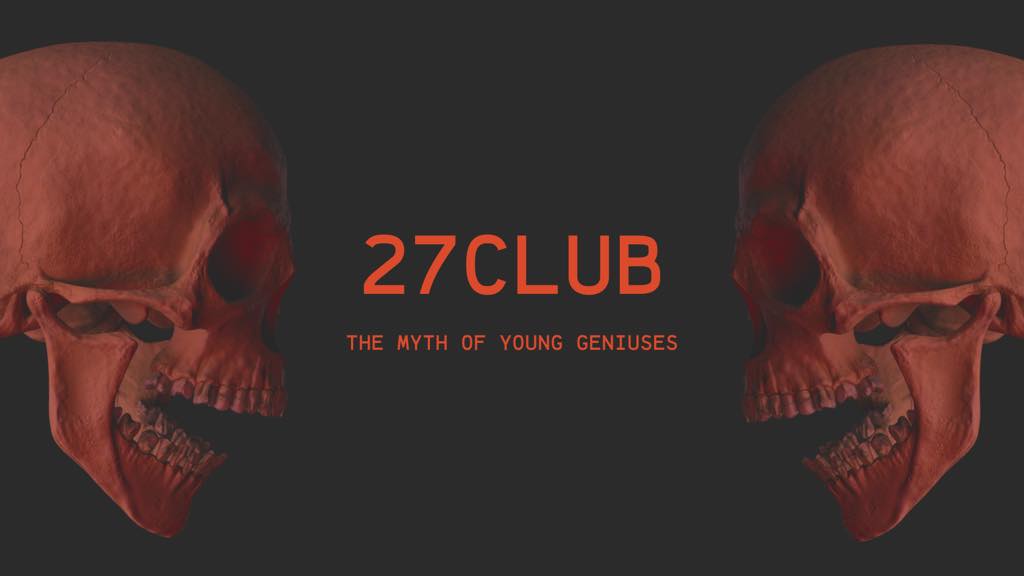
1960年代末から70年代初頭にかけて、ロック史は最も熱を帯びた時期を迎えていた。戦後のベビーブーマー世代が青年期に入り、反戦運動、公民権運動、フリーセックス、ドラッグカルチャーなどが一気に噴出した時代である。音楽はその動乱の只中で「若者の反逆」の象徴となり、ロック・ミュージシャンたちはその旗手として祭り上げられた。だがその熱狂の裏側で、若き才能たちは次々と27歳という年齢で命を落としていくこととなる。後に「27クラブ」と呼ばれる神話の原点である。
ブライアン・ジョーンズ──ローリング・ストーンズの創設者の死
最初に「27の呪い」を強烈に印象づけたのは、ローリング・ストーンズの創設メンバーであるブライアン・ジョーンズである。彼はストーンズ結成時の中心人物であり、ブルースを基盤としたサウンドを築き上げた。しかし1969年、グループ内での孤立と薬物問題によりバンドを追放され、そのわずか一か月後、自宅のプールで変死体として発見された。享年27歳。その死は「ロックは危険である」というイメージを決定づけた。
彼が導入したシタールの響きは、当時のロックに異国情緒と実験性を持ち込み、サイケデリック時代の幕開けを告げた。
ジミ・ヘンドリックス──ギターを燃やした男
1970年9月、ジミ・ヘンドリックスがロンドンで急逝する。公式の死因は睡眠薬とアルコールの併用による窒息死とされるが、詳細はいまだに謎が残されている。享年27歳。彼のギターはブルースとロックの伝統を引き継ぎながら、爆発的な音響実験によって「電気の魔術師」と呼ばれるほどの革新をもたらした。
そのイントロの轟音は、60年代末のロックが到達した実験精神を象徴するものであり、彼の死によって「天才は早逝する」という神話が強まった。
ジャニス・ジョプリン──魂を焼き尽くした歌声
ヘンドリックスの死からわずか3週間後、ジャニス・ジョプリンがヘロインの過剰摂取によって倒れ、27歳で生涯を閉じる。彼女は白人女性でありながら黒人ブルースの魂を体現し、圧倒的なシャウトで聴衆を魅了した。その存在は、ロックにおける「女性の解放」を象徴するものでもあった。
燃え尽きるような歌唱は、まさに命を削って表現するというロックの美学を体現している。
ジム・モリソン──詩人としての死
翌1971年、ザ・ドアーズのフロントマンであったジム・モリソンがパリのアパートで亡くなる。死因は心不全とされるが、薬物との関係も指摘され続けている。享年27歳。彼はロック・スターであると同時に詩人でもあり、言葉と音楽を結びつけた表現者であった。
その曲の妖しいオルガンとモリソンの艶めいた声は、ロックが単なる娯楽を超え、意識の変容を誘う芸術となり得ることを示した。
「27クラブ」という言葉の萌芽
こうして1970年から71年にかけて、ヘンドリックス、ジョプリン、モリソンというロックの象徴が立て続けに27歳で死んだ事実は、人々に強烈な印象を残した。加えて、その直前にブライアン・ジョーンズが同じく27歳で亡くなっていたこともあり、「27歳はロック・スターにとって呪われた年齢だ」という言説が広まったのである。実際には偶然の連鎖にすぎないとも言えるが、神話は事実よりも強力である。若きカリスマたちが27歳という節目で命を落とすことは、ロックを一層「危険で神秘的な文化」として人々の記憶に刻み込んだ。
27という数字の象徴性
なぜ「27」という年齢が特別視されるのか。心理学的には、20代後半は「自己のアイデンティティが確立する時期」とされる。社会に出て数年を経て、自らのキャリアや人間関係を固め始める年齢である。だがロック・スターたちは、一般的なライフサイクルとはかけ離れた速度で名声を手にし、同時に強烈なストレスと孤独を抱え込む。彼らにとって27歳は、成功と破綻の境界線であったのかもしれない。
神話としての定着
ブライアン・ジョーンズ、ジミ・ヘンドリックス、ジャニス・ジョプリン、ジム・モリソン──この4人の死によって、27クラブの伝説は形成された。以後、この神話は繰り返し語られ、1990年代にはカート・コバーンの死によって再び息を吹き返すこととなる。その過程については次回詳しく論じるが、ここで重要なのは「27クラブ」が単なる偶然の集合体ではなく、ロック文化の中で「若くして燃え尽きる天才」の象徴として消費され、定着していったという事実である。
第1回では、27クラブの起源とされる1960~70年代初頭の出来事を振り返った。27という年齢が神話化された背景には、当時の社会的混乱と音楽文化の爆発がある。次回は1990年代、カート・コバーンによって再び光を当てられた「27歳の呪い」について考察する。

Jiro Soundwave:ジャンルレス化が進む現代音楽シーンにあえて一石を投じる、異端の音楽ライター。ジャンルという「物差し」を手に、音の輪郭を描き直すことを信条とする。90年代レイヴと民族音楽に深い愛着を持ち、月に一度の中古レコード店巡礼を欠かさない。励ましのお便りは、どうぞ郵便で編集部まで──音と言葉をめぐる往復書簡を、今日も心待ちにしている。








