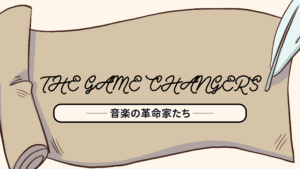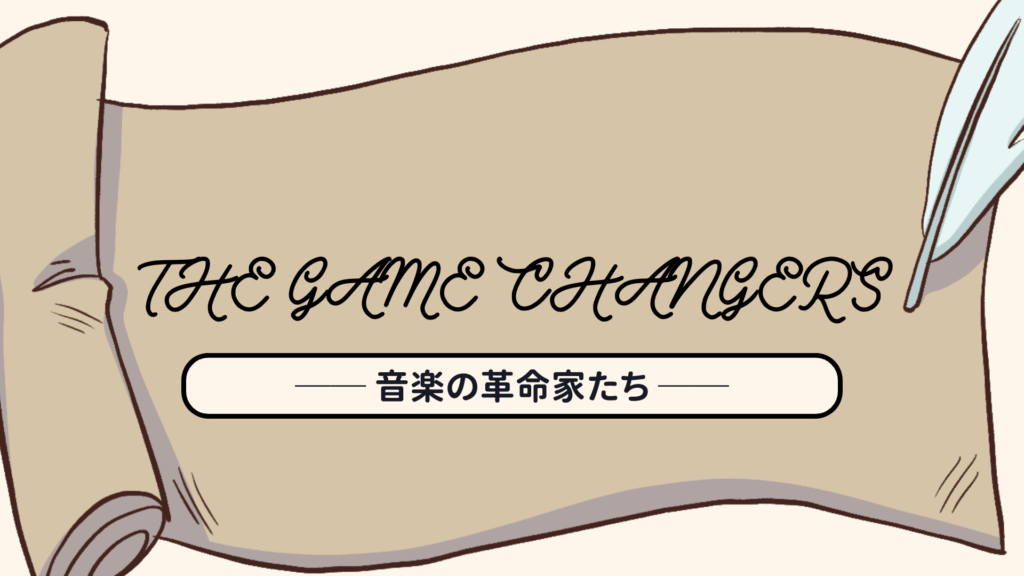
「エクスペリエンスの終わり」──ジミは”ヒーロー”に飽きていた
1969年6月。ジミはジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスの解散を発表する。ノエル・レディングとの確執、音楽的な方向性の違い、そして何よりも、”ジミ・ヘンドリックス”というイメージに縛られた自分に疲れていた。
「フラストレーションを解放するために曲を書く」「リードを弾くのは自分を表現するため。でも僕のリードの弾き方は生々しいんだ。それは自然に出てくるもの」とジミは1968年のインタビューで語っている。
そんな時期、ジミが出会ったのが黒人ドラマー、バディ・マイルスと、幼馴染でベーシストのビリー・コックスだった。
「Band of Gypsys」──黒人として、戦う音楽を
この新しいバンドで、ジミはこれまでとはまったく違う方向へと舵を切る。 ギター・ヒーローとしてではなく、黒人のひとりとして、現実のアメリカと向き合うための音楽を始めたのだ。
1969年末から1970年初頭にかけて、バンド・オブ・ジプシーズはフィルモア・イーストで伝説的なライブを行う。
特に衝撃的なのは《Machine Gun》。 ベトナム戦争をテーマにしたこの10分超の演奏は、ギターが銃声になり、フィードバックが爆撃音になり、空白が死者の静寂になる。 ここには、もはやショーマンシップはない。あるのは、黒い怒りと、祈りと、魂の叫びである。
この曲は、ヒップホップのパイオニアであるパブリック・エナミーやザ・ルーツなど、後世の”プロテスト・ミュージック”にも深く影響を与えた。
「ウッドストック」で見せた、”ギターによる国歌”
1969年8月、ジミはウッドストック・フェスティバルのトリを飾る。 だが、彼の登場は午前9時。観客はすでに半分以上帰っていた。
この場面で彼が奏でた《Star-Spangled Banner(アメリカ国歌)》は、歪みとフィードバックに満ちた”音によるデモ”だったと言える。
この演奏は今なお賛否を呼ぶ。ある人は「国家への冒涜」と非難し、ある人は「ギターで描いた抗議」と絶賛した。
どちらにせよ、この演奏でジミは、ロックを”国家的芸術”へと変えた最初のアーティストとなったと言っていいだろう。
Electric Lady Studios、始動──しかし、もう彼の時間はなかった
1970年、ついに念願のスタジオ「Electric Lady Studios」が完成する。 ジミはこの空間を「音の実験室」にしようと考えていた。ミュージシャンが集い、ジャンルを越えた即興を交わす”エレクトリック・チャーチ”。
実際、この年にはマイルス・デイヴィスとの共演計画があり、相互に敬意を払う関係だった。1970年末に実現予定だったが、ジミの死により幻の共演となった。
ジミはこの時、ロックとジャズの”未来”を模索していたのではあるまいか。
そして、最後のツアーへ──”Cry of Love”ツアーと異国の死
1970年9月18日。ジミはロンドンのサマーカンド・ホテルで急死する。27歳。睡眠薬の過剰摂取による嘔吐物での窒息死だった。
彼の死を巡っては様々な憶測も生まれたが、検死結果は事故死とされている。
最後の音源《Angel》《Freedom》──静かで、内省的なジミ
ジミの死後に発表された《The Cry of Love》や《First Rays of the New Rising Sun》には、 それまでの爆発的サウンドとは違う、静謐で穏やかな旋律が並ぶ。
そこにあるのは、世界を変えようとした男が、ようやく見つけた自分の内なる光だったのかもしれない。

Jiro Soundwave:ジャンルレス化が進む現代音楽シーンにあえて一石を投じる、異端の音楽ライター。ジャンルという「物差し」を手に、音の輪郭を描き直すことを信条とする。90年代レイヴと民族音楽に深い愛着を持ち、月に一度の中古レコード店巡礼を欠かさない。励ましのお便りは、どうぞ郵便で編集部まで──音と言葉をめぐる往復書簡を、今日も心待ちにしている。