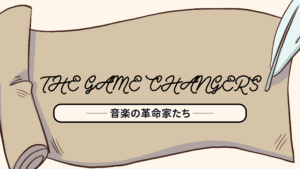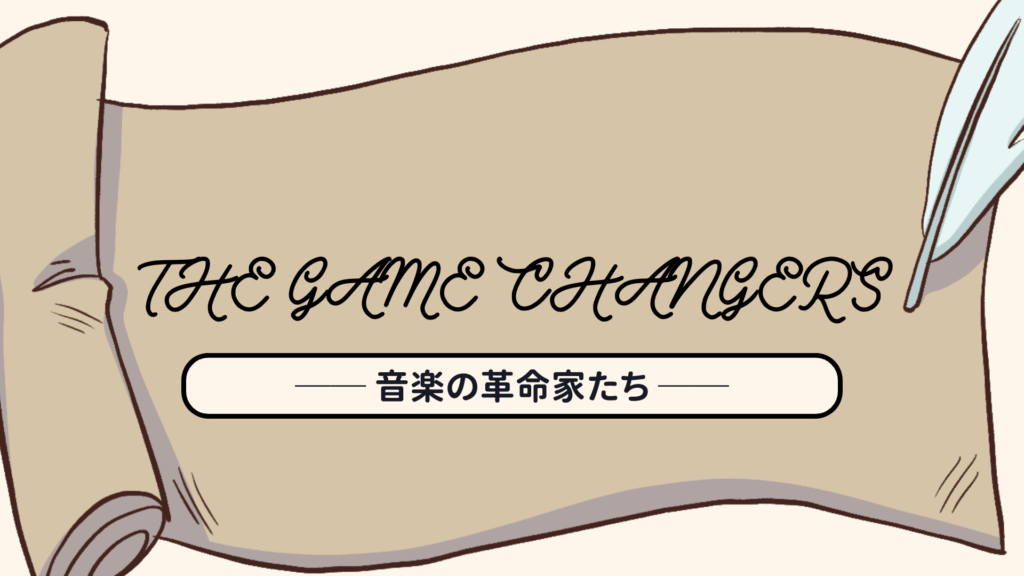
1968年。アメリカは混沌の渦中にあった。 ベトナム戦争の泥沼化、公民権運動の激化、キング牧師暗殺、ロバート・ケネディ暗殺──。若者たちの怒りと絶望は、音楽に牙を剥かせる。 その年、ジミ・ヘンドリックスは音の宇宙を描いた。アルバム《Electric Ladyland》。 それはただのロック作品ではない。ジミ自身の内なる声と、技術的執念と、時代の狂気が混ざり合ったサウンド・ラビリンスである。
制御不能のクリエイティビティ──制作現場は”戦場”だった
このアルバムの制作期間、ジミはまさに音楽のマッドサイエンティストと化していた。レコーディング・スタジオには夜な夜な仲間やミュージシャンが集まり、ドラッグとセッションが渦巻く混沌の空間が生まれていた。
プロデューサーのエディ・クレイマーは語る。 「ジミは明け方に現れて、ギターを抱えて”これ録ろう”と始める。誰も何の曲をやるのか知らない。だけど、それが良かった。」
ジミは、ミキシングの卓を操作し、音の反響や残響をミリ単位で追い込む異常な集中力を見せた。もはや”ギタリスト”ではなく、”サウンド・アーキテクト”だった。
《Voodoo Chile》──ブルースと宇宙の融合
《Voodoo Chile》は15分にも及ぶ大作。根っこにはデルタ・ブルースがありながら、そこに宇宙空間のようなエフェクトと、うねるようなインプロヴィゼーションが重なっていく。
この楽曲は1968年5月2日、ニューヨークのレコード・プラント・スタジオで録音された。参加しているのは、ジャズ・オルガン奏者のスティーヴ・ウィンウッド(トラフィック)とジェファーソン・エアプレインのジャック・キャサディ(ベース)、そしてエクスペリエンスのドラマー、ミッチ・ミッチェル。この豪華な”ジャム”は、ジミが”黒人ブルース”と”白人ロック”を結びつける架け橋になった証でもある。
《1983… (A Merman I Should Turn to Be)》──音の幻想文学
この曲はジミの中でも最も詩的かつ幻想的な作品の一つ。人間が海に還るというサイケデリック・SFのような物語が、海底を漂うようなディレイとコーラスに包まれて展開される。この列車は、もはやブルースの列車ではない。彼が作った音の宇宙船なのだ。
《All Along the Watchtower》──ディランを超えたカバー
ボブ・ディランの《見張塔からずっと》(All Along the Watchtower)を、ジミはまったく別の命を与えた。 重厚なリズムと多層的なギターのオーバーダブ、緊張感のある構成。ディラン本人もこのバージョンに敬意を表し、ライブでジミのアレンジを模倣したほどである。
この一曲だけで、”カバーは原曲を超えられない”という常識が覆った。
“黒い”ジミと、”白い”マーケットのねじれ
《Electric Ladyland》はアメリカで初の全米1位アルバムとなった。 だが、この快挙にもジミの内心は晴れなかった。
当時のレコード会社は、アルバム・ジャケットにジミの意志を無視して裸の白人女性たちの写真を使用した(UK盤)。ジミはこのジャケットを酷く嫌悪し、「これは俺とは何の関係もない」と激怒。「イギリスの人々がこのジャケットに反発するのも無理はない」とコメントした。
ここにも、ジミが黒人として白人主導の音楽業界に置かれた歪な立場がにじむ。
Electric Lady Studios──自分の”宇宙船”を持つという夢
『Electric Ladyland』の成功後、ジミは自分の音楽を完全にコントロールする場所を夢見るようになった。その夢が現実となったのは2年後の1970年。ニューヨーク・グリニッジ・ヴィレッジにElectric Lady Studiosが開設された。
自分の理想の音響設計、自由な時間、仲間とのセッション──。 ここでジミは、ようやく”レコード会社”や”白人プロデューサー”に縛られずに、本当の意味で”自由な音”を追求する環境を手に入れた。
だが、”自由”はすでに彼を蝕んでいた
スタジオ開設は1970年8月26日。ジミは翌日の8月末に最後のスタジオ録音「Slow Blues」をここで行った。そしてその僅か3週間後、ロンドンで帰らぬ人となった。
バンドメンバーとの確執、マネジメントとの摩擦、ドラッグの影──。アルバムは成功し、スタジオは完成した。 だが、ジミ・ヘンドリックスという宇宙船は、すでに軌道を外れ始めていた。

Jiro Soundwave:ジャンルレス化が進む現代音楽シーンにあえて一石を投じる、異端の音楽ライター。ジャンルという「物差し」を手に、音の輪郭を描き直すことを信条とする。90年代レイヴと民族音楽に深い愛着を持ち、月に一度の中古レコード店巡礼を欠かさない。励ましのお便りは、どうぞ郵便で編集部まで──音と言葉をめぐる往復書簡を、今日も心待ちにしている。