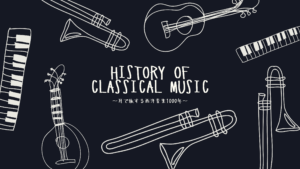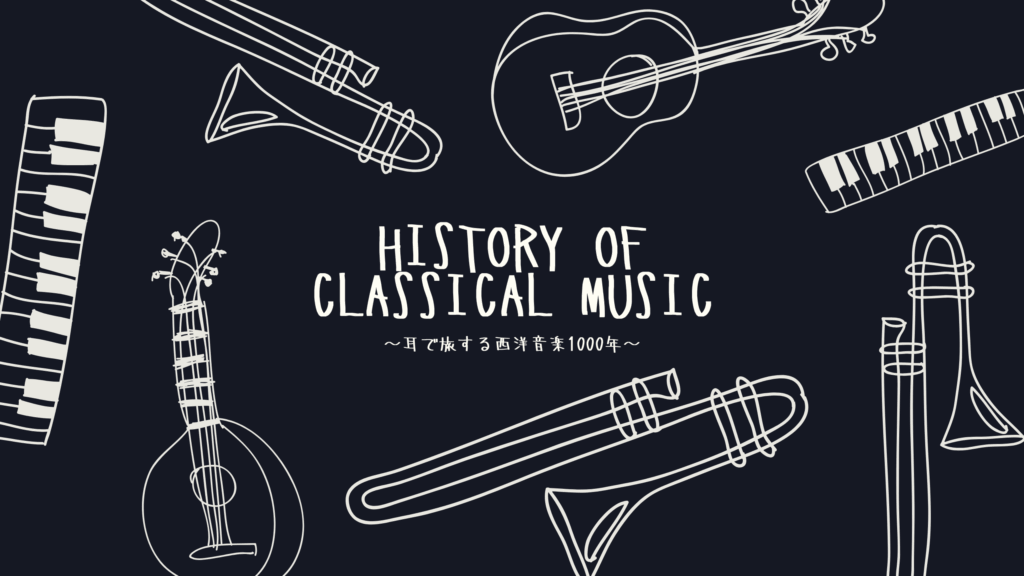
音楽は、どこから来て、どこへ向かうのか。
「クラシック音楽」と聞くと、あなたはどんなイメージを抱くだろうか。
堅苦しい、難しそう、あるいは昔の音楽 ── 。けれど、それはほんの一部に過ぎない。
クラシック音楽とは、9世紀の祈りの声から始まり、劇場、宮廷、戦場、そして映画館やスマートフォンの中へと受け継がれてきた、“人間の感情と思想のアーカイブ”である。そこには、ただ美しいだけではない、問いや葛藤、時代のうねりと個人の叫びが、確かに息づいている。
この全8回の連載では、中世から21世紀まで、クラシック音楽の歴史を大きく8つのフェーズに分けてたどる。バッハも、ベートーヴェンも、ジョン・ケージも、決して遠い存在ではない。彼らの音楽は、時代を超えて今も私たちの耳に届いている。
音楽は、いつも変わり続ける。
だからこそ、過去を知ることは、未来の音をもっと自由に聴くためのヒントになるはずだ。
クラシック音楽の1000年を、あなたの耳で旅してみよう。
「もう、ドレミファソラシドだけでは足りない。」
19世紀、ロマン派が感情の深みを極限まで掘り下げた結果、音楽はひとつの臨界点に達する。和声は極度に複雑化し、旋律は明瞭さを失い、「調性=音楽の中心」そのものが危機を迎える。
そして20世紀初頭、ついにいくつもの作曲家たちが“音楽の地図”を塗り替えはじめる。今までのルールに従わない、新しい響き、構造、思想を持った音楽の誕生である。
今回の主役は、ドビュッシー、ストラヴィンスキー、シェーンベルク。彼らはそれぞれ異なる方向から音楽を変えた。つまり、20世紀の音楽は「破壊」ではなく、「拡張」だったのである。
音の印象派 ── ドビュッシーの“耳で見る絵画”
クロード・ドビュッシー(1862–1918)は、フランス音楽に新しい風を吹き込んだ先駆者である。
彼の音楽は、従来の「和声進行」や「形式」に縛られず、色彩・空気感・一瞬の印象を音で描こうとするものだった。しばしば「印象派音楽」と呼ばれるが、これは絵画のモネやルノワールに倣った命名であり、彼自身はこの呼び方を好んではいなかった。
ドビュッシーの音楽では、旋律はぼんやりと霞み、リズムは流れるように揺れ、和声は従来の機能から解き放たれる。聴き手は感情ではなく“気配”を聴くことになるのだ。
リズムの革命 ── ストラヴィンスキーの原始的衝動
イーゴリ・ストラヴィンスキー(1882–1971)は、音楽の“野性”を呼び覚ました作曲家である。
彼の代表作《春の祭典》は、1913年にパリで初演され、激しいリズム、異常な和声、不協和音の炸裂によって観客の大半を混乱と怒りに陥れた。実際、初演は大暴動に発展したという逸話も残っている。
この作品の革新性は、調性の破壊というよりも、音楽の「身体性」の再発見にある。踊るための音楽が、思考を超えて本能に訴えかける。ストラヴィンスキーはクラシック音楽を、“理性の芸術”から“生命のエネルギー”へと引き戻したのだ。
音楽の秩序をゼロから作り直す ── シェーンベルクと十二音技法
アルノルト・シェーンベルク(1874–1951)は、音楽理論そのものを再設計した作曲家である。
彼は、ロマン派後期の“和声の崩壊”を徹底的に突き詰め、あらゆる音を“平等”に扱う「十二音技法」を考案した。これは、1オクターブの12音すべてを一度ずつ使う「音列」を基に作曲するという方法である。従来の「ドが中心」だった音楽は消え、音同士が“平等”に並ぶ世界が生まれた。
この方法論は、バッハやベートーヴェンが築いた「調性の文化」を根本から否定し、音楽の価値観を刷新した。
聴く側の耳も変わりはじめる
20世紀の音楽は、単なる“難解さ”の追求ではなかった。それは、聴く側の耳を再構築する挑戦でもあった。
今まで「心地よい」とされてきた響きが否定され、「不協和音」や「無音」すらも音楽の一部として受け入れられるようになる。観客は、感情ではなく“構造”や“思想”を聴くようになり、音楽は哲学的な芸術へと近づいていった。
同時に、録音技術の発達やラジオの登場によって、音楽の享受の仕方も変化していく。音楽はホールで生演奏を聴くものから、家でスピーカーから流すものへと変化していったのだ。
調性なき時代の、静かな希望
すべてが解体されたように見えた20世紀音楽にも、実は“新しい美しさ”が潜んでいる。それは、「予測不能な構造」や「無意識との対話」、「沈黙の中の音」── つまり、私たちの聴き方そのものを更新する音楽である。
この流れはやがてジョン・ケージ、武満徹、スティーブ・ライヒなどへと続き、21世紀の音楽へとバトンをつないでいく。
まとめ:破壊と創造の20世紀
20世紀の音楽は、ある意味で“地図なき旅”であった。ドレミファソラシドという秩序を壊し、代わりに自らの耳と思想を羅針盤にして、新たな音楽の世界を切り拓いていった作曲家たち。
そこには、“調性”や“メロディ”という従来の価値観に縛られない、新しい感受性の可能性があった。私たちが今、日々の中で無意識に触れている音楽 ── 映画音楽、環境音楽、アンビエント、エクスペリメンタル ── それらすべてが、この時代の冒険の果実なのである。

Sera H.:時代を越える音楽案内人/都市と田舎、過去と未来、東洋と西洋。そのあわいにいることを好む音楽ライター。クラシック音楽を軸にしながら、フィールド録音やアーカイブ、ZINE制作など多様な文脈で活動を展開。書くときは、なるべく誰でもない存在になるよう心がけている。名義の“H”が何の頭文字かは、誰も知らない。