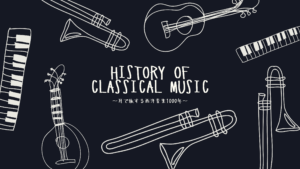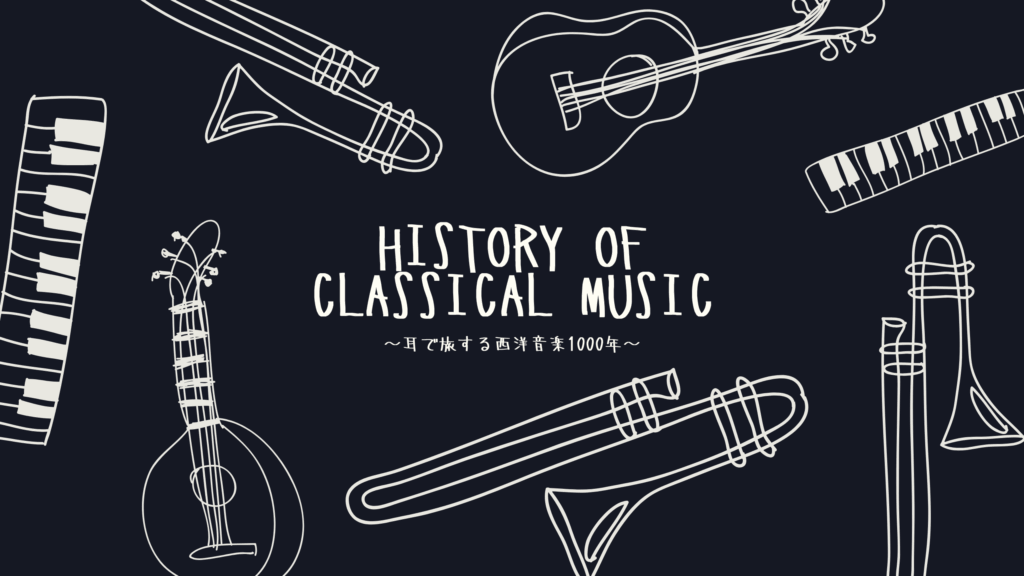
音楽は、どこから来て、どこへ向かうのか。
「クラシック音楽」と聞くと、あなたはどんなイメージを抱くだろうか。
堅苦しい、難しそう、あるいは昔の音楽 ── 。けれど、それはほんの一部に過ぎない。
クラシック音楽とは、9世紀の祈りの声から始まり、劇場、宮廷、戦場、そして映画館やスマートフォンの中へと受け継がれてきた、“人間の感情と思想のアーカイブ”である。そこには、ただ美しいだけではない、問いや葛藤、時代のうねりと個人の叫びが、確かに息づいている。
この全8回の連載では、中世から21世紀まで、クラシック音楽の歴史を大きく8つのフェーズに分けてたどる。バッハも、ベートーヴェンも、ジョン・ケージも、決して遠い存在ではない。彼らの音楽は、時代を超えて今も私たちの耳に届いている。
音楽は、いつも変わり続ける。
だからこそ、過去を知ることは、未来の音をもっと自由に聴くためのヒントになるはずだ。
クラシック音楽の1000年を、あなたの耳で旅してみよう。
火山のように噴き上がる激情。夜のように深く、そして夢のように儚い旋律。19世紀、音楽はついに“理性の器”を飛び出し、感情の爆発と個の表現へと突き進む。それがロマン派である。
古典派が築いた“均整と理性”の美学は、産業革命、ナショナリズム、個人主義の台頭とともに大きく揺らぎ始める。芸術は“全体のためのもの”から“個人の声”へ。音楽家は社会の職人ではなく、孤高の芸術家として自らの内面を叫ぶ存在へと変貌していった。
今回は19世紀ロマン派の世界を、ショパン、シューマン、リスト、ブラームスらの音楽とともに見ていく。音楽が「叫び」「夢」「国」「死」すらも描けるようになった革命の時代である。
ロマン派とは何だったのか?
“ロマン”という言葉には、多義的な意味がある。幻想、感情、個性、憧れ、夢 ──。それは理性の対極にある、人間の内なる衝動と世界への耽溺である。
ロマン派の作曲家たちは、音楽を「感情の記録」と捉えた。旋律は叫び、和声は揺れ動き、形式はしばしば解体されていった。音楽の長さも規模も、作曲家の内的宇宙に比例して膨張していく。この時代、音楽はもはや“背景”ではない。“物語”そのものである。
革命と孤独の詩人 ── ショパン
フレデリック・ショパン(1810–1849)は、ピアノ音楽の革命児である。ポーランド生まれ、パリで活躍しながらも、生涯を通して祖国への郷愁を抱き続けた作曲家だ。彼の音楽には、華やかさと深い内省、そして絶望の美しさが同居している。
彼はピアノという楽器に、感情のすべてを語らせた。小さな前奏曲の中に、人生の悲しみが凝縮される。その密度の高さは、短詩のようであり、夢の断片のようでもある。
「音楽の詩人」シューマンと、愛の断片
ロベルト・シューマン(1810–1856)は、文学と音楽の橋渡しをした詩人肌の作曲家である。ピアノの詩集ともいえる作品《子供の情景》や、恋人クララへの思いを綴った《幻想小曲集》など、彼の音楽は短く、しかし情感の詰まった断章のようだ。
また、彼は音楽評論家としても活動し、若きブラームスを見出した人物でもある。その思想の根底には、「音楽は内面を語るべきだ」という美学が貫かれていた。
音楽のスーパースター、リストの光と影
フランツ・リスト(1811–1886)は、初めて「音楽で女性を失神させた男」と呼ばれる、19世紀のスーパースターである。彼は超絶技巧をもってピアノという楽器の限界を拡張し、一方で宗教的な瞑想や死の観念を描いた作品も残している。
その音楽はしばしば「劇的」「絵画的」と称される。彼の作品には、バロックの形式美も、古典のバランスもない。あるのは、個の感情の純粋な解放である。
情熱の継承者、ブラームス
ヨハネス・ブラームス(1833–1897)は、ロマン派の中でも特異な存在である。彼はシューマンから“ベートーヴェンの正統な後継者”と称され、形式を重んじつつも、深く濃密な感情を音楽に込めた。
ブラームスの音楽は、ロマン派の情熱と古典派の理性がせめぎ合う“音の葛藤”である。そこには、決して表には出さない抑制された激しさがある。
ロマン派と“国民”という意識
この時代は、ナショナリズムの時代でもある。ショパンのポーランド、スメタナのチェコ、シベリウスのフィンランド ── 作曲家たちは自国の伝統や民謡に根ざした音楽を創り始めた。音楽は“自我の叫び”であると同時に、“民族の声”ともなった。
ロマン派とは、自己の内面と祖国の風景、その両方を音楽に託した時代だったのである。
まとめ:音楽が“個”を語り始めたとき
ロマン派の音楽は、作曲家という“人間”の存在が濃密に現れる芸術である。そこには誰かに頼まれて作った音楽ではなく、自分の声、自分の痛み、自分の夢がある。
音楽はもはや“誰かのため”ではなく、“私自身”のために鳴り始めた。それは、芸術の大きな転換点であり、今日私たちが音楽に「共感」する出発点でもある。

Sera H.:時代を越える音楽案内人/都市と田舎、過去と未来、東洋と西洋。そのあわいにいることを好む音楽ライター。クラシック音楽を軸にしながら、フィールド録音やアーカイブ、ZINE制作など多様な文脈で活動を展開。書くときは、なるべく誰でもない存在になるよう心がけている。名義の“H”が何の頭文字かは、誰も知らない。