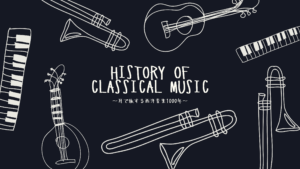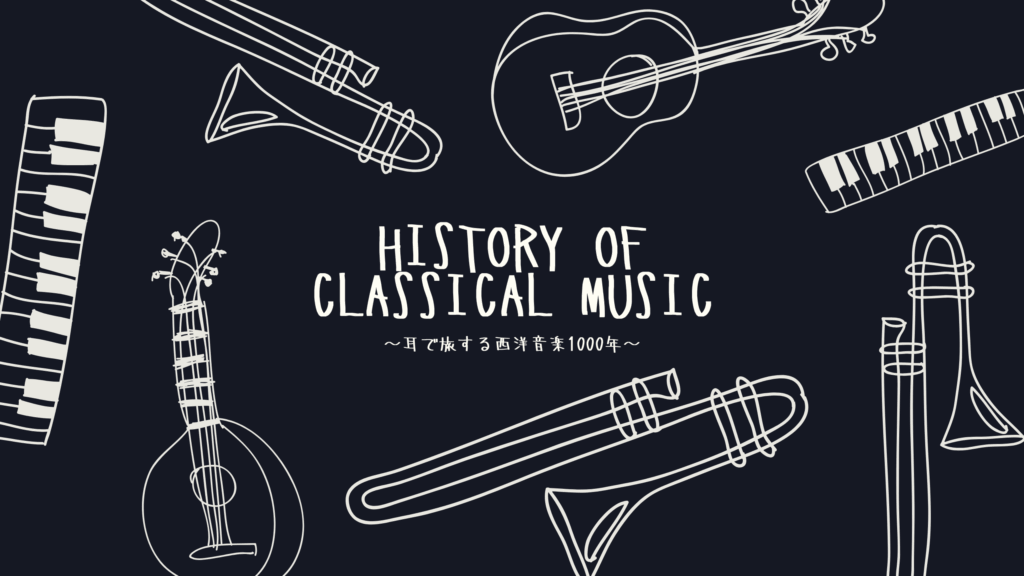
音楽は、どこから来て、どこへ向かうのか。
「クラシック音楽」と聞くと、あなたはどんなイメージを抱くだろうか。
堅苦しい、難しそう、あるいは昔の音楽 ── 。けれど、それはほんの一部に過ぎない。
クラシック音楽とは、9世紀の祈りの声から始まり、劇場、宮廷、戦場、そして映画館やスマートフォンの中へと受け継がれてきた、“人間の感情と思想のアーカイブ”である。そこには、ただ美しいだけではない、問いや葛藤、時代のうねりと個人の叫びが、確かに息づいている。
この全8回の連載では、中世から21世紀まで、クラシック音楽の歴史を大きく8つのフェーズに分けてたどる。バッハも、ベートーヴェンも、ジョン・ケージも、決して遠い存在ではない。彼らの音楽は、時代を超えて今も私たちの耳に届いている。
音楽は、いつも変わり続ける。
だからこそ、過去を知ることは、未来の音をもっと自由に聴くためのヒントになるはずだ。
クラシック音楽の1000年を、あなたの耳で旅してみよう。
音楽が「祈り」から始まり、「人間」へと向かった先に、ある種の転換点が訪れる。それがバロック時代である。17世紀から18世紀半ばにかけて、音楽はついに“感情”を解き放ち、観る者・聴く者の心を直接揺さぶる「ドラマ」となった。
この時代の音楽は、明確なリズムと対照的な感情のコントラストによって特徴づけられている。壮麗な建築や絵画と同じく、バロック音楽は“動き”と“光”を重んじる芸術であり、クラシック音楽における表現力の飛躍とも言える。
今回は、バロック音楽の構造と魅力をひも解きながら、J.S.バッハ、ヴィヴァルディ、ヘンデルらの代表作を紹介していく。
「バロック」とは何だったのか?
「バロック」という語は、本来は「いびつな真珠」を意味するポルトガル語“barroco”に由来し、当初は否定的な意味合いで用いられていた。しかし今日では、華やかさ、劇的な感情、そして精緻な構造美を兼ね備えた時代として高く評価されている。
この時代、音楽は宮廷や教会のみならず、劇場や街中の演奏会へと開かれていった。オペラやカンタータ、協奏曲、組曲など、多彩なジャンルが登場し、音楽家たちはその中で新たな表現を追求していった。
音楽の主人公、バッハの宇宙
バロック時代の最重要人物といえば、何と言ってもヨハン・セバスチャン・バッハ(1685–1750)である。
彼はオペラを一切書かなかったにもかかわらず、バロックの精神をあらゆる形式で体現した。対位法の極致、構造美、そして宗教的敬虔さと人間的情熱の融合 ── その音楽は、聴く者を「知と情の宇宙」へと導く。
イタリアから世界へ ── ヴィヴァルディの協奏曲革命
バロック時代を語る上で外せないもうひとりが、アントニオ・ヴィヴァルディ(1678–1741)である。彼は、独奏楽器とオーケストラが競い合う「協奏曲(コンチェルト)」形式を確立し、そのスタイルは後のモーツァルトやベートーヴェンへと引き継がれていく。
ヴィヴァルディの音楽は、わかりやすく、躍動感に満ち、聴き手をわくわくさせてくれる。その代表作が《四季》である。
ヘンデルと“オペラからオラトリオへ”の逆転劇
ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル(1685–1759)は、バッハと同年に生まれ、イタリア、イギリスと舞台を移しながら多彩な作品を残した。
特に注目すべきは、彼がオペラと並んで手がけたオラトリオというジャンルである。オラトリオは宗教的題材による音楽劇だが、舞台装置や演技を持たず、音楽だけで物語を展開する。中でも《メサイア》は、今なお世界中で演奏され続けている不朽の名作である。
“形式”と“感情”の美しき均衡
バロック音楽の魅力は、緻密な構造と、燃えるような感情のコントラストにある。音楽は、数学的に精緻な形式を持ちながら、それでいて魂を揺さぶる力を失わない。
とりわけ、繰り返しと変奏(リトルネッロ形式)、低音の反復(通奏低音)、対位法的な声部の絡みといった技法は、後の音楽の基本語彙となっていく。つまり、バロック音楽とは、クラシック音楽にとっての“文法”を築いた時代だったのである。
バロックが今なお愛される理由
現代でもバロック音楽の人気は衰えない。軽快でわかりやすい旋律、明確なリズム、そして精神性の高さ──それらがバランスよく共存しているからである。
加えて、ピアノや電子音ではなく、チェンバロやバロック・ヴァイオリンなど、当時の楽器の響きが再現される「古楽演奏(ピリオド・パフォーマンス)」の潮流も広がっている。演奏スタイルに対する関心が高まり、よりリアルな「バロックの音」を体感できるようになったのだ。
まとめ:バロックは“動く建築”、そして“感情の器”
バロック音楽は、ただ聴くだけでなく、「場」をつくり、「時間」を彫刻する力を持っている。それは、神に捧げる音楽でもあり、人間の感情を爆発させる舞台装置でもある。
この時代に生まれた形式と技法は、古典派以降の音楽に受け継がれ、今日のクラシックの土台となっている。
そして何より、バロック音楽は今も変わらず、私たちの“心の劇場”を満たしてくれる。

Sera H.:時代を越える音楽案内人/都市と田舎、過去と未来、東洋と西洋。そのあわいにいることを好む音楽ライター。クラシック音楽を軸にしながら、フィールド録音やアーカイブ、ZINE制作など多様な文脈で活動を展開。書くときは、なるべく誰でもない存在になるよう心がけている。名義の“H”が何の頭文字かは、誰も知らない。