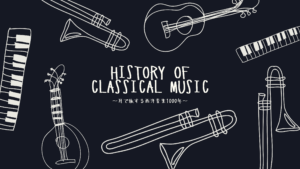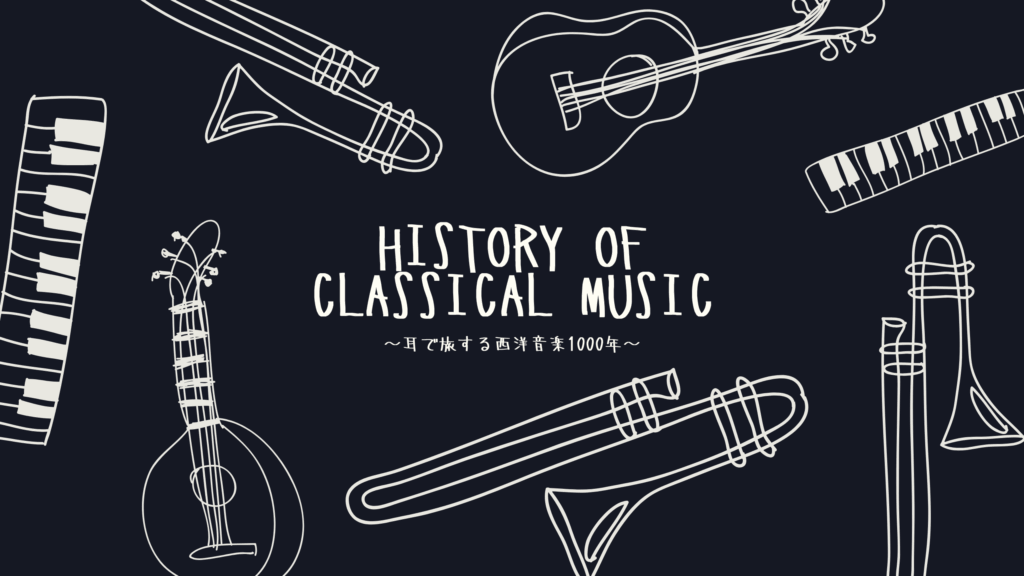
音楽は、どこから来て、どこへ向かうのか。
「クラシック音楽」と聞くと、あなたはどんなイメージを抱くだろうか。
堅苦しい、難しそう、あるいは昔の音楽――。けれど、それはほんの一部に過ぎない。
クラシック音楽とは、9世紀の祈りの声から始まり、劇場、宮廷、戦場、そして映画館やスマートフォンの中へと受け継がれてきた、“人間の感情と思想のアーカイブ”である。そこには、ただ美しいだけではない、問いや葛藤、時代のうねりと個人の叫びが、確かに息づいている。
この全8回の連載では、中世から21世紀まで、クラシック音楽の歴史を大きく8つのフェーズに分けてたどる。バッハも、ベートーヴェンも、ジョン・ケージも、決して遠い存在ではない。彼らの音楽は、時代を超えて今も私たちの耳に届いている。
音楽は、いつも変わり続ける。
だからこそ、過去を知ることは、未来の音をもっと自由に聴くためのヒントになるはずだ。
クラシック音楽の1000年を、あなたの耳で旅してみよう。
クラシック音楽の旅は、どこから始まるのか。それは、現在のような“芸術”としての音楽ではなく、“祈り”としての音楽 ── すなわち神への奉仕、精神の高みを目指すための道具として生まれた音の世界である。文字も読めず、楽器すら持たぬ人々が、空間に満ちる“声”によって世界と交信しようとした時代。その響きこそが、クラシック音楽の原点である。
今回は、9世紀頃から16世紀にかけての中世・ルネサンス時代に焦点を当て、「なぜ音楽が人間に必要だったのか」という根源的な問いに迫ってみたい。
声だけの音楽:グレゴリオ聖歌と“単旋律”の祈り
最初に登場するのが、グレゴリオ聖歌である。これはキリスト教の礼拝に用いられたラテン語による聖歌で、旋律は極めてシンプル、リズムも自由で、器楽の伴奏は一切ない。ひたすらに、神の言葉を“声”で伝えるという純粋な表現だ。
これらの音楽は、耳ではなく“心”で聴くものだった。大聖堂の高い天井に反響する歌声は、まるで天から降り注ぐ光のように、信仰を深める手段として機能していたのである。
(『シャイニング』『レクイエム・フォー・ドリーム』など)にも頻出する恐るべきモチーフ。
音楽は重なり始める ── “多声音楽”の誕生
やがて、神の言葉をひとつの旋律で歌うだけでなく、複数の旋律を同時に歌うという革新的な技法が現れる。これが「ポリフォニー(多声音楽)」の始まりである。
この技法の発展には、楽譜の進化が大きく関係している。中世の修道士たちは、音の高さや長さを視覚的に記録する方法を確立し、音楽が“再現可能な芸術”へと変貌していった。とりわけ、ノートルダム楽派と呼ばれる13世紀の作曲家たちは、複雑で荘厳な音楽を生み出し、宗教音楽の表現力を大きく押し広げた。
人間中心の音楽へ ── ルネサンスの転換点
14世紀後半から16世紀にかけて、ルネサンス期の音楽は中世からの大きな転換を見せる。宗教の中にあった音楽は、次第に人間そのものを見つめる表現へと変化していく。
この時代には、対位法(カウンターポイント)と呼ばれる技術が成熟し、複数の旋律が独立しながら調和するという高度な作曲法が発展した。また、“音の調和”は神の秩序の反映であると考えられていたため、音楽はまさに“宇宙の縮図”とされていたのである。
知られざる名曲たち ── 美しきア・カペラの宝石
この時代の音楽は、現代の耳にとっても極めて新鮮である。なぜなら、電子音も打ち込みも存在しない“純粋な声”のみで世界を構築しているからだ。
また、近年ではルネサンス音楽が再評価され、アンサンブルや合唱団による録音も増えてきた。中には、映画『ノッティングヒルの恋人』の挿入歌として使われたトマス・タリスや、フランスの作曲家ギヨーム・デュファイのように、再発見されてきた作曲家も多い。
“響き”としてのクラシックを体感する
中世・ルネサンス期の音楽を聴いていると、現代の音楽とはまったく違う時間が流れていることに気づかされる。拍子もリズムもなく、和声進行もない。あるのは“響きのうつろい”と、音と音の間にある“余白”である。
それは、忙しない現代生活から切り離され、ゆったりとした精神の深呼吸を取り戻す時間でもある。たとえば休日の朝や、夜に静かに過ごしたいとき、こうした音楽は最高の「時間の薬」になってくれるだろう。
まとめ:音楽の始まりは「祈り」であった
クラシック音楽は、最初から「芸術」ではなかった。それは、神への祈りであり、人と人とをつなぐ記号であり、空間を神聖化するための“場づくり”でもあった。
中世とルネサンスは、クラシック音楽の「魂のルーツ」である。そしてその響きは、現代の私たちにとっても、忘れられた内面の声を取り戻す鍵となるだろう。

Sera H.:時代を越える音楽案内人/都市と田舎、過去と未来、東洋と西洋。そのあわいにいることを好む音楽ライター。クラシック音楽を軸にしながら、フィールド録音やアーカイブ、ZINE制作など多様な文脈で活動を展開。書くときは、なるべく誰でもない存在になるよう心がけている。名義の“H”が何の頭文字かは、誰も知らない。