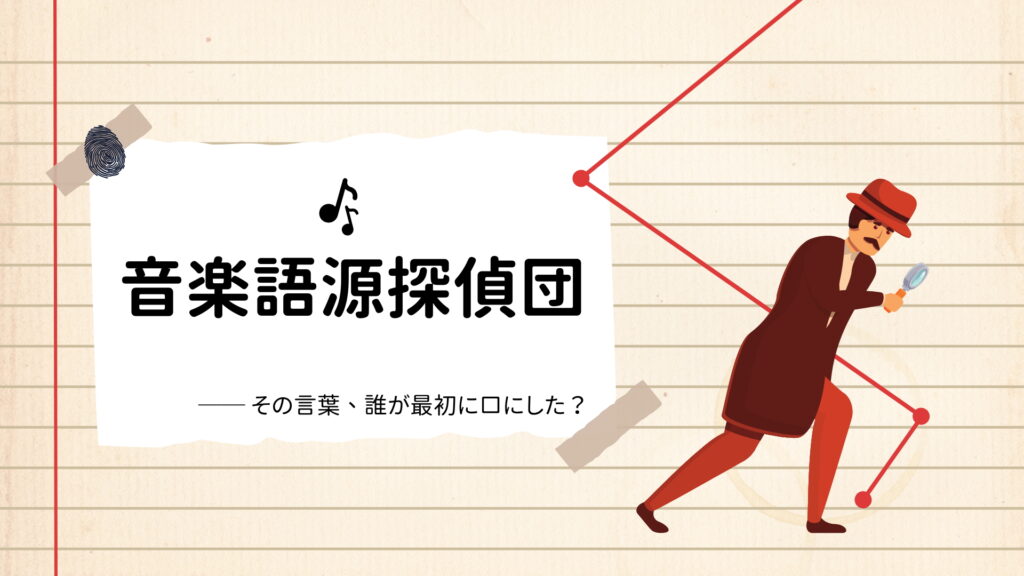
シンセサイザー群雄割拠の時代
1970年代後半、シンセサイザーは急速に進化を遂げていた。Moog、ARP、Sequential Circuits、そしてRolandやYAMAHAといったメーカーが、アナログシンセからデジタル制御への過渡期にさまざまな機材を送り出していた。
しかし当時、最大の問題は「互換性がない」ということだった。あるメーカーのシーケンサーで作ったフレーズは、別のメーカーのシンセに送っても鳴らない。接続用の端子や信号はそれぞれ独自規格で、ユーザーは複数のシステムを併用するたびに困難に直面していた。
たとえば、クラフトワークの「Computer World」(1981)やYMOの「Technopolis」(1979)といったエレクトロニック・ミュージックの先駆者たちは、複雑なシンク信号やカスタムケーブルを駆使して機材を同期させていた。だが、これは熟練したエンジニアがいてこそ可能な芸当で、一般の音楽家が真似できる環境ではなかった。
こうした混乱の中で、「共通の言語が必要だ」という声が高まっていったのである。
「MIDI」という言葉が生まれるまで
1981年、米国カリフォルニアのAES(Audio Engineering Society)大会で、シンセメーカー Sequential Circuits の創業者デイヴ・スミスと技術者カート・ウィッティグが、新しいインターフェイスの構想を発表した。彼らはそれを 「USI(Universal Synthesizer Interface)」 と呼んでいた。
この提案に真っ先に反応したのが、Roland創業者の 梯郁太郎(かけはし・いくたろう) である。彼はUSI構想を評価しつつ、さらに広いメーカー間で合意を形成するべきだと考え、YAMAHA、Korg、Kawai など日本の主要メーカーにも参加を呼びかけた。
やがて議論の中で「USI」よりも音楽的で直感的な名前が求められた。そこで浮上したのが Musical Instrument Digital Interface──略して MIDI である。この呼び名は、技術者だけでなく一般の音楽家にも理解しやすく、採用が決定された。
1982年にはMIDI 1.0仕様書がまとめられ、翌1983年、アナハイムで開かれたWinter NAMM Showにて、Roland Jupiter-6 と Sequential Circuits Prophet-600 がMIDI端子で接続され、2台のシンセが同じフレーズを演奏するデモンストレーションが行われた。この瞬間が「MIDIの誕生」として音楽史に刻まれている。
この時代の象徴的な楽曲として、Prophet-600を使用したハービー・ハンコック「Rockit」(1983)が挙げられる。スクラッチとシンセサウンドの融合は、MIDI時代の幕開けを象徴している。
音楽をつなげたインターフェイスの奇跡
MIDIは徐々に世界標準となり、シンセサイザーだけでなく、ドラムマシン、エフェクター、照明システムにまで拡張していった。1980年代中期から後期にかけて、MIDI対応機器の普及により、日本の音楽シーンでも打ち込みサウンドが本格的に浸透していった。
海外では、ニュー・オーダー「Blue Monday」(1983)がプログラムドラムとシンセサイザーを効果的に使用した初期の代表例であり、デペッシュ・モード「Master and Servant」(1984)などもMIDIシーケンシングを活用した楽曲として知られている。
1990年代にはパソコンと接続する「DTM」の時代に突入し、YAMAHAのXG音源やRolandのSCシリーズがアマチュアにまで普及した。「打ち込み」という言葉が浸透したのも、このMIDIのおかげである。小室哲哉プロデュースによる楽曲群や、TM NETWORK「Get Wild」(1987)などは、MIDIによる複雑なシーケンスがサウンドの骨格を形成している代表例である。
2000年代以降、ソフトウェア音源が台頭しても、MIDIは依然として音楽制作の基盤であり続けている。現代のDAW(Digital Audio Workstation)環境においても、MIDIは楽器間の通信やオートメーション制御において重要な役割を果たしている。
つまり「MIDI」という言葉は、1980年代初頭の技術者の提案から生まれたが、それは単なる略称にとどまらず、音楽家たちの創造力を無限に拡張するための合言葉となったのである。
結論
「MIDI」という言葉を最初に提案したのは、Sequential Circuits の デイブ・スミス と技術者 カート・ウィッティグ である。だが、その普及と標準化には、Rolandの 梯郁太郎 をはじめとする日本の技術者たちの尽力が不可欠であった。
今やMIDIは「音楽をつなぐ共通言語」として、40年以上にわたり進化を続けている。スマートフォンの音楽アプリから巨大なフェスの照明演出まで、MIDIは見えないところで息づいているのだ。
「MIDI」とは、単なる技術用語ではなく、1980年代の夢想家たちが世界をひとつにつなげようとした証であり、音楽家たちが未だに語り継ぐ魔法の言葉なのである。

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。







