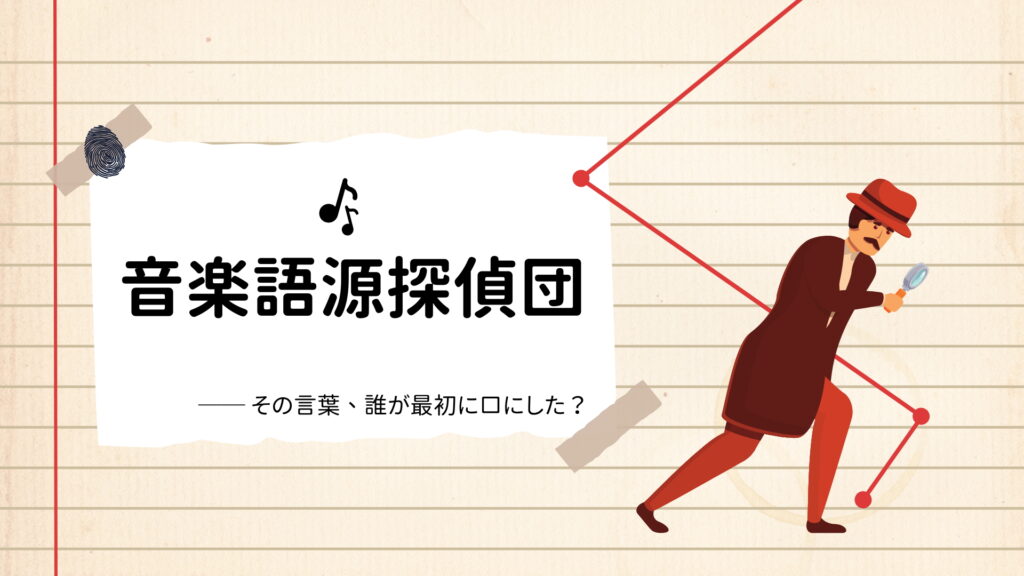
「打ち込み」という言葉はどこから来たのか
「打ち込み」という言葉は、日本の音楽シーンに特有の用語である。英語で言えば「programming」や「sequencing」といった表現にあたるが、国内では1980年代以降「シンセサイザーやリズムマシンにリズムやフレーズを”打ち込む”」という行為を、そのまま日常語として定着させていった。
語源については複数の説があり、明確な起源は特定されていない。一般的には、MIDI(Musical Instrument Digital Interface)が普及した1983年以降のDTM黎明期に、ミュージシャンやエンジニアたちがスタジオで「このパターンをシーケンサーに打ち込んでおいて」といった言い方をしていたことが影響している可能性が高いとされる。当時は、従来の演奏録音とは異なる「演奏しない演奏」の概念が新しく、その作業を表現する適切な日本語として「打ち込み」という表現が自然発生的に生まれたと考えられる。
特に日本では、「手作業で鍵盤を叩くこと」よりも「コマンドを一音一音入れていく」作業が印象強く、その語感が職人的な響きをもって広まった。演奏を「吹き込む」と呼んでいたアナログ録音時代に対し、デジタル時代には「打ち込む」という言葉がしっくりきたのだろう。
ここで参考として挙げられるのは、坂本龍一の『B-2 Unit』(1980年)収録の「Riot in Lagos」である。この楽曲はシーケンサーとリズムボックスによるミニマルな構造を持ち、後に「打ち込み」と呼ばれるようになる制作手法の先駆的な例として位置づけることができる。ただし、この時点ではまだ「打ち込み」という言葉は存在していなかった。
DTMブームと「打ち込みサウンド」の拡張
1980年代後半から1990年代にかけて、パソコンとMIDIを活用したDTM(Desk Top Music)が一気に広がった。この時代、音楽誌や機材雑誌がこぞって「打ち込み講座」を掲載し、キーボード誌では「打ち込みフレーズを作ろう」という特集が組まれていた。ここで完全に「打ち込み」という言葉が一般化し、プロ・アマ問わずに使われるようになった。
例えば小室哲哉が手がけたTRFの「EZ DO DANCE」(1993年)は、シーケンサーによるリズムとシンセサイザーのフレーズが前面に出ており、「生演奏ではなく、打ち込みで作られたサウンド」という印象が強烈だった。同時に、多くのアーティストも積極的に打ち込みを導入し、1990年代のポップスシーンを特徴づける要素となった。
この頃の「打ち込み」は、単にリズムを打ち込むだけでなく、コード進行やベースライン、シンセのアルペジオまでも網羅しており、一人のクリエイターが「バンド全員分を打ち込む」ことすら珍しくなかった。その結果、「打ち込みサウンド」という言葉自体が、単なる制作方法の記述から、90年代ポップスを象徴するスタイルの呼称にまで拡張していったのである。
ポップスとクラブカルチャーをつなぐ「打ち込み」
2000年代以降、「打ち込み」という言葉はさらに広がりを見せる。クラブカルチャーの影響を受けたJ-POPや、エレクトロニカを取り入れた新世代のアーティストが台頭したことで、もはや「打ち込み」は特別なものではなく、音楽制作の標準的な手法となった。
Perfumeの「ポリリズム」(2007年)は、中田ヤスタカがコンピュータで緻密に組んだリズムとサウンドが日本のポップスに新たな可能性をもたらした象徴的楽曲である。ここでは「打ち込み」という手法が単なる技術用語を超え、「現代的なサウンドの特徴」として受容された。
一方で、ロックシーンでも「打ち込み」は有効に活用された。多くのバンドがプログラミングされた要素を楽曲に組み込み、バンドサウンドと打ち込みの融合が自然に行われるようになった。現在では、打ち込みを土台に生演奏を重ねるスタイルが広く普及し、「打ち込み」という言葉自体の境界線が曖昧になっている。
つまり、「打ち込み」という言葉は、最初は現場の俗語として生まれた可能性が高いが、1980〜90年代のテクノロジー進化とポップスの大衆化を経て、今では「コンピュータで作られた音楽」という極めて広い意味合いをもつに至ったのである。
結論
「打ち込み」という言葉を最初に言い出した人物を特定することは困難である。だが、その背景には1980年代のスタジオ現場での表現があり、それが雑誌やメディアを通じて広まり、やがて一般のリスナーの耳にも届いたという経緯があると推測される。
いまや「打ち込み」は、単なる技術用語ではなく、日本の音楽文化を象徴するキーワードである。手作業で一音一音をシーケンサーに入力していた時代の労力と創意工夫を思い起こすとき、私たちはこの言葉に「デジタル時代の音楽制作」という独特のニュアンスを感じ取ることができるのである。
※本コラムは筆者の見解であり諸説あります。

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。







