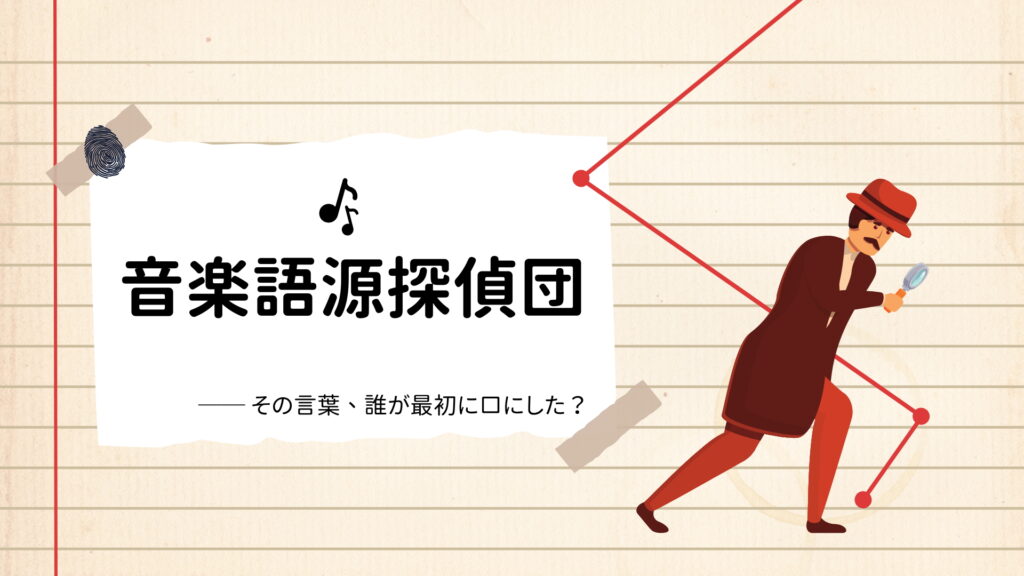
欧米の“teen idol”と日本への輸入
「アイドル」という言葉は日本オリジナルの造語ではない。元来は英語の “idol” に由来し、「偶像」「崇拝の対象」を意味する単語である。宗教的には「偶像崇拝」というニュアンスで使われるが、20世紀に入ると芸能やポピュラー文化の文脈で「若者が熱狂的に憧れるスター」を指すようになった。
特に1950年代のアメリカでは、「ティーン・アイドル(teen idol)」という表現がポピュラーであった。エルヴィス・プレスリー、ポール・アンカ、リッキー・ネルソンらがその代表格であり、彼らはただの歌手ではなく「10代の憧れの対象」としてマーケットされていた。映画『ジェイルハウス・ロック』に映るプレスリーの姿や、ポール・アンカの「Diana」を涙ながらに聴くティーンの姿はまさに“アイドル”の原型をなしている。
この “teen idol” の概念が日本に持ち込まれたのは、アメリカンポップスや映画が大量に輸入されていた1960年代初頭である。音楽業界や芸能誌の記者たちは、まだ「スター」「歌手」といった言葉を中心に使っていたが、やがて“idol”をそのままカタカナ化して紹介する記事が現れるようになった。
1960年代映画と芸能界が広めた“アイドル”
「アイドル」という言葉が日本で一般の耳目を引いた最初の大きな契機は、1964年に公開されたフランス映画『アイドルを探せ』(原題 Cherchez l’idole)だと思われる。この映画自体は若者向けの軽いミュージカル映画であり、タイトルに“idol”の語が含まれていたことで、日本のマスメディアに「アイドル=若者に人気のスター」という連想が生まれたと言っていいだろう。
この頃の日本の芸能界は、テレビの普及とともに新しいスター像を模索していた。美空ひばりや江利チエミといった戦後直後の歌謡スターとは異なり、欧米的でモダンな若者文化を体現する存在が求められたのである。1960年代後半には、西郷輝彦、橋幸夫、舟木一夫ら「御三家」が若者のアイドル的存在として人気を博すが、当時のメディアはまだ「アイドル歌手」という表現を多用してはいなかった。
しかし、1960年代半ばから後半にかけて、芸能記者や放送作家が“idol”という言葉を意識的に使い始める。欧米の “teen idol” を翻訳する形で「アイドル」を「若者の憧れの対象」として記事に書き、テレビ番組の紹介や雑誌特集で定着させていったのである。
1970年代「新三人娘」と言葉の定着
「アイドル」という言葉が日本の芸能用語として本格的に根付いたのは1970年代初頭である。その代表が天地真理、南沙織、アグネス・チャンのいわゆる「新三人娘」であった。彼女たちは従来の歌謡曲歌手のような技巧派ではなく、親しみやすく清純なキャラクターを売りにしており、テレビを通じて10代のファンから圧倒的な人気を集めた。
この時期、マスメディアは彼女たちを「アイドル歌手」と呼び、その呼称は新聞や雑誌の見出しで繰り返し使われた。特に天地真理の「水色の恋」(1971年)は大ヒットとなり、彼女の笑顔と歌声は「国民的アイドル」という新しいスター像を象徴するものとなった。
同時に、南沙織の「17才」(1971年)も大きな話題を呼び、沖縄出身でハーフのような容姿を持つ彼女は「都会的で新しい女の子像」を体現した。
ここで注目すべきは、芸能界が「アイドル」を単なる歌手ではなく「トータルな人気者」としてプロデュースし始めた点である。歌唱力の優劣よりも、テレビ映えする笑顔、雑誌のグラビアに載る可憐さ、親しみやすいキャラクター性が重視された。つまり、“idol”が「若者が憧れる存在」から「産業としてプロデュースされる商品的スター」へと変化した瞬間であった。
80年代以降、アイドル像の多様化
1970年代に定着した「アイドル」は、1980年代に入るとさらに産業的に拡大していく。松田聖子、中森明菜、小泉今日子らが「80年代アイドル」として脚光を浴び、従来の「清純派」に加え「自立した女性像」「反抗的キャラクター」など多様なアイドル像が現れた。
松田聖子の「青い珊瑚礁」(1980年)は、可憐さとポップさを兼ね備えた典型的アイドルソングであり、彼女は「ぶりっ子」という新しい言葉を社会に生み出した存在でもあった。
一方、中森明菜の「少女A」(1982年)は、アイドルでありながら従来の清純路線を裏切る挑発的なキャラクターを打ち出し、アイドル像の幅を広げた。
1990年代以降は、モーニング娘。やAKB48のように「集団アイドル」や「会いに行けるアイドル」が登場し、アイドルの定義はさらに拡散する。2010年代には、地下アイドル、バーチャルアイドル、さらにはVTuberまでが「アイドル」と呼ばれるようになり、その範囲は限りなく広がっている。
結語
「アイドル」という言葉を日本で最初に言い出した人物を一点に特定することは難しい。だがその成立の過程をたどれば、答えは次のように整理できる。
- 起源は欧米の“teen idol”であり、日本の芸能界はこれを輸入した。
- 普及のきっかけは1964年公開の映画『アイドルを探せ』や、1960年代半ばの音楽ジャーナリズムである。
- 定着の決定打は1970年代初頭の「新三人娘」と彼女たちを「アイドル歌手」と名付けたマスメディアである。
つまり「アイドル」という言葉は、誰かひとりの発明ではなく、欧米文化を翻訳し、芸能界とマスメディアが共同で広めた言葉であった。
そしてこの言葉は、時代ごとに意味を変えながら今も生き続けている。清純さ、親しみやすさ、反逆性、DIY精神──「アイドル」とは常に若者文化の鏡であり、同時に商業的なプロデュースの産物でもある。その二重性こそが、日本における「アイドル」という言葉を特別なものにしているのである。
※本コラムは筆者の見解であり諸説あります。

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。







