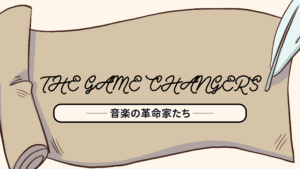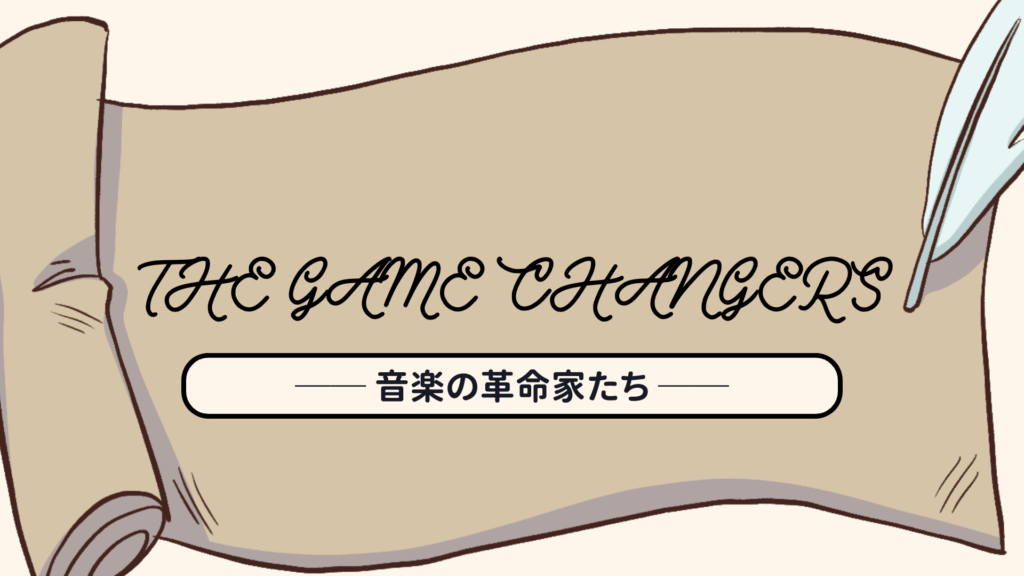
モンタレー・ポップ・フェスティバル──ロックの祝祭
このイベントは、後のウッドストックやコーチェラにも繋がる“フェス文化”の原点と言われている。オーガナイザーはジョン・フィリップス(ママス&パパス)やルー・アドラー。音楽と反戦の意志が交差する、まさに「サマー・オブ・ラブ」の象徴だった。
出演アーティストには、ジャニス・ジョプリン、ザ・フー、グレイトフル・デッド、サイモン&ガーファンクル、そしてジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスが並んだ。
ジミは当初、アメリカではまだ無名に近かった。だがチャス・チャンドラーの策略で、当時すでに人気絶頂だったザ・フーの直後という絶好のタイミングに出演が決定される。
(ちなみに、出演順を巡ってジミとザ・フーが揉めたという逸話も残っている)
《Wild Thing》と“炎上”パフォーマンス
その夜のセットリストは圧巻だった。《Killing Floor》で幕を開け、《Foxy Lady》《Like a Rolling Stone》(ボブ・ディランのカバー)、《Hey Joe》といった楽曲を次々に披露する。そしてラスト、トロッグスの《Wild Thing》。ギターは叫び、アンプは唸り、ジミは暴れた。
そしてクライマックス──彼はステージ上でギターに火をつけた。マッチを擦る。炎が舞う。ジミはその炎の前に跪き、まるで“供物”を捧げる神官のようにギターに祈る。
客席は一瞬、静まり返った。次の瞬間、熱狂と悲鳴が混じったような歓声が轟いた。
「演奏」ではなく「儀式」だった
あのパフォーマンスは単なる“ショック芸”ではない。ジミにとって、それは音楽と身体と精神をひとつにする儀式だったのだ。《Wild Thing》のソロでは、彼はギターを股間に突き立てるように演奏し、床に叩きつけ、破壊し、火をつけた。そこには黒人アーティストとしての怒りも、ロック文化に対する挑戦も、サイケデリアへの身体的な応答もすべて詰まっていた。
この夜を観た者の多くは「ロックの歴史が変わった瞬間」と語る。ジミ・ヘンドリックスは単なるギタリストではなく、“現象”となった。
アメリカ逆輸入──“黒い革命児”の帰還
モンタレーを境に、アメリカのメディアはジミに熱狂し始める。特に西海岸──サンフランシスコのフィルモアやアヴァロン・ボールルームなど、サイケ・ロックの震源地では彼は完全に時代の先端を象徴する存在となった。
その一方で、東海岸の保守的なブルース・ファンからは「何だあの騒音は」という拒絶の声もあった。だが、それこそがジミの革新性の証だった。ブルースでもない、ロックでもない、“第三の音楽”を彼は体現していた。
“黒人性”と“白人マーケット”の狭間で
アメリカに戻ったジミが直面したのは、黒人アーティストとしてのアイデンティティと、白人市場での成功とのギャップである。
黒人のブルース・ミュージシャンたちは、彼の派手なパフォーマンスやサイケデリックな装いを異端視した。一方、白人の若者たちは彼を「異国の魔術師」のように崇めた。
ジミ自身もその狭間で苦悩した。「俺は誰のために演奏しているんだ?」と。
音楽は進化する──《Axis: Bold as Love》
モンタレーの翌年、1967年末にセカンド・アルバム《Axis: Bold as Love》がリリースされる。ここでジミは、“炎と暴力”だけではない、内省的な音楽世界を提示した。
《Little Wing》はたった2分半の小曲ながら、彼の詩的な感性と柔らかなトーンが光る名作だ。
《If 6 Was 9》では、既成概念への挑戦とフリーキーな精神性を前面に出し、
《Castles Made of Sand》では人生の儚さを浮遊するメロディに託している。
ジミは炎を超え、“音で描く詩人”となっていく。

Jiro Soundwave:ジャンルレス化が進む現代音楽シーンにあえて一石を投じる、異端の音楽ライター。ジャンルという「物差し」を手に、音の輪郭を描き直すことを信条とする。90年代レイヴと民族音楽に深い愛着を持ち、月に一度の中古レコード店巡礼を欠かさない。励ましのお便りは、どうぞ郵便で編集部まで──音と言葉をめぐる往復書簡を、今日も心待ちにしている。