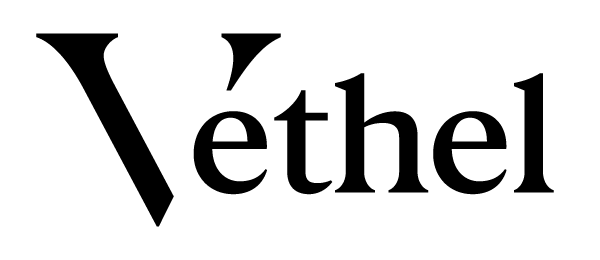1970年代末、ディスコの黄金時代が終わりを迎えたアメリカ。商業化の波に飲まれたディスコは一部のリスナーやメディアから反感を買い、「Disco Demolition Night(ディスコ爆破ナイト)」に象徴されるように、急速にその居場所を失っていった。しかし、ディスコが完全に死んだわけではなかった。その魂を受け継ぎながら、新たな表現へと進化させた音楽があった。それが、ハウスミュージックである。
“The Warehouse”とフランキー・ナックルズの伝説
ハウスの発祥地はシカゴのナイトクラブ「The Warehouse」。このクラブのレジデントDJであり、“Godfather of House”と称されるフランキー・ナックルズの存在は、ハウスの誕生に欠かせない。
ニューヨークでラリー・レヴァンと共にプレイしていたナックルズは、1977年にシカゴへと移り住み、「The Warehouse」のDJを任される。彼はディスコの名曲やソウル、ファンクに加え、イタロ・ディスコやエレクトロなど多様なジャンルを織り交ぜながら、ドラマチックで感情豊かなセットを構築した。
ナックルズのプレイは、単なる選曲を超えた芸術だった。レコード同士のビートを継ぎ目なく繋ぎながら、時にはリズムボックスを自ら操作し、既存の曲に新たな命を吹き込んだ。観客とのインタラクションを大切にしながらも、どこかスピリチュアルで没入感のあるグルーヴ。その空間で踊る人々は、ただ音楽を楽しむのではなく、解放され、癒やされ、変容していった。
シカゴのクラブシーンは当時、ゲイ・ブラック・ラテン系コミュニティの重要な拠点だった。「The Warehouse」も例外ではなく、ナックルズの音楽は彼らのアイデンティティを肯定し、連帯感を育む媒介となっていた。この時期、彼がプロデューサーとして手がけたジェイミー・プリンシプルとの「Your Love」は、後にハウスミュージックのアイコンとなる。
ローカルの創意が産んだ”DIYサウンド”
1980年代初頭、シカゴでは限られた資源と独自の工夫によって、新たな音楽が次々と生み出されていた。高価なスタジオにアクセスできない若者たちは、ROLAND TR-808やTR-909、TB-303といった比較的手の届くドラムマシンやシンセサイザーを使い、リビングや地下室でトラックを制作した。
こうして生まれた音楽は、洗練されていないがゆえの荒削りさと、機械の無機質さを逆手に取った独特の温かみを持っていた。これが「ハウス」と呼ばれるサウンドの原点である。最初は「Warehouseでかかっている音楽」として「house music」と呼ばれるようになったという説もある。
Trax RecordsやDJ Internationalといった地元のインディペンデント・レーベルがこの動きを後押しした。マーシャル・ジェファーソンの「Move Your Body」は“ハウスの国歌”とも称され、ラリー・ハード(a.k.a. Mr. Fingers)の「Can You Feel It」は、ディープハウスというサブジャンルの礎を築いた。
また、Phuture(フューチャー)による「Acid Tracks」はTB-303の独特のうねる音を前面に押し出し、アシッド・ハウスという新たな潮流を巻き起こす。その後のレイヴ文化やテクノにも影響を与えたこのサウンドは、まさにDIY精神の結晶だった。
ハウスのグルーヴは生きている
私が初めてシカゴ・ハウスを聴いたのは、大学時代に友人から渡された1枚のコンピレーションCDだった。聴いた瞬間、心を掴まれた。シンプルで反復的なリズムなのに、どこか切なく、温かく、体が自然と揺れてしまう。なぜか懐かしさすら感じた。あの時感じたのは、“生きているグルーヴ”そのものだったのだと思う。
その後も、シカゴ・ハウスの精神は形を変えながら世界中に広がっていった。ダフト・パンク、ハニー・ディジョン、ムーディーマン、そしてセオ・パリッシュらが現代においてそのエッセンスを受け継ぎ、再解釈しながらプレイしている。ハウスはもはや一地域の音楽ではなく、グローバルな言語となった。

Kei Varda:音楽文化研究者/ライター。ポストクラブ時代の感性と身体性に着目し、批評と記録の間を行き来する。特定の国や都市に属さない、ボーダーレスな語り口を好む。最近はリズムと都市構造の相関関係をテーマにした執筆に注力中。