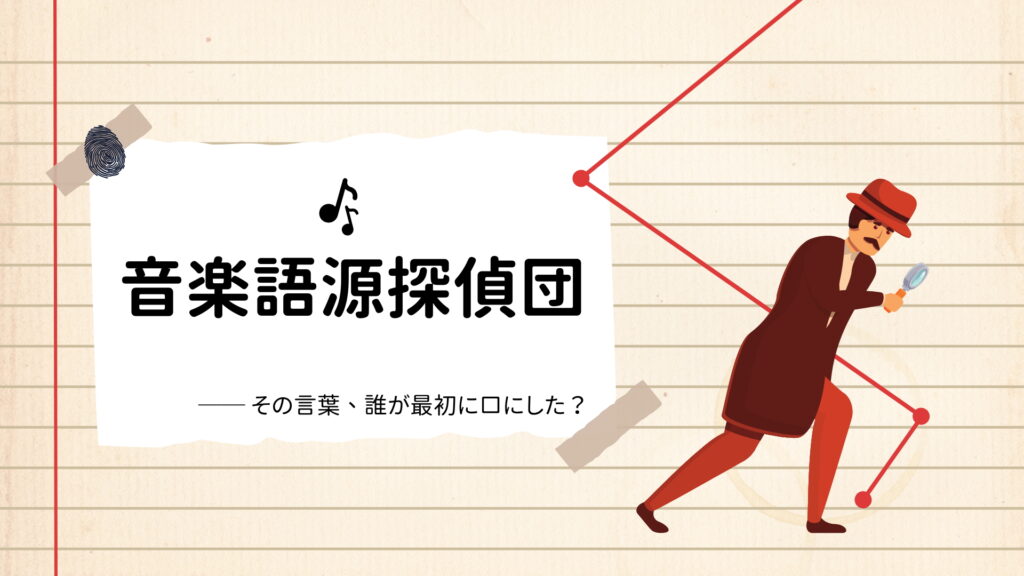
ロック・ギターの会話に当たり前のように出てくる「パワーコード」。だが、「最初にそう言い出したのは誰?」と問われると、途端に霧が立ちこめる。結論から言えば、これは特定の名付け親がいる“固有名詞”というより、現場とメディアの往復によって自然発生的に固まっていった俗称だ。ギター・メソッドや音楽誌で一般化するのは1980年代に入ってからで、たとえば定番教本『The Guitar Handbook』(1982年版)の章立てにすでに“Power chords”の項が立っている。つまり遅くとも80年代初頭には、ギタリスト共通の語彙として定着していたわけだ。
パワーコードはどこから来たのか?
ただし「言葉の歴史」と「サウンドの歴史」は重なりながらも別物だ。音そのものはもっと早い。評論家ロバート・パーマーは、ディストーションを浴びた5度のユニゾン(オクターヴ含む)がロックの暴発力を生む原型として、1950年代初頭のブルース・ギタリスト、ウィリー・ジョンソン(ハウリン・ウルフ・バンド)やパット・ヘア(ジェイムズ・コットン)を挙げている。具体的には「How Many More Years」(1951年)や「Cotton Crop Blues」(1954年)。ここで鳴っているのは、のちに“パワーコード”と呼ばれることになる音塊の、ほとんど完成形だ。
ポップ・チャートの只中でそれを“主役”に押し上げ、のちのギター少年の耳に焼き付けたのは、1958年のリンク・レイ「Rumble」だろう。彼はスピーカーコーンに実際に傷をつけて歪みを得たという伝説ごと、ロックの攻撃性を記号化してみせた。ピート・タウンゼント(ザ・フー)は「『Rumble』がなければギターを手にしなかった」とまで語っている。リンク・レイはしばしば“パワーコードを世に知らしめた人物”と記され、その功績は今も一般的な紹介文に刻まれている。
60年代半ばには、英国ビート勢がこの“二音(+オクターヴ)の塊”を曲の骨格に据え、キンクス「You Really Got Me」(1964)やフー「My Generation」(1965)が“乗算可能な攻撃性”を大衆化する。以降、70年代のハードロック〜ヘヴィメタル、パンク、80年代以降のオルタナ、90年代グランジ、2000年代ポップパンクにいたるまで、パワーコードは“電気ギターで疾走する曲”の最短距離として居座り続ける。
では、語としての「パワーコード」はどこから来たのか。一次資料で“この人が名付けた”と断言できる証拠は見つからない。だが経路は推測できる。70年代にロック・ジャーナリズムが演奏語彙を平易な英語で記述し始め、ギター誌が奏法を図解する。その過程で「fifth chord」「two-note chord」といった説明的な回り道を経ず、“力強いコード=パワーコード”という通俗語が定着したのだろう。90年代初頭の論考でも、パワーコードという語は完全に“共通名詞”として使われている。
なぜ“5度”はこんなに強いのか ── 音響の側面
パワーコードは、理論的には「根音+完全5度(+オクターヴ)」で“和音”というより“ダブルストップ”に近い。歪んだアンプに複数音を入れると非線形で倍音同士の和差周波数(インターモジュレーション)が発生する。三和音(長3度や短3度)を歪み下で鳴らすと、倍音どうしの干渉が濁りやすい。一方、完全5度は倍音列の初期項目(2:3:4)にきれいに乗るため、歪ませても“分厚いのに輪郭が崩れない”というご褒美がつく。だから、たった二音でも巨大に響く。
指板上の地政学 ── “E5の城”と可動フォーム
実務的には、6弦ルートのEやAの開放弦がアンプの低域を直撃して“強く感じられる”ため、初学者はE5、A5から着手することが多い。そこから人差し指と薬指(または小指)を“塊”としてスライドし、どのフレットでも同じ形で展開できる可動フォームになる。ドロップDや全音下げの世界では、さらに1フィンガーで横に寝かせて轟音を得ることもできる。ここで重要なのは、左手はコード、右手はリズムという分業だ。右手のオルタネイト、パームミュート、アクセント配置(3-3-2やシャッフルのハネ)で、同じE5でもグルーヴの人格が変わる。
「誰が言い出した?」 ── 問いの落とし所
・音の源流は50年代ブルースの電化とスタジオ歪みにさかのぼる(ジョンソン/ヘアの録音)。
・大衆化の引き金はリンク・レイ「Rumble」。以後、キンクス〜フーが“曲の柱”に育てた。
・語としての一般化は70年代のロック言説とギター教育が押し広げ、80年代の教本で完全に定着。
つまり「最初に言い出した誰か」はいない。ただし「最初に鳴らして、最初にそれを記号にした人」なら、引用可能な固有名が並ぶ。
パワーコードの“作曲術” ── やりすぎない、でも足りなくしない
パワーコードは“情報量を削る”作戦だ。3度を抜くことで長短の感情色を宙吊りにし、ベースやメロディが作る長短・拡張和声の余地を残す。ゆえに、
- ベースが3度で色を決める(例:ベースがC、ギターがG5=C/E的に聴かせる)
- メロディが#4やb6でモード感を差し込む
- ドラムのフィル位置で“推進力”の錯覚を作る
この三者連携が決まると、二音の塊は“曲の設計”に化ける。逆に言えば、全員が同じ拍・同じ音域で厚塗りすると、途端に単調に聴こえる。王道だからこそ、隙間の設計が肝だ。
参考曲プレイリスト(耳でたどる小史)
- Howlin’ Wolf – “How Many More Years” (1951):ざらついたアンプに叩きつける初期電化ブルース。パワーコードの原像を聴く。
- James Cotton – “Cotton Crop Blues” (1954):パット・ヘアの荒くれたコンプ+歪み。リフそのものが“塊”で動く。
- Elvis Presley – “Jailhouse Rock” (1957):スコッティ・ムーアの開幕コードワークに“二音の圧”が顔を出す。
- Link Wray – “Rumble” (1958):不良性と“恐怖のダイアド”を大衆化。のちのすべての轟音系の起点。
- The Kinks – “You Really Got Me” (1964):チャンクなブロックで押すリフ—パワーコードが曲を牽引する典型。
- The Who – “My Generation” (1965):タウンゼント流“風圧”。レイの衝撃が英国モッズで花開く。
- Black Sabbath – “Paranoid” (1970):低域とうねりに三度を置かず、ギターは塊で突進。“重さ”の教科書。
- Ramones – “Blitzkrieg Bop” (1976):8分刻み+パワーコード=速度の幻覚。最小構成の爆発力。
- AC/DC – “Highway to Hell” (1979):倍音リッチな歪みの“抜け”を証明するアンサンブル。
- Nirvana – “Smells Like Teen Spirit” (1991):ダイナミクスで塊を“踊らせる”90s文法の代表。
※8〜10は一般的知識として挙げた参考曲。一次典拠が必要な歴史部分は上掲の出典に依拠している。
まとめ ── 名付けよりも“共有知”としての強さ
“誰が言い出したか”という問いは、しばしばロックの俗語に難しい。パワーコードも例外ではない。だが、名付け親が不明でもサウンドは明白だ。50年代のブルース録音で芽吹き、リンク・レイがアイコン化し、60年代ビート群が骨格に変え、70年代以降の大衆音楽の表現装置として制度化された。80年代にはギター教本が“Power chords”を当然視し、90年代の批評文でも“当たり前の語”として使われる。いま我々がE5を握ってアンプに火を入れるたび、その連綿とした“共有知”の歴史に指を掛けているのだ。
※本コラムは筆者の見解であり、諸説あります

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。







