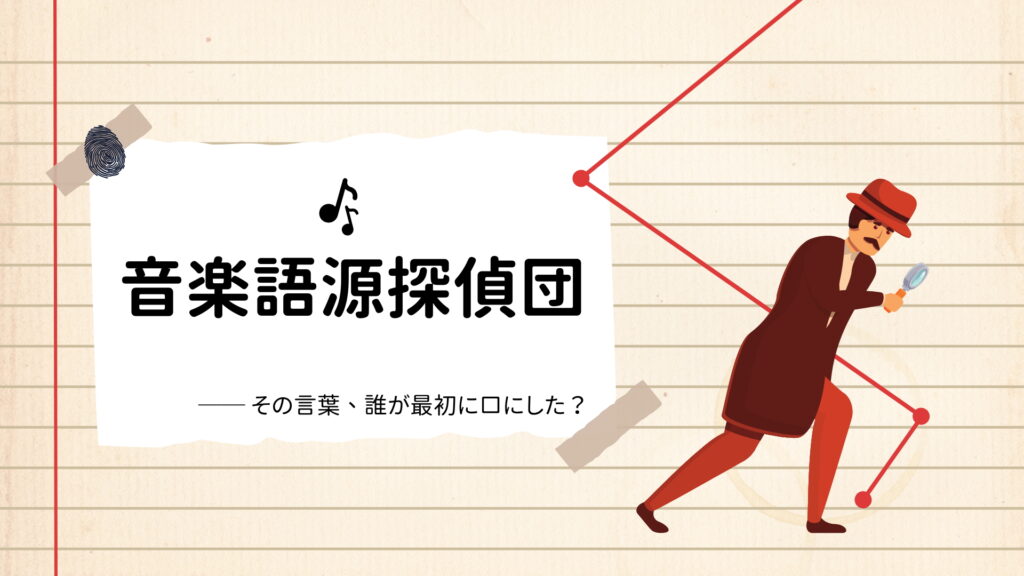
序章:そもそも「現代音楽」とは何なのか?
「現代音楽」と聞いて、どんな音楽を想像するだろうか? 複雑でわかりづらい旋律、不協和音の連続、静寂やノイズ、あるいは無音。クラシックともポップスとも異なるその響きに、どこか近寄りがたさを覚える人も多いだろう。だが、それはある意味で正しい。なぜなら「現代音楽」という言葉自体が、既存の音楽の“わかりやすさ”に反旗を翻して生まれたものだからである。
とはいえ、「現代音楽」はいつ、誰が、なぜ言い出したのか? この問いに明確な答えはない。だが、その輪郭を描き出すために、本稿では3人の人物に注目する。未来を妄想したブゾーニ、革命を設計したシェーンベルク、そして制度を構築したブーレーズ。そして最終的に、音楽の意味そのものを解体したジョン・ケージ。この4人を軸に、「現代音楽」という言葉の正体を探ってみよう。
第一章:未来の音楽を妄想した男 ── フェルッチョ・ブゾーニ
19世紀末、西洋音楽はひとつの飽和点に達していた。マーラーは交響曲を巨大化させ、ワーグナーはオペラを哲学へと昇華した。だが、どれほど豊かに見えても、それは終焉の兆しでもあった。
そんな時代に登場したのが、イタリア出身のピアニスト/作曲家、フェルッチョ・ブゾーニである。彼は1907年に『音楽の新しい美学』という論文を発表し、そこにおいて「伝統的な調性の崩壊」「電気的な音の使用」「無限の音階」など、当時としては突飛とも言えるアイディアを提示した。
音楽は未完成な芸術である。未来の音楽は、未だ知られざる技術によって発展するだろう。
彼の主張はまさに妄想のようだったが、その妄想こそが20世紀音楽の出発点となった。
第二章:調性を壊した革命児 ── シェーンベルクと新ウィーン楽派
フェルッチョ・ブゾーニの未来予想図を、具体的な作曲技法へと変換したのが、アルノルト・シェーンベルクである。彼は20世紀初頭、従来の調性(トニックとドミナントの関係)を放棄し、自由な無調音楽へと舵を切る。そして1920年代には、それを理論化した「十二音技法(Dodekaphonie)」を開発する。
十二音技法とは、12の全ての音を一度ずつ使う音列を基本に作曲する方法で、どの音にも“主音”としての特権を与えない。これは音楽の民主化ともいえる発想であり、同時に旋律や和声の美しさを犠牲にする革命でもあった。
彼の弟子であるベルクとウェーベルンは、この技法をそれぞれの方向に深化させる。ベルクはロマン主義の情感を残し、ウェーベルンは徹底的に構造化されたミニマルな音楽を追求した。
第三章:「現代音楽」という制度──ブーレーズと戦後ヨーロッパの再構築
第二次世界大戦後、ナチスの文化弾圧や戦火によって壊滅したヨーロッパ音楽界を再構築する必要があった。その中心となったのが、ドイツのダルムシュタットで行われた「夏期現代音楽講習会」(1947年〜)である。
ここに集まった若い作曲家たちは、戦前の音楽に対する批判意識を共有していた。中でもフランス出身のピエール・ブーレーズは、過去を徹底的に否定することで、新たな音楽の創造を宣言する。
ドビュッシー以降の音楽は、全て焼き払うべきである。
この過激な言葉の裏には、シリアスで純粋な芸術への渇望があった。彼らはアドルノらの哲学的支援を受け、現代音楽を「苦痛としての芸術」「思考としての音楽」として理論武装し、制度化していった。現代音楽はこの時期、「作曲家のための音楽」へと変貌する。
第四章:音楽をゼロに戻す──ジョン・ケージの沈黙と偶然性
制度化された「現代音楽」に対し、別の角度からそれを破壊したのがアメリカのジョン・ケージである。彼は音の秩序よりも、「音が存在することそのもの」に注目した。
もっとも有名なのは、《4分33秒》という作品。演奏者は何も演奏せず、観客は会場の環境音(咳払い、椅子のきしみ、風の音)を聴くことになる。これによって、「音楽とは何か?」という根源的な問いが突きつけられた。
ケージはまた、易経を使った偶然性の作曲や、準備されたピアノなどの手法で、音楽の領域を拡張した。これは、理性や秩序を重視するヨーロッパ前衛とは対照的であった。
第五章:日本における現代音楽──武満徹という翻訳者
日本において「現代音楽」が紹介されたのは戦後のことである。武満徹はその最前線に立ち、ヨーロッパ前衛とは異なる音響感覚を持ち込んだ。
彼の作品には、西洋的な構造ではなく、「間(ま)」や「余白」、「自然との共鳴」といった日本的な感性が宿る。その音楽は、激しさではなく静けさ、論理よりも気配を重視していた。
終章:「現代音楽」はもう“現代”ではない?
2020年代の今、「現代音楽」という言葉はもはや過去の制度となりつつある。かつてのように権威ある場での発表が中心ではなく、実験音楽やサウンドアートとして、より広い領域へ拡散している。
現代音楽は今や“ジャンル”ではなく、“態度”である。音楽に対して、どこまで問いを立てられるか。その問いの系譜に、シェーンベルクも、ブーレーズも、ケージも、そしてブゾーニもいた。彼らの妄想は、今も音楽の未来をかすかに照らし続けているのだ。

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。







