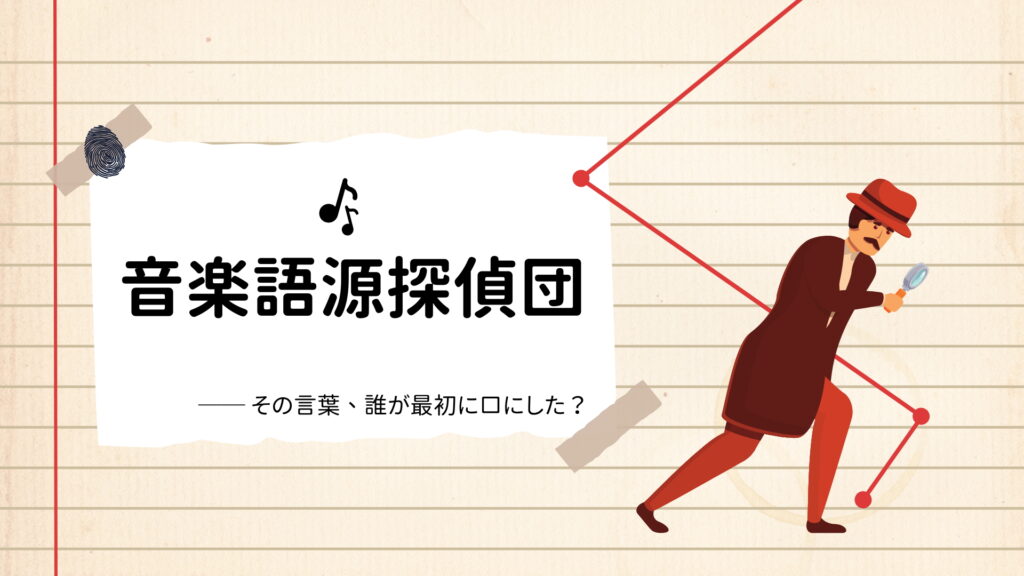
ギター奏者にとって「チョーキング(string bending)」は、もっとも感情を伝えやすい技法のひとつである。音を押し上げ、唸らせ、時には泣かせるような表現が、指先のほんのわずかな力加減で生み出される。ピアノにはできず、サックスにも難しい、まさにギターならではのこの「揺らぎ」は、どのようにして発明されたのか? そして、誰が最初に弦を持ち上げて音楽の表情を変えたのか?
その問いに答えるためには、まず「チョーキング」とは何か、そしてそれがどのように音楽文化の中で位置づけられてきたのかを、歴史のなかに探る必要がある。
「チョーキング」という奏法
チョーキングとは、ギターの弦を指で上(または下)に引き上げることで、音程を上昇させる技法である。通常は半音~1音程度のピッチ変化が用いられるが、場合によってはそれ以上の“ビッグ・チョーキング”も行われる。単なるピッチの移動ではなく、チョーキングはギターが「歌う」ための技法であり、奏者のフィーリングやグルーヴを直接的に伝える手段である。
しかし、このような奏法がクラシック音楽や他の伝統的な弦楽器にはほとんど存在しないことを考えると、チョーキングは比較的新しい、そして特異な表現技術であると言える。
最初に弦を“持ち上げた”のは誰か?
この問いに対して、明確な答えは存在しない。チョーキングが初めて歴史に登場した瞬間は、記録としては残っていないのだ。だが、音楽史を紐解くと、その萌芽は20世紀初頭、アメリカ南部の黒人コミュニティから発展したブルースの中にあるとされている。
特に重要なのが、アフリカ起源の音楽文化に見られる「揺らぎ」や「微分音」の概念である。アフリカの伝統楽器には、弦を揺らしたり、音を引き延ばすような奏法が存在していた。これらが奴隷制度を経てアメリカに渡り、ブルース、ゴスペル、フィールド・ホラーといった黒人音楽の中で再解釈され、ギター演奏にも自然と取り込まれていったと考えられている。
つまり、「誰が最初にチョーキングをしたか」という問いに対しては、「多くの無名のプレイヤーが口伝的に共有してきた」と答えるほかない。とはいえ、記録に残る最初期のチョーキング奏者を探すことはできる。
Tボーン・ウォーカー ── エレキギターでの“うねり”の始祖
1940年代のブルース・ギタリスト、Tボーン・ウォーカーは、チョーキングという表現を明確に意識的に使った、最初の重要人物とされる。彼はジャンプ・ブルースの名手として知られ、ジャズにも通じる洗練されたコードワークと、泣き叫ぶようなリードプレイを得意とした。
ウォーカーの代表曲「Call It Stormy Monday」では、チョーキングを駆使したメロディラインが印象的である。彼の弾き方は、明らかに「音を持ち上げて感情を込める」という意図が感じられ、それまでのバンジョーやアコースティック・ブルースとは一線を画していた。
Walkerは、エレキギターという新しい楽器が持つ可能性をいち早く見抜き、それを声のように“歌わせる”ための手段としてチョーキングを用いた。その意味で、チョーキングをギター奏法の中心に据えた最初の人物といえるだろう。
B.B.キング ── “泣き”のチョーキング
Walkerのスタイルを受け継ぎつつ、それをさらに深化させたのがB.B.キングである。彼は「Lucille」と名付けたギターを手に、まるでボーカルのような滑らかで情感にあふれるフレーズを奏でた。
キングのチョーキングは独特で、1音以上音程を上げたうえでビブラートをかけることで、まるで声帯の震えのような表現を実現している。彼自身、「私はギターで歌っているんだ」と語っていたように、チョーキングはB.B.キングの音楽哲学そのものだった。
アルバート・キング ── チョーキングの重戦車
さらに、もう一人の“キング”も忘れてはならない。アルバート・キングは、チョーキングを「力でねじ伏せる」かのように使うギタリストであった。左利きで右利き用のギターを逆さに持ち、太い弦を下方向にチョーキングするという異端の奏法で、他にはない重厚なサウンドを生み出した。
アルバート・キングのチョーキングは、後進のギタリストに計り知れない影響を与えた。特にジミ・ヘンドリックスやスティーヴィー・レイ・ヴォーンは、彼の「1音上げて泣かせる」スタイルを継承し、それをロックの文脈に落とし込んでいった。
ジミ・ヘンドリックス ── チョーキングと宇宙の融合
ブルースの伝統を受け継ぎながらも、まったく新しい次元でチョーキングを展開したのがジミ・ヘンドリックスである。彼は指の力と感性を極限まで高め、1音チョーキングから1音半、2音以上に至るまで自在に操った。しかも、それをステージ上で歯で弾きながら、あるいはギターを背中にまわして演奏するというエンターテインメント性も備えていた。
チョーキングは、彼のギターが“叫ぶ”ための言語であった。曲の途中で一音を無理やり押し上げることで、爆発的な情感を表現する。まるで怒り、涙、恍惚を一音に込めるようにして。
チョーキングの現在地
現代において、チョーキングはもはや特殊な奏法ではなく、「当たり前」の表現技法となっている。エレキギターにおいて、フレーズを語るうえでチョーキングを用いないギタリストを探すほうが難しいだろう。
さらに、ハーモニクスとの複合、チョークダウン(押し下げ)、ユニゾン・チョーキング、プリベンドなど、さまざまなバリエーションが開発されており、テクニカル系からジャズ、R&B、ポストロックに至るまで、ジャンルを超えて活用されている。
また、日本のギタリストにおいても、Charや布袋寅泰、山岸潤史らがチョーキングを重要な表現手段として用いてきた。言語を超えた“情感の呼吸”として、チョーキングは世界中のギタリストに共有されている。
結び──最初の“ひと押し”の、その後
誰が最初にチョーキングをしたのか ── その問いに明確な答えを出すことはできない。おそらく、それは名もなきブルースマンがある日、気まぐれに指を横にずらしてみた瞬間だったかもしれない。あるいは、Tボーン・ウォーカーが観客の前で「こんな音も出せるんだ」と得意げに披露したステージ上の一幕だったかもしれない。
重要なのは、その「ひと押し」が、音楽の世界に永遠の“感情のうねり”をもたらしたという事実である。チョーキングは、機械的な楽譜では表せない、血と涙と叫びの痕跡であり、それを受け継いだギタリストたちが、今も世界中でその音を持ち上げ続けている。
※本コラムは筆者の見解であり諸説あります。

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。







