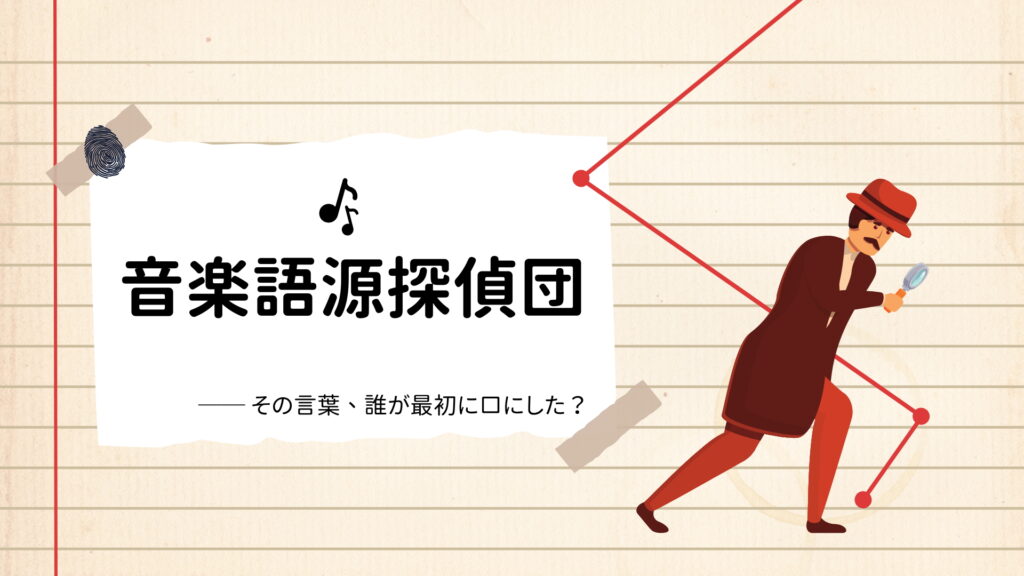
「ライブハウス」という言葉を聞いて、どこか懐かしさを覚える人は多いだろう。煌びやかなステージ、耳をつんざくような音圧、観客との一体感 ── ライブハウスは青春の記憶であり、文化の交差点である。しかし、冷静に考えてみると、この言葉はどこか奇妙である。英語のようでいて、英語ではない。「ライブ」も「ハウス」も英単語だが、“Live House”という表現は英語圏では使われない。では、この言葉はいったい、誰が、いつ、どのようにして言い始めたのだろうか?
和製英語としての誕生
「ライブハウス」は和製英語である。1970年代の終わり頃から、徐々に使われ始めたとされる。前提として、この言葉は日本の特異な音楽文化の中から生まれた。もともと「ライブ(Live)」という言葉自体も、日本では「生演奏」や「生のパフォーマンス」という意味合いで広く受け入れられてきたが、英語では通常“concert”や“gig”といった言葉が使われる。
一方、「ハウス(House)」は“家”や“建物”を意味するが、ここでは「音楽が鳴る場所」という比喩的な意味を持っている。こうして「ライブ」と「ハウス」が結びつき、“音楽が生まれる場所”としての「ライブハウス」という言葉が生まれた。
渋谷・新宿 ──“音の家”が生まれた場所
この言葉の誕生を支えたのは、東京のナイトシーンである。1970年代後半、渋谷や新宿ではロック喫茶やジャズ喫茶が、次第に「演奏を楽しむ場」へと変化していった。なかでも1976年にオープンした新宿ロフト、1977年の渋谷屋根裏などは、若手バンドにとって登竜門的な存在であり、「ライブハウス」という言葉の定着に大きく貢献した。
彼らはそれを「ライブができる家」と呼んだ。実際、それらの箱は文字通り“ハウス”だった。決して広くはなく、音響も粗削りで、店主のこだわりで成り立っているような場所だった。だからこそ、そこには“育つ音楽”があった。人と人、音と音がぶつかり合う小さな空間が、「ライブハウス」という言葉にぴたりとはまったのである。

メディアが後押しした名詞化
この言葉が一般に広まっていったのは、1980年代に入ってからだ。音楽雑誌『ロッキンf』『音楽専科』『GB』などがこぞってこの言葉を使い始め、バンドブームの広がりとともに、若者たちの間で当たり前の言葉となった。
さらにラジオ番組でも「次は渋谷のライブハウスでライブがあります」といった告知が多用されるようになり、言葉が名詞化していった。「ライブをする場所」ではなく、「ライブハウスでライブをする」という言い回しが成立した時点で、この言葉は日本語として完全に定着したと言ってよい。
言葉が文化になるとき
言葉は、文化とともに育つ。ライブハウスという言葉には、単なる“建物”以上の意味がある。そこには、バンドマンたちの挫折と希望、オーディエンスの衝動と共鳴、そして現場を支えるスタッフの情熱が詰まっている。つまり「ライブハウス」とは、音楽が生まれる“場”であると同時に、“精神”そのものを指しているのだ。
例えば、80年代にはBOØWY、REBECCA、THE BLUE HEARTSなどがライブハウスから飛び立ち、90年代にはHi-STANDARDやNUMBER GIRL、2000年代にはアジカンやサカナクションなどが、その空間を通して音楽を進化させていった。ライブハウスは単なる登竜門ではなく、音楽の実験場であり、現場主義の象徴であった。
海外には存在しない“ライブハウス”という概念
英語圏では“Live House”という言葉は存在しない。アメリカやイギリスでは、音楽を演奏する会場は“club,” “venue,” “music hall,” “pub”などと呼ばれる。つまり、「ライブハウス」は完全に日本固有の文化であり、日本語でしか成立しえない表現なのである。
そのため、海外のアーティストが来日して「ライブハウス」という言葉に出会うと、戸惑うこともあるという。日本のライブハウスの多くは、音響や照明のクオリティが高く、スタッフの対応も丁寧で、かつ観客の集中力も非常に高い。だからこそ「Live House」という言葉には、英語では訳せない日本の音楽文化の空気が含まれているのだ。
「ライブハウス」は今、どこへ向かうのか
2020年以降のパンデミックを経て、ライブハウスは大きな転機を迎えている。多くの会場が一時休業、あるいは閉店に追い込まれた一方で、配信ライブやハイブリッドイベントといった新たな形も生まれてきた。
だが、依然として「ライブハウス」は、音楽にとってかけがえのない場所であり続けている。むしろ制限のなかで生まれた小さな音が、時代を照らす光になることもある。若い世代のミュージシャンが再び「ライブハウス」という言葉に惹かれ、そこで表現しようとしているのは、その証左である。
この言葉を「誰が最初に使ったのか」は、今もはっきりしない。けれど、そこに込められた情熱と衝動は、時代を超えて確かに受け継がれている。それが、「ライブハウス」という和製英語が、単なる言葉を超えて文化になったということなのだ。
あとがき
「ライブハウス」とは、単なる会場の名称ではなく、音楽の現場を支える人々の魂が宿った場所の総称である。たとえ英語圏にその言葉が存在しなくても、そこにある音楽の熱量は、世界共通で伝わる。今日もどこかで、誰かがその“音の家”で、音を鳴らし始めている。
※本コラムは筆者の見解であり、諸説あります

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。







