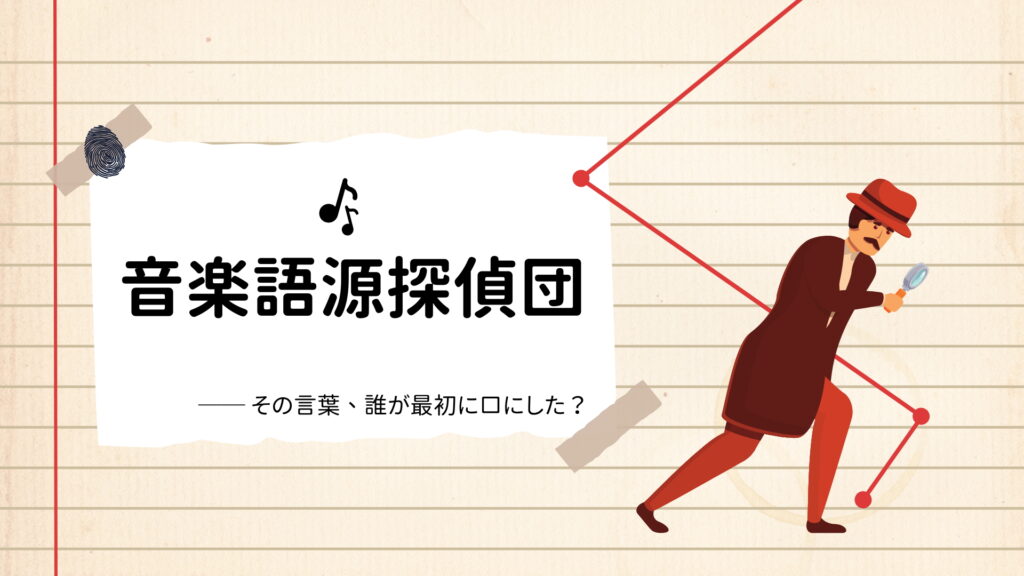
音楽の世界において、「チル(chill)」という言葉ほど、この数十年で意味が変容しつつも愛されてきた表現も珍しいのではないか。かつてはスラングに過ぎなかったこの言葉が、今ではジャンル名として、またリスニング体験そのものを言い表す代名詞として、あらゆる場面で用いられている。本稿では「チル」という言葉が音楽とどう出会い、どのようにして今日のような文脈に至ったのかを辿りつつ、その変遷を象徴するアーティストたちを紹介していきたい。

スラングとしての「Chill」
もともと「chill」という単語は、「冷える」「冷静になる」といった意味を持つ動詞・形容詞である。アメリカの黒人英語(AAVE)やヒッピー文化のスラングにおいては、1960年代以降、「落ち着く」「くつろぐ」という意味で用いられるようになった。特に1970年代のジャズ・ファンクやスモーキーなソウル・ミュージックの中では、こうした感覚が音楽体験そのものと結びついて語られることもあった。
例えば、1970年代のマーヴィン・ゲイやアイザック・ヘイズのようなアーティストは、「夜のムードを演出する」ような音楽を作り出し、「chill」の精神を先取りしていた存在である。もっとも、当時は「チル・ミュージック」といったジャンル名があったわけではなく、あくまで感覚的なレベルで語られていたに過ぎない。
アンビエントとダウンテンポ ── 90年代の「Chill Out」
「チル」が音楽のジャンル名として語られるようになるのは、1990年代のクラブ・カルチャーと密接に関わっている。クラブのバックルーム、いわゆる「チルアウト・ルーム(Chillout Room)」では、踊り疲れた人々がビートの緩やかな音楽を聴きながら、ソファに身を沈め、クールダウンする空間が用意されていた。このような空間で流れていた音楽 ── アンビエント、ダウンテンポ、トリップホップなど ── がやがて「チルアウト・ミュージック」として確立されていくのである。
代表的なアーティストには、ジ・オーブやエイフェックス・ツイン、マッシヴ・アタック、ポーティスヘッドなどが挙げられる。彼らの音楽には、ビートの緩さと空間の広がり、内省的な雰囲気が漂っており、「チル」という感覚を音響で体現していた。
また、この時代の象徴として忘れてはならないのが、イビサ島のクラブCafé del Marである。ここではDJのホセ・パディーヤによって選ばれたスローな楽曲たちが、海辺のサンセットとともに提供され、チルアウトという概念を広める重要な役割を果たした。
インターネットとChillの拡散
2000年代に入り、音楽の流通経路がフィジカルからデジタルへと移行する中で、「チル」はより曖昧かつ広義な意味を持ち始める。MySpaceやYouTube、SoundCloudなどのプラットフォームでは、ジャンルの境界が溶け、誰もが「chill vibes」や「relaxing beats」といったタグをつけて音楽を発表するようになった。
この文脈で登場したのが、いわゆる「Lo-fi Hip Hop」である。特にYouTubeで人気を博した「lofi hip hop radio – beats to relax/study to」は、ジャジーでスローなヒップホップ・ビートにアニメ風のループ映像を合わせたもので、若いリスナーの間で“チルの代名詞”となった。ここで流れる音楽には明確なジャンル名がなくても、「これはチルだ」と誰もが共通して認識するだけのニュアンスが存在していた。
このムーブメントを牽引したプロデューサーとしては、Nujabes(日本)、J・ディラ(米国)といった90年代~2000年代初頭のビートメイカーたちが挙げられる。彼らの音楽が、後のチルビートのプロトタイプとなった。
「チル」はジャンルではなく、感覚である
ここまで見てきたように、「チル」という言葉は音楽におけるジャンルというよりは、感覚や状態を表す言葉として使われてきた。つまり、「チルな音楽」は「このジャンルの音楽」というより、「このように感じる音楽」なのである。そのため、チルはローファイにもなり得るし、アンビエントにも、ボサノヴァにも、シティポップにもなる。
SpotifyやApple Musicといったストリーミング・サービスでも、「Chill Hits」「Chill Vibes」「Evening Chill」など、気分やシチュエーションに合わせたプレイリストが日々生まれている。そこに並ぶアーティストは、アリナ・バラズやJoji、マック・デマルコ、トム・ミッシュなど、ジャンルはバラバラでありながら、すべてが「チル」として括られる。

終わりなき「チル」の旅
結局のところ、「誰が最初にチルと言い出したのか」という問いに明確な答えはない。しかし、それは「チル」という言葉が、いつの時代もリスナーの身体感覚やライフスタイルと共鳴しながら進化してきた証であるとも言える。時にジャズ、時にエレクトロニカ、時にヒップホップとして姿を変えながら、「チル」はこれからも人々の耳元で静かに囁き続けるのだろう。
※本コラムは筆者の見解であり、諸説あります

Shin Kagawa:音楽の未来を自由に妄想し続ける、型破りな音楽ライター。AI作曲家による内省的なポップや、火星発のメロウ・ジャングルといった架空の音楽ジャンルに心を奪われ、現実逃避と未来の音楽シーンを行き来しながら執筆を続ける。幻想的なアイデアと現実のギャップを楽しむ日々の中で、好きな映画は『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。







