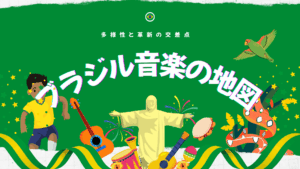ブラジルの音楽は、ただのジャンルやリズムの集まりではない。それは広大な国土に根を張る無数の文化の交差点であり、歴史的な重層性と現代的な革新が常に交錯しているダイナミックな音の海だ。本シリーズでは、サンバの起源から現代のクラブシーンに至るまで、ブラジル音楽の成り立ちとその豊かな多様性を深く掘り下げ、21世紀の音楽シーンにおける新しい潮流を追いかける。
本コラムを通じて、伝統的なサウンドの中にひそむ革新や、地域ごとのユニークな音の魅力に触れ、ブラジル音楽が持つ無限の可能性を再確認できるだろう。サンバの叙情的な情熱、ボサノヴァの静けさ、アフロ・ブラジルの鼓動、そして電子音楽との融合 ── それらが織りなすメロディとリズムは、世界中のリスナーに強い影響を与え続けている。
この8回のコラムを通じて、ブラジル音楽がどのように地域性と世界性を交わらせ、時代を越えて進化してきたのかを紐解いていく。音楽というアートフォームを超え、ブラジル音楽は文化、政治、アイデンティティを語る重要なメディアであることを、改めて感じさせられるに違いない。
さあ、ブラジル音楽の世界に再び足を踏み入れ、その無限の魅力を心ゆくまで味わってほしい。
バイーア ── それはブラジル音楽の母なる土地である。奴隷制度の時代にアフリカから連れてこられた人々が、命をかけて守り抜いたリズムと声が、サルヴァドールの路地に、海風に、カンドンブレの太鼓に、今もなお脈打っている。
ブラジル音楽の“黒い核”ともいえるアフロ・ブラジル音楽は、ただのジャンルではない。それは「存在の証明」であり、「抑圧への抵抗」であり、「世界との対話」である。そして何より、聴く者の心と体を“動かす”── それがこの音楽の魔法だ。
リズムの原風景 ── カンドンブレとアフロ・ブラジル宗教の影響
アフロ・ブラジル音楽の中心には、カンドンブレというアフリカ由来の宗教がある。これはヨルバやバントゥーの神々(オリシャ)を祀る信仰であり、音楽と踊りがその中心的な儀礼をなしている。
カンドンブレのドラム、特にアタバキの三重奏は、サンバやアシェー音楽、さらには現代のバイーア系ヒップホップにまで、深く浸透している。信仰と音楽、そしてコミュニティが一体となるこの構造は、まさに“生きたリズム文化”そのものである。
サンバの源流としてのバイーア
リオ・デ・ジャネイロで花開いたサンバは、実はバイーアをルーツに持つ音楽である。奴隷解放後、バイーアから都市へと移住した黒人コミュニティが、宗教儀礼の音楽や踊りを都市文化に融合させていった。
特に注目すべきはサンバ・ジ・ローダ。輪になって踊るこのスタイルには、カポエイラやアフリカの民俗舞踊と共通する要素が見られる。
サンバヘギとアシェー ── 祝祭と抵抗のダンスミュージック
1980年代に登場したサンバヘギは、アフロ・ブラジル音楽の新たな進化形である。レゲエ、ファンク、そして伝統的な太鼓隊(バテリア)を融合させ、巨大な打楽器編成で爆発的なグルーヴを生み出す。
このスタイルの先駆者であり象徴的存在が、オロドゥンだ。サルヴァドールのカーニバルでの圧倒的な存在感、社会活動への積極的な関与、そしてマイケル・ジャクソンとの共演によって、世界的に知られるようになった。
また、イレ・アイエやティンバラーダといったグループも、アシェー音楽と呼ばれる陽気でスピリチュアルなダンスミュージックを展開しながら、アフリカ系ブラジル人の誇りを打ち鳴らしている。
黒人文化運動と音楽 ──「声を取り戻す」ために
これらのグループは単なるバンドではない。教育、福祉、アイデンティティ確立のための「文化運動体」でもある。オロドゥンは若者に打楽器教育を行い、イレ・アイエは「黒人であることの誇り」をテーマにパレードを行う。
音楽は、差別に対する怒りを叫ぶ手段であり、希望をつなぐ合図であり、未来を創る手段だった。黒人音楽は、「被抑圧者の声なき声」が、ついに“声”として外に響き出した結果でもあるのだ。
現代への継承 ── Bバイアナシステムとバイーアのネオ・アフロ
現代においても、アフロ・ブラジルの精神は進化し続けている。たとえばバイアナシステムは、ダブやエレクトロニックを取り入れた音楽で、バイーア文化の新たな姿を世界に示している。
彼らの音楽は、伝統と現代をつなぐ“都市のサウンドシステム”であり、社会運動のサウンドトラックでもある。まさに、黒い詩学の現在進行形だ。
アフロ・ブラジルの鼓動は止まらない
バイーアのリズムは、ただ踊らせるだけではない。歴史の痛みを記憶し、誇りを鼓動に変え、未来への連帯を築いていく。アフロ・ブラジルの音楽は、「楽しい」だけでは語りきれない。そこには、失われたものを取り戻し、沈黙を破って語りはじめた人々の、深い祈りと叫びがある。
次回予告:第6回「街角の声、現代ブラジルのヒップホップとファヴェーラビート」
次回はサンパウロやリオのストリートから発信される、現代のリアルを映すヒップホップ、そしてファヴェーラの電子音楽・ファンキ(ファンキ・カリオカ)へと突入。デジタル時代の新しい表現者たちの声を追っていきます。

Jiro Soundwave:ジャンルレス化が進む現代音楽シーンにあえて一石を投じる、異端の音楽ライター。ジャンルという「物差し」を手に、音の輪郭を描き直すことを信条とする。90年代レイヴと民族音楽に深い愛着を持ち、月に一度の中古レコード店巡礼を欠かさない。励ましのお便りは、どうぞ郵便で編集部まで──音と言葉をめぐる往復書簡を、今日も心待ちにしている。