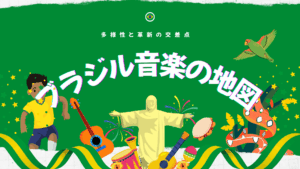ブラジルの音楽は、ただのジャンルやリズムの集まりではない。それは広大な国土に根を張る無数の文化の交差点であり、歴史的な重層性と現代的な革新が常に交錯しているダイナミックな音の海だ。本シリーズでは、サンバの起源から現代のクラブシーンに至るまで、ブラジル音楽の成り立ちとその豊かな多様性を深く掘り下げ、21世紀の音楽シーンにおける新しい潮流を追いかける。
本コラムを通じて、伝統的なサウンドの中にひそむ革新や、地域ごとのユニークな音の魅力に触れ、ブラジル音楽が持つ無限の可能性を再確認できるだろう。サンバの叙情的な情熱、ボサノヴァの静けさ、アフロ・ブラジルの鼓動、そして電子音楽との融合 ── それらが織りなすメロディとリズムは、世界中のリスナーに強い影響を与え続けている。
この8回のコラムを通じて、ブラジル音楽がどのように地域性と世界性を交わらせ、時代を越えて進化してきたのかを紐解いていく。音楽というアートフォームを超え、ブラジル音楽は文化、政治、アイデンティティを語る重要なメディアであることを、改めて感じさせられるに違いない。
さあ、ブラジル音楽の世界に再び足を踏み入れ、その無限の魅力を心ゆくまで味わってほしい。
1964年、ブラジルで軍事クーデターが勃発し、以後21年にわたり軍政が続くことになる。この政治的抑圧の時代、アーティストたちは、沈黙するか、迎合するか、あるいは ── 音楽で抗うかの選択を迫られた。そんな中で生まれたのが、「MPB(ムジカ・ポプラール・ブラジレイラ)」と「トロピカリア」と呼ばれる新しい音楽運動である。ボサノヴァが個人の感性を磨いたなら、MPBとトロピカリアは「国の魂」を問い直す芸術運動だった。
MPBとは何か ── 大衆音楽の新しい姿
MPB(Música Popular Brasileira)とは、「ブラジルの大衆音楽」という意味だが、実際には「伝統と現代の融合」を体現するジャンル横断的な潮流である。1960年代半ば、若い世代の音楽家たちは、サンバ、ボサノヴァ、フォーク、ロック、ジャズといった多様な要素をミックスしながら、軍政下の現実や個人の思想、社会的メッセージを音楽に込めるようになった。
この時代を象徴するのが、エリス・レジーナのような卓越した歌手と、シコ・ブアルキのような詩的かつ政治的な作詞家である。彼らは歌の力で、大衆の心に火を灯し、同時に軍事政権の検閲と闘った。
シコ・ブアルキの「Construção」は、まるで実験音楽のように単語が反復される構造で、労働者の死と社会の機械化を鋭く描いた。リズムと構造を通して社会を批評する、まさにMPBの真骨頂である。
トロピカリアとは ── ブラジル的サイケデリア
MPBが「伝統の継承と刷新」なら、**トロピカリア(Tropicália)**は「爆発的な再構築」である。1967年、カエターノ・ヴェローゾとジルベルト・ジルを中心に始まったこの運動は、ブラジルの伝統音楽と欧米のロック、サイケデリック、アヴァンギャルドを大胆に融合させた。
彼らは、アート、映像、ファッション、詩などの感覚をも横断しながら、「何でもあり」のカーニバル的精神で、ブラジルの文化を再定義しようと試みた。これは政治に対する挑発であると同時に、国民の精神構造に揺さぶりをかける芸術的革命だった。
カエターノの「Tropicália」は、ブリコラージュ的な詩とコラージュ的な音響で構成され、まるで音楽の万華鏡のようである。一方、ジルの「Domingo no Parque」は、暴力的な事件をあえてリズミカルに語り、社会の矛盾をエンターテインメントとして突きつける。
Os Mutantes ── ロックとユーモアの革命児
この運動をさらに彩ったのが、サンパウロ出身のサイケ・バンド「オス・ムタンチス」である。彼らは、ビートルズやジミ・ヘンドリックスに影響を受けながらも、ブラジル独自のカオス感覚で音楽を再構築した。
アルバム『Tropicália ou Panis et Circenses』は、この運動のマニフェストともいえる作品で、トロピカリアの精神を凝縮した一枚である。リスナーを戸惑わせ、笑わせ、そして考えさせるこの音楽は、「わかりやすさ」への挑戦状でもあった。
弾圧と亡命 ── 歌う自由への代償
トロピカリアは、その挑発的な表現ゆえに政府の検閲と弾圧の対象となった。カエターノ・ヴェローゾとジルベルト・ジルは1969年に逮捕され、ロンドンへの亡命を余儀なくされる。だが彼らは国外でも創作を止めず、異国での体験を通してさらに多様な音楽性を獲得していった。
この時期のカエターノの音楽は、静かな内省と世界へのまなざしに満ちている。亡命とは、自由を奪われることでありながら、新しい自由を獲得する旅でもあった。
トロピカリアの遺産──「混ざること」こそアイデンティティ
トロピカリアは1~2年という短命なムーブメントであったが、その精神はその後のブラジル音楽に決定的な影響を与えた。「ジャンルを越境し、伝統と革新を同時に肯定する」姿勢は、現代のミュージシャンたちにも脈々と受け継がれている。
カエターノ・ヴェローゾは後にこう語っている ──「トロピカリアは、ブラジルを“ブラジル的”にするための運動ではなく、ブラジルが“世界的”であることを証明するための運動だった」と。
次回予告:第5回「アフロ・ブラジルの鼓動 ── バイーアからの黒い詩学」
次回は、バイーア州を中心に受け継がれてきたアフリカ系文化に注目し、サンバヘギやアシェー、カンドンブレの影響を受けた音楽たちの歴史をたどる。ブラジルにおける黒人文化の誇りと抵抗の声 ── その豊かさに迫っていく。

Jiro Soundwave:ジャンルレス化が進む現代音楽シーンにあえて一石を投じる、異端の音楽ライター。ジャンルという「物差し」を手に、音の輪郭を描き直すことを信条とする。90年代レイヴと民族音楽に深い愛着を持ち、月に一度の中古レコード店巡礼を欠かさない。励ましのお便りは、どうぞ郵便で編集部まで──音と言葉をめぐる往復書簡を、今日も心待ちにしている。