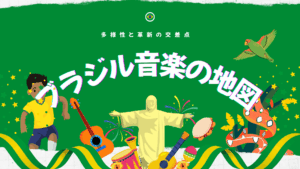ブラジルの音楽は、ただのジャンルやリズムの集まりではない。それは広大な国土に根を張る無数の文化の交差点であり、歴史的な重層性と現代的な革新が常に交錯しているダイナミックな音の海だ。本シリーズでは、サンバの起源から現代のクラブシーンに至るまで、ブラジル音楽の成り立ちとその豊かな多様性を深く掘り下げ、21世紀の音楽シーンにおける新しい潮流を追いかける。
本コラムを通じて、伝統的なサウンドの中にひそむ革新や、地域ごとのユニークな音の魅力に触れ、ブラジル音楽が持つ無限の可能性を再確認できるだろう。サンバの叙情的な情熱、ボサノヴァの静けさ、アフロ・ブラジルの鼓動、そして電子音楽との融合 ── それらが織りなすメロディとリズムは、世界中のリスナーに強い影響を与え続けている。
この8回のコラムを通じて、ブラジル音楽がどのように地域性と世界性を交わらせ、時代を越えて進化してきたのかを紐解いていく。音楽というアートフォームを超え、ブラジル音楽は文化、政治、アイデンティティを語る重要なメディアであることを、改めて感じさせられるに違いない。
さあ、ブラジル音楽の世界に再び足を踏み入れ、その無限の魅力を心ゆくまで味わってほしい。
ブラジル音楽とは何か? サンバ、ボサノヴァ、トロピカリア ── これらの言葉は確かに広く知られているが、それだけでは到底この音楽文化の全貌を言い表すことはできない。むしろ、ブラジル音楽を特徴づけているのは「多様性」そのものである。そしてその多様性は、地理的広がりやジャンルの分類以前に、「音楽が生まれる土壌」に根差している。すなわち、ブラジルという国の歴史、民族構成、宗教、階級、そして日々の生活が交錯するなかで醸成された「リズムのるつぼ」こそが、ブラジル音楽の核心なのである。
三つの起源 ── 先住民、アフリカ、ヨーロッパ
ブラジル音楽の地層をひもとくと、まずは三つの大きな文化的起源に辿り着く。先住民のリズム、アフリカから連れてこられた奴隷たちの打楽器、そしてポルトガルをはじめとするヨーロッパ音楽の旋律と和声。これらが混ざり合い、時に衝突しながらも、独自の形をとって発展してきた。
とりわけ重要なのは、アフリカ系ブラジル人の影響である。17世紀から19世紀にかけて、ブラジルには400万人以上のアフリカ人が奴隷として連れてこられた。彼らの宗教儀式や労働歌に根ざしたリズムは、現在のサンバ、マラカトゥ、アシェーといった多くのジャンルの基礎となっている。例えば、ボディーパーカッションのグループBarbatuquesによる「Baianá」は、アフロ・ブラジル音楽の遺産を現代的に再解釈した好例である。
一方、ポルトガルから持ち込まれたヨーロッパ音楽 ── とりわけポルカ、ファド、クラシック音楽 ── もまた、ブラジル音楽のメロディやハーモニーに深い影響を与えてきた。加えて、先住民族が保持していた素朴な打楽器や旋律的な歌唱も、地方音楽の根に息づいている。
「ショーロ」というブラジル音楽の出発点
こうした文化の交差点から最初に結実した都市音楽が「ショーロ」である。19世紀末のリオ・デ・ジャネイロで誕生したこのインストゥルメンタル音楽は、ポルカやワルツにアフリカ的なリズムの自由さを加えたもので、言うなれば「ブラジル版のクラシックジャズ」のような存在である。
代表的作曲家ピシンギーニャは、その技巧と情感を兼ね備えた演奏でショーロを芸術の域に押し上げた。彼の代表作「Carinhoso」は、今なおブラジル人に愛される不朽の名曲である。
ショーロは、のちのサンバやボサノヴァの土台となる重要なジャンルであり、形式美と即興性のバランスという点においても、ブラジル音楽の性格をよく表している。
宗教と生活、音楽の垣根なき交錯
ブラジル音楽を語るうえで欠かせないのは、音楽が「生活に根ざしている」という事実である。音楽は決して舞台の上やスタジオの中だけのものではない。街角の祭り、カンドンブレの儀式、カポエイラの輪 ── そうした場所で音楽は生まれ、育まれ、受け継がれていく。
たとえば、アフロ・ブラジル宗教「カンドンブレ」におけるドラムのリズムは、霊的世界との交信を意味するものであるが、そこから派生したビートは、サンバやアシェーなどに多大な影響を与えてきた。
このように、宗教・生活・芸術の垣根を越えた場所にこそ、ブラジル音楽のリアルがある。つまりそれは「演奏される音楽」ではなく「生きられる音楽」なのである。
リズムが語る社会と歴史
リズムとは、単なる拍の連続ではない。ときにそれは、権力への抵抗の声であり、コミュニティの結束の証でもある。奴隷制度の中で抑圧されていた打楽器が、やがてサンバの中で解放される過程は、その象徴と言える。
ブラジル音楽は、社会と切り離せない。むしろそれは、社会そのもののリズムであり、歴史の身体化でもある。だからこそ、ブラジル音楽を知ることは、音楽ジャンルを覚えること以上に、「どうして音が生まれるのか」を知ることである。
次回予告:サンバはどこから来たのか?
こうして重層的な文化の交錯地点に立ったとき、次に見えてくるのが「サンバ」という音楽の登場である。だが、サンバは突然現れたものではない。それは、バイーアの宗教儀式からリオの都市文化への変容を経て、ようやく形を成す。次回は、ブラジル音楽の象徴的存在とも言えるサンバの歴史に踏み込み、その社会的意味と音楽的進化について解き明かしていく。

Jiro Soundwave:ジャンルレス化が進む現代音楽シーンにあえて一石を投じる、異端の音楽ライター。ジャンルという「物差し」を手に、音の輪郭を描き直すことを信条とする。90年代レイヴと民族音楽に深い愛着を持ち、月に一度の中古レコード店巡礼を欠かさない。励ましのお便りは、どうぞ郵便で編集部まで──音と言葉をめぐる往復書簡を、今日も心待ちにしている。