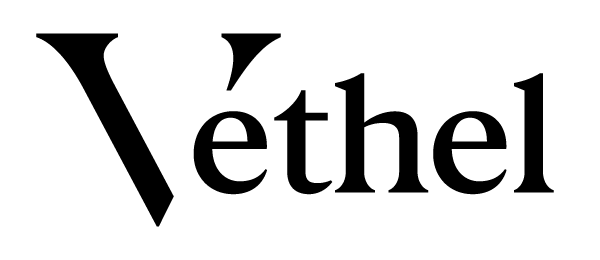AIが再構築した名曲たちを紹介するコラム「AIが奏でる“人間らしさ”という病」。第3回となる今回は、初の“邦楽編”だ。
AIが邦楽をアレンジし直すとき、そこには必ず“文化翻訳”が生まれる。日本語特有のイントネーションや母音の響き、言葉の置き方 ── これまで人間が無意識に行なってきた表現の細部を、AIがどのように読み取り、どう再構築するのか。
今回取り上げる3曲は、同じ時代に生まれたものもあれば、まったく異なる背景を持つものもある。それぞれが本来属していた文脈から切り離され、AIによって別のスタイルへと置き換えられる過程には、違和感や精度の高さ、時に滑稽さすら混じり合う。
その揺れ幅の中に、“日本の歌心とは何か”という問いが静かに浮かび上がってくる。
B’z「ZERO – Gospel Funk / Soul ver.」
── ロックの衝動が、ソウルの息遣いと交差する
1992年にリリースされたB’zの「ZERO」を、AIはゴスペルとファンクを掛け合わせた祝祭的アレンジへと再構築。ハードロック感あふれる原曲が、ここでは高揚感に満ちた“立体的なグルーヴ”として息を吹き返す。
まず印象的なのは、暑苦しいほどソウルフルなボーカル。原曲にはないアドリブやシャウトが随所に差し込まれ、まるで即興的に煽りを入れるシンガーのようなエネルギーがほとばしる。
軽快なギターカッティングとタイトなドラムが作るビートは、ファンクのハネとロックの推進力を同時に保ちながら、コーラスとオルガンが加わることで、一気にゴスペル的な“祝祭性”が立ち上がる。
映像がなくても、教会で手拍子が響き渡るような情景が自然と浮かぶ。原曲の硬質な勢いを、より開放的なグルーヴへと翻訳した好例だ。
LUNA SEA「ROSIER – Funky AI Arrange (Disco Funk AOR)」
── 疾走するロックが、都会のグルーヴへと滑り込む
同じく1994年、ヴィジュアル系黄金期を象徴するLUNA SEAの代表曲「ROSIER」。原曲では疾走感のあるビートとボーカル・RYUICHIのシャウトが印象的だが、AIはそこに“アーバンなサウンドスケープ”を持ち込んだ。
イントロから漂うのは、AORとファンクの中間にあるような洗練されたサウンド。グルーヴィなリズムに軽やかなベースが絡み、思わず身体が揺れる。
ベーシスト・Jによる名セリフパートは、軽快なラップへと再解釈され、以降、フェイクとコーラスが絶妙に掛け合う構成は、ゴスプレのような緻密さを感じさせる。
原曲のカタルシスを残しながらも、AIはその“叫び”を“ハネるビート”へと変換する。ロックの熱を冷まさずに、ファンクのクールさをまとわせた、AI的リミックスの理想形だ。
Perfume「ポリリズム – Afrobeat / World Groove ver.」
── テクノポップが、原始の祝祭へと還る
まずは、何も考えずにこの動画を再生してほしい。Perfumeの代表曲「ポリリズム」(2007年)が、まさかアフロビートになるとは──驚きと笑い、そして妙な説得力が同居している。
ジャンベ、ベル、カリンバ……さまざまな民族楽器が独自のリズムを刻み、それらが重なり合って生まれるポリリズムは、まさにタイトルの自己言及的再構築だ。電子音ではなく“人力のリズム(を模したAIが構築したリズム)”によって再現されたこのグルーヴは、原曲の機械的精度とは対極にあるのに、なぜか本質を突いている。
自然への祈りや生命の循環を感じさせる土着的なサウンド。それはまるで、AIがテクノロジーの皮を脱ぎ捨て、太鼓のリズムに“人間の原初”を見出したようでもある。Perfumeのクールな未来音が、今、温かい地球の音楽として蘇る。
AIが“日本の歌心”をどう再現するのか
AIが邦楽を再構築する ── それは単なる翻訳ではなく、文化の鏡像を覗き込む行為だ。イントネーションの微妙なズレ、情感の揺れ、それらの“違和感”こそが、むしろAIが人間の音楽を理解しようとするプロセスそのものに思えてくる。
AIが日本語の歌を“正しく”歌えるようになる日。それは、私たち自身の“感情のアルゴリズム”が解読された日でもあるかもしれない。

舞音(まいね):カルチャーコラムニスト。音楽、文学、テクノロジーを横断しながら“感情の構造”をテーマに執筆。AIと人間の創作を対立ではなく共鳴として捉える視点が特徴。