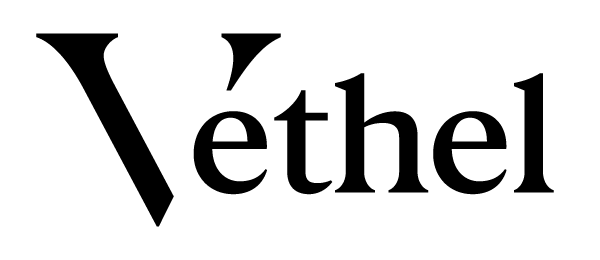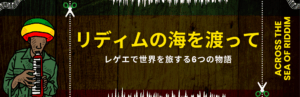強く、優しく、揺らめくように響く音。
レゲエはジャマイカの土の匂いとともに生まれ、やがて海を渡り、世界中の心に根を下ろした──。
なぜこの音楽はこれほど人を惹きつけるのか?
どこまでが「レゲエ」で、どこからがその先なのか?
本連載では、誕生から進化、拡張、そして現在へと続くレゲエの物語を、全6回で丁寧にひもといていく。
音楽としての魅力はもちろん、その背後にある歴史、思想、コミュニティにまで迫る旅。
きっと読み終えたとき、レゲエという言葉が、音楽以上の意味を持つはずである。
レゲエのビートが世界を揺らし始めた1970年代、ジャマイカのとある録音スタジオでは、表舞台とは別の革命が密かに進行していた。
それは、ただ“歌を聴かせる”ための音楽ではなく、“音そのものを操作する”という発想。そこから生まれたのが、レゲエの裏の主役 ── ダブである。
この回では、ダブとは何か、どのように発展し、どんな影響を世界にもたらしたのかを掘り下げていく。
ダブとは何か? ── “リミックス”の原点
「ダブ」という言葉は、もともと録音の“ダブ・プレート”に由来する。これは本来、レコードのテストプレス盤を意味していたが、やがて「ヴォーカルを削除し、リズムトラックを再構成したバージョン音源」のことを指すようになる。
最初期のダブは、ヴォーカル曲のB面に収録されるインストゥルメンタル・バージョンとして誕生した。DJがライブで“トースティング”(MC的な掛け声)を乗せるための土台として使われたのである。
だが、単なる伴奏では終わらなかった。エンジニアたちは次第にエコーやリバーブを加え、ドラムやベースを引き伸ばし、原曲とは異なる“音響の物語”を紡ぎ出していく。ダブとはつまり、リミックスの始祖であり、「音を創造的に加工する」という発想そのものだった。
革命家リー“スクラッチ”ペリーとブラック・アークの神話
このダブという実験を芸術の域にまで押し上げたのが、鬼才 リー“スクラッチ”ペリーである。彼の自宅兼スタジオ「ブラック・アーク」は、音の錬金術が日夜繰り広げられる“魔法の工房”であった。
ペリーは、録音されたトラックを分解し、再構成し、加工することによって、音楽の「見えない次元」を可視化しようとした。たとえば、マックス・ロメオの名作「War Ina Babylon」や、コンゴスの「Heart of the Congos」など、彼の手がけた作品には、独特の霧がかかったような音像がある。
彼のダブは、単なるエフェクトの遊びではない。それは「目には見えないスピリチュアリティ」を音に託す、深い表現行為であった。
キング・タビー ── ダブ・エンジニアという新たなアーティスト像
リー・ペリーと並ぶもうひとりの巨人が、キング・タビーである。もともと電気工の仕事をしていたタビーは、独自にカスタマイズしたミキサー卓を駆使し、音響操作を芸術に変えた男である。
彼の作品は、例えばオーガスタス・パブロとのコラボレーション「King Tubbys Meets Rockers Uptown」のように、リズムと空間の“揺らぎ”で構成されている。音の一部が突然フェードアウトしたかと思えば、ディレイの残響が空間を支配する。その音響世界には“静けさ”すらがビートの一部として作用し、聴き手はまるで音の中に沈み込むような感覚を味わう。キング・タビーは、演奏者ではない。だが、“音の編集によって物語を語る者”=アーティストとして、ダブというジャンルを確立した。
リズムの再利用 ──「リディム文化」の成立
ダブは、楽曲を再構成する文化だけでなく、「リディムを共有し使い回す」という発想も広めた。 ジャマイカではひとつのリディム(例:スレンテン、スタラグ、リアル・ロックなど)に対して、無数のアーティストが異なる歌詞とスタイルで曲を乗せる。 これは、DJカルチャーやヒップホップの「トラック共有」文化の原点とも言えるものである。ダブとは、リズムの再利用と改変を通じて、「音楽がひとつの共同体である」という思想を体現していると言える。
ダブから広がる世界 ── クラブ・ミュージックへの影響
ダブは、レゲエという枠をはるかに超えて、多くのジャンルに影響を及ぼした。
• ポストパンク(ザ・クラッシュ、パブリック・イメージ・リミテッド)
• ヒップホップ(グランドマスター・フラッシュなどのDJ文化)
• テクノ/ダブテクノ(ベーシック・チャンネル、Rhythm & Sound)
• ダブステップ(スクリーム、ブリアル)
特に1980~90年代のイギリスでは、ダブはサウンドシステム文化と結びつきながら、レイブ・カルチャーやアンダーグラウンド・クラブシーンの形成に大きな影響を与えた。
音響的な“スペース”の扱い方や、“ベース中心”の設計思想は、現代のクラブ・ミュージックの根底に深く流れ続けている。
まとめ:音を“彫刻”する芸術としてのダブ
ダブとは、「音楽の裏側にある構造を見せる芸術」である。それは、録音された音を“固定されたもの”ではなく、“可変の素材”として捉える発想だ。 演奏された瞬間に完成するのではなく、その後も音楽は「編集によって進化し続ける」という思想。 この柔軟な発想こそが、現代における音楽制作の基盤を形作った。
ダブを聴くとき、我々はただ音楽を聴いているのではない。音がどのように空間に作用するのか、そしてその空間がどのように我々を包み込むのか ── その実験に耳を傾けているのである。
次回・第4回では、レゲエと世界各地の音楽文化との交差 ── イギリス、アフリカ、日本などに広がった“ディアスポラとしてのレゲエ”の物語を描いていく。

Jiro Soundwave:ジャンルレス化が進む現代音楽シーンにあえて一石を投じる、異端の音楽ライター。ジャンルという「物差し」を手に、音の輪郭を描き直すことを信条とする。90年代レイヴと民族音楽に深い愛着を持ち、月に一度の中古レコード店巡礼を欠かさない。励ましのお便りは、どうぞ郵便で編集部まで──音と言葉をめぐる往復書簡を、今日も心待ちにしている。