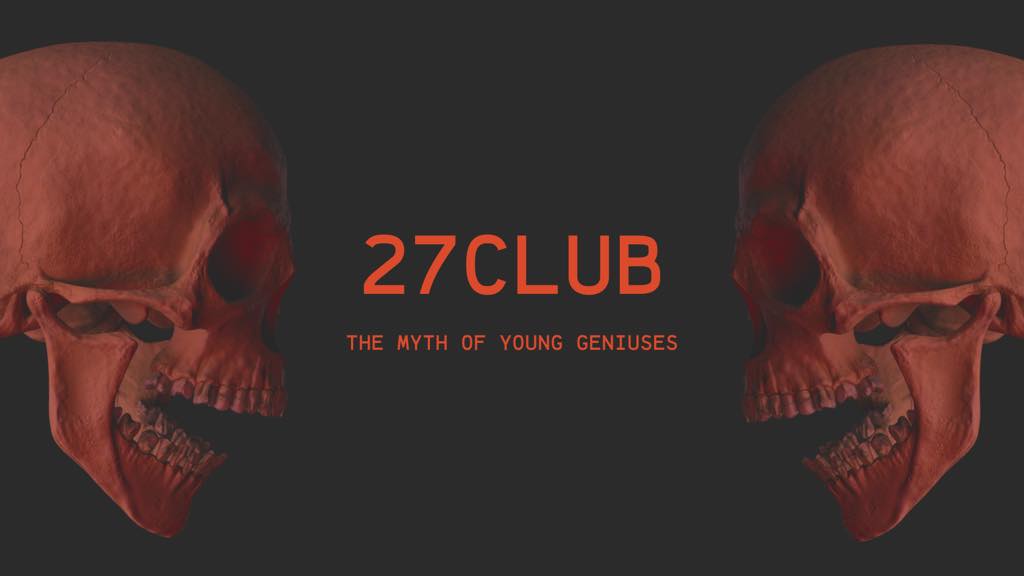
2011年7月23日、ロンドン北部カムデン地区にある自宅で、エイミー・ワインハウスが亡くなった。死因はアルコール中毒による急性中毒。享年27歳。その訃報は瞬く間に世界中に広まり、再び「27クラブ」という言葉がメディアに躍った。
1960~70年代のヘンドリックス、ジョプリン、モリソン、そして1990年代のカート・コバーンに続き、21世紀に入ってもなお「27歳の呪い」は更新され続けるのか──。その問いが再び浮上した瞬間であった。
ソウルフルな声を持つ「新しい古典」
エイミー・ワインハウスは1983年、ロンドンで生まれた。ジャズやソウルを愛する家庭に育ち、10代の頃から歌の才能を発揮。2003年にデビューアルバム『Frank』を発表し、その独特の歌声とジャズ的なフレージングで注目を集めた。だが真のブレイクは2006年、『Back to Black』のリリースによって訪れる。
このアルバムはモータウンや60年代ソウルの響きを現代的に蘇らせた傑作であり、世界中で大ヒットを記録した。特に代表曲“Rehab”は、自身のアルコール依存症を皮肉を込めて歌い上げた楽曲で、彼女のリアルな生き様と強烈にリンクしていた。
──「No, no, no」という拒絶のフレーズは、彼女の実生活と切り離せぬ象徴的な歌詞となり、音楽と人生が直結する彼女のスタイルを物語った。
メディアに消費される「トラブルメーカー」
しかし、ワインハウスは成功と同時にゴシップの渦中に置かれることとなった。ドラッグ使用、アルコール依存、恋人との破滅的な関係──。イギリスのタブロイド紙は彼女のスキャンダラスな側面を連日報じ、パパラッチは24時間彼女を追いかけた。
ワインハウスはメディアによる「監視」の犠牲者であったとも言える。60~70年代のアーティストが伝説となったのは死後の回想によってであったが、ワインハウスの場合、死に至る過程そのものがリアルタイムで消費された。髪を振り乱し、酩酊しながらステージに立つ姿がYouTubeで拡散され、その度に「破滅へと向かう歌姫」という物語が補強されていった。
ジェンダーと社会的期待
エイミー・ワインハウスの事例を語る上で重要なのは、ジェンダーの問題である。男性ロックスターの放蕩はしばしば「カリスマ」「破滅型の天才」と称賛されるが、女性アーティストの逸脱は「醜態」「失敗」としてより厳しく断罪される傾向がある。
ワインハウスはその典型例であった。彼女の才能は称賛されながらも、その生き方は徹底的に監視され、消費され続けた。
──恋愛の破綻と孤独を歌い上げるこの楽曲は、彼女の実人生そのものを映し出すようであり、聴く者に生々しい共感と痛みを与える。
「27歳の呪い」の現代的再演
ワインハウスの死によって、「27クラブ」という言葉は再び大きく取り上げられた。しかも今回はSNS時代に突入した直後であり、TwitterやFacebookを通じて瞬時に世界中で拡散された。ヘンドリックスやコバーンの死の際に比べ、情報の速度は桁違いであった。
ファンは追悼のメッセージを投稿し、ニュースサイトは「27クラブの最新メンバー」と見出しを打った。死が「瞬時に世界規模のイベント」となったのは、この時代の特異な特徴である。
産業としての「死の消費」
ワインハウスの死後、未発表音源やドキュメンタリー映画が次々とリリースされた。特に2015年のドキュメンタリー映画『AMY』は、彼女の才能と苦悩を克明に描き出し、アカデミー賞を受賞した。しかしそれは同時に、彼女の死がいかに文化産業に利用されるかを示す事例でもあった。
「27クラブ」は単なる偶然の年齢ではなく、音楽ビジネスにおける「死のブランド」として機能し始めたのである。
現代的な27クラブの意味
エイミー・ワインハウスの死は、21世紀の音楽文化における「27クラブ」の意味を更新した。それは単に「若き天才の早逝」ではなく、
- メディア監視社会の残酷さ
- ジェンダーに基づく差別的まなざし
- SNS時代の情報消費の速度
といった現代的文脈と結びついたのである。
この意味において、ワインハウスは「現代の27クラブ」の象徴であり、彼女の死は神話であると同時に、現実社会の歪みを映し出す鏡でもあった。
まとめ
第3回では、エイミー・ワインハウスを中心に「現代的な27クラブ」の意味を考察した。彼女の死は、メディアとSNSがアーティストをいかに消費するか、そして死さえも商業化されてしまう現実を浮き彫りにした。
次回は「心理学的背景──なぜ若き天才は早逝するのか」と題し、27クラブを心理学の視点から掘り下げる。

Jiro Soundwave:ジャンルレス化が進む現代音楽シーンにあえて一石を投じる、異端の音楽ライター。ジャンルという「物差し」を手に、音の輪郭を描き直すことを信条とする。90年代レイヴと民族音楽に深い愛着を持ち、月に一度の中古レコード店巡礼を欠かさない。励ましのお便りは、どうぞ郵便で編集部まで──音と言葉をめぐる往復書簡を、今日も心待ちにしている。








